(1)テキストをひたすら何度も読む
テキストを延々と何度も読み続ける行為は、2つの構造的欠陥があるため、勉強効率が非常に悪い。
まず、テキスト再読は「曖昧な内容の理解度向上」と「既知の内容の単なる復習」に大別できるが、惰性的な作業である後者の占める割合が大きい。
さらに、再読を繰り返す中で、「Aの次にはB。Bの次にはC」というふうに、内容そのものではなくテキスト上の順序を覚えがちなので、理解度の低い箇所に気づきにくい。
「テキストに下線」もやりがち
(2)下線を引いたりハイライトする
カラフルなペンで教科書や参考書を一生懸命にデコレーションする行為は、単なる遊びだ。下線を引いたりハイライトしたところで、内容が自分の頭に入るわけではない。
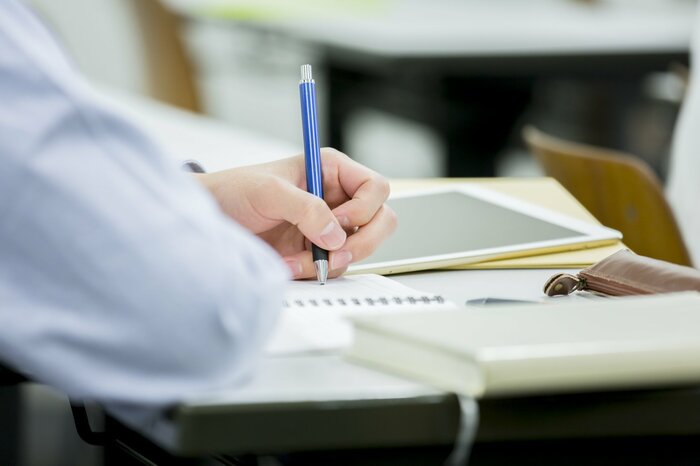
(3)ノートを取る
意図を持たずにノートを取る行為は、不毛である。ノートを取ったところで、教科書や参考書の劣化版を作っているに過ぎないからだ。
大事な箇所だけ取捨選択してメモするのは「あり」だが、何も考えずに惰性的にノートを取るのは「なし」だろう。
「目的を持たない人は、やがては零落する。全く目的がないぐらいなら、邪悪な目的でもある方がマシである」―トーマス・カーライル(英国の評論家・歴史家)
3つの科学的勉強法を駆使する
効率的な勉強法とは、冷静さと積極性に溢れた「勤勉な勉強法」を指す。意味のある努力は、ほぼ必ず報われる。
その典型例を次に示す。
(1)勉強する「前」に模擬試験を行う
(2)間隔を空けて練習と模擬試験を繰り返す
(3)質問形式でメモする
これらは全て、勉強である。直観に反するが、科学的には理にかなっている。
一つずつ解説していこう。





