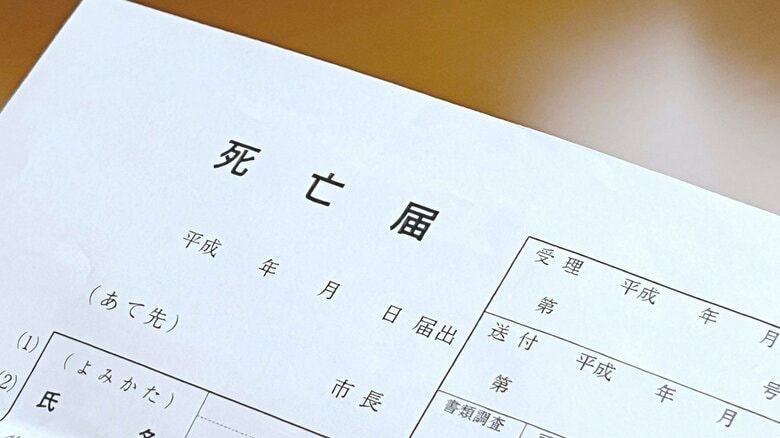また、家主・地主や病院長のなかには、「届出義務者」であっても、死亡届を出すことをためらう人もいます。
こうした場合、法に規定のない「死亡記載申出書」を提出することで、戸籍に死亡を記載する手続きが取られることもあります。
火葬を行うのは、どこの自治体か
死亡届が出された場合、火葬はどうなるのでしょうか。
身寄りのない人が亡くなった場合、自治体は戸籍などをたどって親族を探します。
親族が見つからなかったり、見つかっても関わりを拒んだりした場合、多くのケースでは自治体が火葬を行うことになります。
ここで問題になるのが、「火葬を行うのは、どこの自治体なのか」です。

自治体が火葬を行う根拠となっているのは「行旅病人及行旅死亡人取扱法」です。
行旅死亡人、つまり「行き倒れ」として扱われるため、原則として亡くなった場所の自治体が火葬を行うことになっているのです。
昔は家族や親族が葬儀を行って遺骨を引き取るのが当然であり、「引き取り手がいない」という事態を考える必要はさほどなかったのかもしれません。
しかし、独居高齢者が増えて、死後に引き取り手のないケースが増加傾向にあることを考えると、現在の法律には不備があるといわざるをえません。