生活に欠かせないティッシュペーパー。最近は店舗で箱のないソフトパック型のティッシュペーパーを見かける機会が増えたように思わないだろうか?実はここ数年、ソフトパック型のティッシュペーパーがじわりじわりと増えてきているのだ。
10年でソフトパック型のシェアが2割に
民間調査会社のインテージによると、2012年のティッシュペーパーのシェア(枚数構成比)はボックス(箱)型が96.9%、ソフトパック型が2.0%だった。しかし2022年には、ボックス型が78.5%、ソフトパック型が20.8%とソフトパック型のシェアは2割を占めるまでになった。

また、2023年1月~7月のシェアを確認すると、ボックス型が71.5%、ソフトパック型が27.7%と直近のデータでもソフトパック型のシェアが拡大している。これについて、インテージの市場アナリスト・木地利光氏は「ティッシュペーパーを含む各種消費財や光熱費などの値上がりが続く中、少しでも支出を抑えるため、単価の低いソフトパックの人気が高まっているものと考えられます」と分析している。
たしかに値段を比較してみると、インテージの調査によると150組5個入りの商品(2023年4月~7月の平均単価)の場合、ボックス型が257円、ソフトパック型は210円とソフトパック型の方が50円程度安い。
そんなソフトパック型のティッシュペーパーにはどんなメリットがあるのか?「クリネックス」を販売する日本製紙クレシアは、「消費者のメリットとしては、持ち運びにも便利で、容量が多く、コンパクトサイズになること」と話している。「エリエール」を販売する大王製紙はコンパクトであること以外に「箱がないため、使用後に分別の手間がかからず、ごみも小さく捨てることができる」「箱に比べて隙間なく紙を詰めることができ、企業側の物流効率が改善される」としている。
ボックス型は「取り出しやすさ」「保形性」
メリットも多いソフトパック型だが、今後、さらに増えていきそうか? 一方、ボックス型にはどんなメリットがあるのか? まずは、日本製紙クレシアの担当者に詳しく話を聞いてみた。
――なぜソフトパック型が増えてきた?
1パック当たりの価格の値ごろ感だと思います。
――ソフトパック型とボックス型、異なるのはパッケージだけで中身は変わらないの?
当社が2018年から発売している「クリネックス ティシュー ローション 肌うるる」は、持ち運んで使用することを想定しているので、シートサイズは異なります。シートそのものの品質は同じです。

――日本製紙クレシアでは、ソフトパック型は保湿タイプのみ発売されているが、通常タイプが発売されていない理由は?
市場において通常タイプのソフトパックは中国を中心とした輸入品が多く、低価格で売られており価格競争の激化が想定されるためです。ソフトパックのメリットは持ち運びの利便性と考えており、特に花粉症シーズンなどで肌に優しいタイプの商品の方が消費者ニーズに合致していると考えています。
また、家での使用を考えれば、取り出し性・デザイン性・保形性(外装・外箱の形状維持性)からも箱タイプの方が優れていることや、紙箱はリサイクルできるというサステナブルな視点からも紙箱の利点をしっかり伝えたいと考えています。
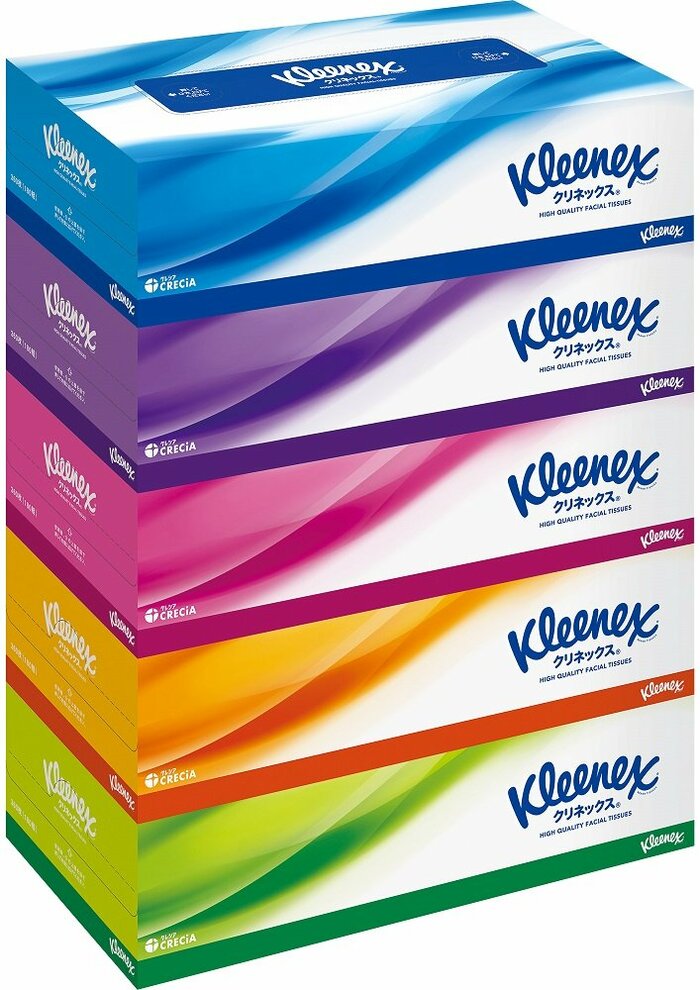
――ボックス型のメリットは?
消費者のメリットとしては、「1枚ずつの取り出しやすさ」や「保形性があること」です。企業側のメリットとしては、箱はエコなのでサステナブルな商品であることです。
消費者の使い分けがより一層進む
――それぞれここ数年で進化している部分はある?
(ボックス型)ボックスの取り出し口のビニールを無くしたものも発売しています。
(ソフトパック型)ソフトパックの形状で、包装を「紙」にした商品も発売しています。
――将来的にボックス型は消えていくと思う?
無くならないと思います。ボックスの利便性をご理解いただいていると思っています。当社としても紙箱は再生可能資源なので、今後の地球環境を鑑みると、もっと利用していくべきだと思っています。啓発も必要だと思っています。
――今後、ソフトパック型は増えていくと思う?
箱タイプのティシューは当社が日本で初めて発売していますが、2024年で60年になります。ソフトパックタイプはまだ15~16年足らずの歴史です。箱タイプとソフトパックのメリット・デメリットに対して、消費者の理解が進めば使い分けなども、より一層進むと考えています。
ソフトパック型の利便性が際立つ展開
では大王製紙はどうだろうか? ソフトパック型は今後、さらに増えていきそうか?ボックス型にはどんなメリットがあるのか?こちらも担当者に詳しく話を聞いてみた。
――なぜソフトパック型が増えてきた?
日本国内にソフトパックティシューが流通しだしたのは2007年頃、一般的に広まり始めたのは2012年頃です。当時から現在まで中国等からの輸入が主であり、特に価格帯の低い商品から広まっていきました。昨今では国産品や高品質な商品などのバリエーションが増え、ボックスティシューとソフトパックティシューが並び立ち、よりソフトパックの利便性が際立つ展開になっています。
――ソフトパック型だと輸送コストはどのくらい抑えられるの?
弊社の商品で物流効率を計算した際、10tトラック1台あたりに積載可能なティシュー重量は、箱ティシューと比較し、ソフトパックティシューは約1.5倍です。
――異なるのはパッケージだけで中身は変わらない?
当社商品について回答いたします。中身の紙の品質は同じブランドでは同じものを使用しています。一方、紙の幅などの大きさについては、持ち運んで使っていただくことや、省スペースでお使い頂ける利点を活かすため、ソフトパックティシューはコンパクトサイズに設計しています。
ソフトパック型の市場比はまだまだ伸びる
――ボックス型タイプのメリットは?
消費者のメリットは、取り出しやすいこと。企業側のメリットは箱が頑丈であり、商品陳列しやすいことです。
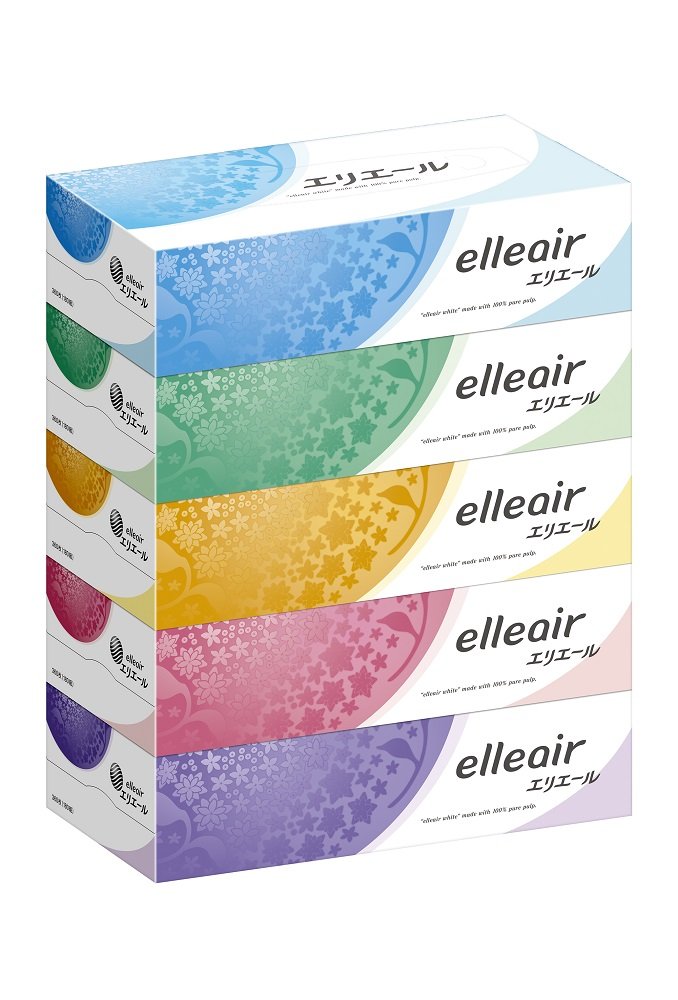
――それぞれここ数年で進化している部分はある?
当社では、ソフトパックティシューの「取り出し口」に着目し、一般的なペーパータオルのような取り出し口ではなく、円形状に加工した取り出し口を採用することで、最後まで取り出しやすい仕様にしています。

これにより、従来は「ソフトパックティシュー=取り出しにくい」ということで敬遠されていた方に使いやすさを実感いただき、ソフトパックティシューの市場が広がる結果になりました。さらに、保湿ティシューやエリエールティシューといった、ボックスティシューのみで展開していた高品質品についてもソフトパックタイプを展開することで、どちらのタイプも選択いただけるようにしています。
一方で、ボックスティシューは保湿ティシューやコットンフィールのような高品質商品を中心にリニューアルを重ねており、肌触りの良さを追求する改善を行っています。ボックスティシューは装飾も含めて高級商品の割合が多く、肌へのストレスの低さや厚みなどを期待する方に向けた商品改良を行っています。
――この先もソフトパック型は増えていく?ボックス型は消える?
まだまだ主流はボックスティシューです。ボックスティシューのメリットは取り出しやすさです。この点について、ソフトパックティシューは改良の余地があり、ボックスティシューがすぐになくなることにはならないと想定しています。ただし、ソフトパックティシューを一度使用した方は、継続使用の傾向が高く、引き続きソフトパックティシュー市場比は伸長すると想定しています。
値段が安く、コンパクトなソフトパック型は今後も伸びそうだ。しかし、「エコ」「保形性」「取り出しやすさ」のメリットのあるボックス型がまだまだ主流だいうこともわかった。消費者の私達はそれぞれのメリットを理解しつつ、使い分けていくことになりそうだ。






