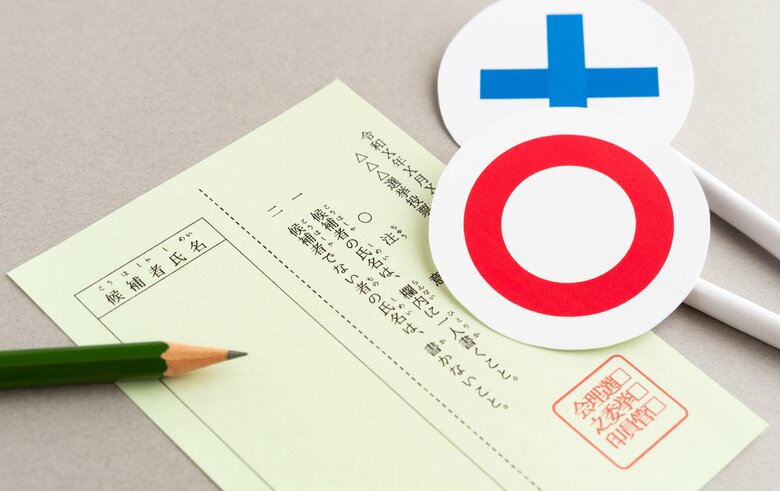今年は4年に一度の統一地方選の年
昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されました。
これを前に、全国の都道府県の知事や議員、市区町村長や議員を一斉に選んだのが統一地方選挙の始まりです。
その後は、知事や市長の途中死亡や辞職、市町村の合併、議会の解散などがあって「統一」して実施される選挙は減少する一方です。ぼくが入社したころ(1980年代)は、統一地方選の「華」といえば、東京都知事選と大阪府知事選でしたが、今はどちらも選挙の時期がずれてしまいました。不謹慎を承知で言えば、全国放送のテレビ的には「あまりおいしくないコンテンツ」になってしまったのかもしれません。
それはさておき
「地方自治は民主主義の学校」と言われます。
身近な問題を解決するために代表者を選出し、代表者が話し合って解決策を決定する。
大きな問題を抱えた自治体ではそうした原則が生かされているでしょう。一方、有権者の多くが政治・行政に期待する課題がそれほどない自治体も少なくありません。というか、ありがたいことに切実な問題を抱えていない自治体の方が多いのが実際だと思います。
4年前の統一地方選では41の道府県議会選挙で、945の選挙区のうち371の選挙区で定員を超える候補者がなく無投票で議員が決まりました。全体の3分の1以上の選挙区で投票が行われなかった、ということです。
知らない人に投票する
ぼくたちが最初に選挙に触れるのは「学級委員選挙」だと思うのですが、それでいいですか?1960年代はそんな感じだったと思います。
学級委員は、毎日教室で顔を合わせるクラスメートから学級の代表を選出します。勉強のできる子、運動の得意な子、リーダーシップのある子、まじめな子、思いやりのある子、かっこいい子、なんとなく以上に知っている人の中から自分たちの代表を選ぶことができます。

大人になってからの選挙は、多くの場合、話したことも会ったこともない人に投票することになるのではないでしょうか。そりゃ尻込みしてしまいますよね。
近くて遠い選挙
政党所属ならその政党への評価がひとつの基準になるでしょうが、地方選挙では無所属の候補者が少なくありません。無所属となると選びようがない。若い人とか女性とか、選挙ポスターの良し悪しとか、候補者から受ける印象で選ぶしかないかなあとも思ってしまいます。

有力な国会議員ならメディアで触れることも多くて、議会でどんな活動をしているかそれなりに評価することができます。そうした有力議員が「政党の顔」になって、自分の選挙区の候補者を選ぶ基準になるのが一般的なのかな、と思います。
一方、地方選挙では、候補者がどのような政策を持ち、日常的にどのような活動をしているのか触れる機会が極めて少ないです。今は、その気になればインターネットである程度の候補者情報を得ることができますが、そんなに積極的に投票先を調べないのが一般的ですよね。
そもそも、4年前に自分が誰に投票したか覚えていますか?
主権者であるために
日本国の主権は日本国民にあるとされています。集合体としての「国民」は「主権者」ですけど、一人ひとりの国民にとって、この主権を行使する機会は投票しかありません。
その主権の行使によって、実際に権力を行使する代表者が選ばれます。
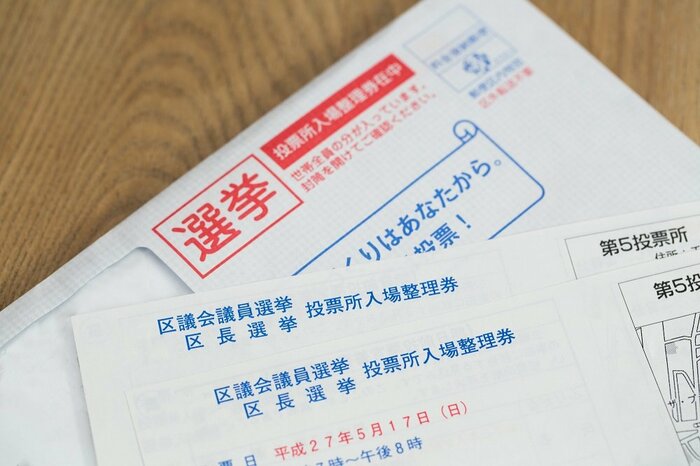
当選してから一回も議会に顔を出さない代表者、選挙違反をして当選した代表者、政治資金の収支にルーズな代表者。
誰かたちの中から誰かを選ぶのはとても難しいことだと思います。
テキトーに投票したらヘンな人が代表者になっちゃった。そんなこともあると思います。一回一回の選挙がすべて理想的な選挙になるなんてことはないでしょう。
棄権しないために、自分が納得できる投票先を選ぶのは難しいです。
それでも4月の選挙に行ってみようと、ちょっとでも考えていただけたらこの一文をものした甲斐があります。
【執筆:フジテレビ解説委員 岡野俊輔】