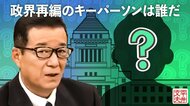立憲代表選の討論にイラッ
日本記者クラブで22日に行われた立憲民主党代表選の候補者討論会を聞いていてイラっとしたのでなぜなのか考えてみた。

代表選の最大の争点は衆院選惨敗の原因となった共産党との「おつきあいの仕方」をどう総括するかだと思うのだが、まず「共産党との共闘は間違っていたか」という司会者の質問に「はい」と答えた人は一人もいなかった。つまり誰が代表になっても立憲と共産との選挙協力は続く。
次に共産と結んだ「限定的な閣外協力」などの合意については、逢坂誠二氏が「国民感覚から相当ずれていた」と発言したほか、小川淳也、泉健太、西村智奈美の3氏も見直しが必要との考えを示した。僕はこれを聞いて、誰が代表になってもどうやら共産との閣外協力については取り下げるのだなと思った。
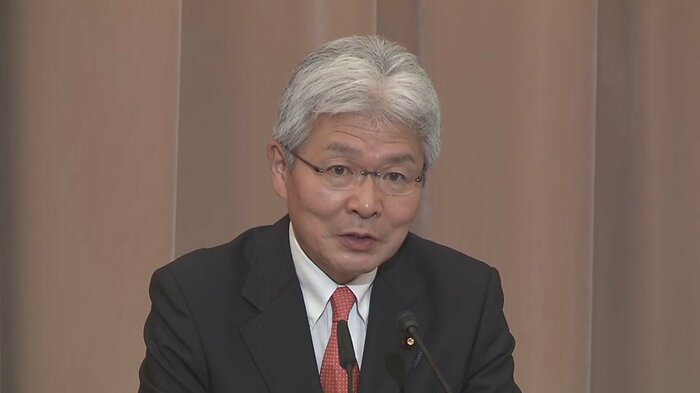
共産との閣外協力は枝野前代表が衆院選の前に初めて明言したのだが、世間では「共産の圧力に屈服した」との批判が出ていた。自民は「あちらさんは立憲共産党」(BY麻生太郎)などと揶揄し、結局立憲はこの「共産との閣外協力」という一言で惨敗してしまったのだ。

枝野幸男はまともな政治家だ
僕は枝野さんが「閣外協力」という言葉を出した時、「この人はまともな政治家だな」と、彼のことを少し見直した。選挙協力する以上そう言うのが筋だからだ。たとえ批判されようと筋を通すことは大事だ。だが同時に「大丈夫かな」とも思ったら案の定、選挙で負け、枝野さんは代表を辞めてしまった。

立憲の次期代表は来年の参院選でこの「共産との閣外協力」という言葉を取り下げるのだろうか。「衆院選は政権選択だから政権の形を示したが、参院選は政権選択ではないので形を示す必要はない」という理屈は「あり」かもしれない。
ただ普通の人が普通に考えたら、選挙を一緒に戦った政党は勝ったら政権に入るだろう。一緒に戦うが政権に入れてあげません、というのはあまりにも虫のいい話ではないか。そういう肝心な部分を説明しなかったり、ごまかしたりしていては有権者の信頼は得られないと思うのだ。
代表選では相手に殴りかかれ
一連の論戦でもう1つ気になったのは、経済も安保も4人の主張に大きな差がないことだ。自民党総裁選では河野太郎氏が最低保障年金を打ち出して他の候補にボコボコにされ、結局「太郎はまだ早い」ということで岸田文雄さんが勝った。面白かったのは河野さんは格下げのポストを与えられ、冷や飯食いになったくせに涼しい顔して選挙応援に飛び回っていた。これが自民の強さである。
立憲にこういう強さはないのか。たとえば国民民主出身で最も保守的と見られる泉さんは「共産との選挙協力はやめよう」となぜ言わない。
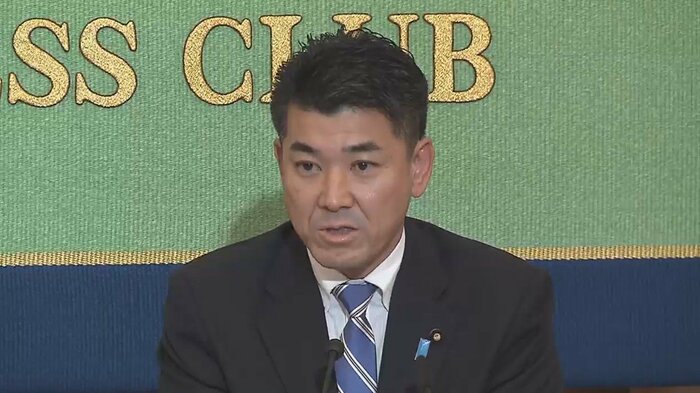
あるいは泉さんよりは共産との連携に熱心な小川さんは「共産との閣外協力の何が悪い」となぜ言わない。そして共産と組んでも大丈夫だということをなぜ説明しない。
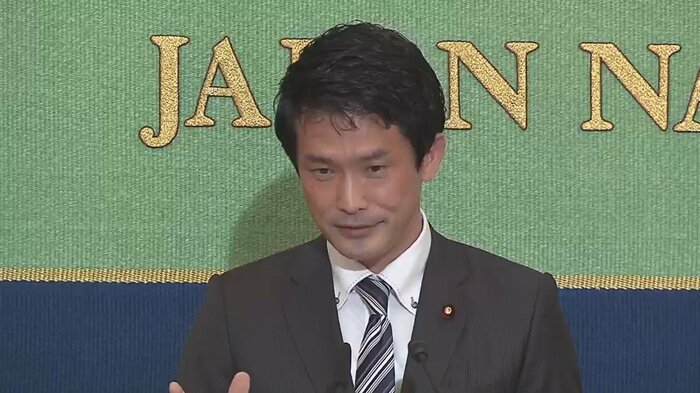
09年に発足した民主党政権は辺野古で社民党が離れ、消費税で旧自由党が離れ、最後に小池劇場で真っ二つに分裂した。彼らはそのトラウマで政策の違いによる対立や分裂を怖がっているように見える。

だが旧民主が本当に再生するためには、たとえ対立しても分裂せずに一緒にやっていく方法を考えることだ。でないといつまでも自民の対抗勢力にはなりえない。ボヤボヤしていると維新が国民民主も抱き込んで立憲を上回る勢力になる可能性がある。このようなユルい代表選をやっていてはだめだ。もっとガチで緊張感をもって、相手に殴りかかるような代表選をやってほしいと思うのだ。選挙戦後半に期待する。
【執筆:フジテレビ 解説委員 平井文夫】