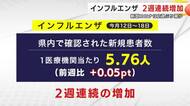感染状況の警戒レベル 初めて「黄」に
7日開かれた、東京都の新型コロナウイルスモニタリング会議では、新規感染者数の7日間平均が、前回の296人から159人に減少したとの分析が示された。年代別に見ると、10代以下の割合が14.7%と8月以降高い水準が続いている。 感染経路は、これまで同様、家庭内感染が最も多い67.1%。会食での感染は依然20代や30代で高いという。

都内では、感染状況と医療提供体制の警戒レベルについて、深刻な方から順番に「赤」→「橙」→「黄」→「緑」の4段階に分けられている。
先週、感染状況の警戒レベルは「赤」から「橙」に引き下げられたばかりだが、7日の会議で、さらに「黄」=「感染状況は改善傾向にあるが注意が必要」に 引き下げられた。上から3番目の「黄」になるのは、この警戒レベルが導入されて以来、初めてだ。
“発射台”が高いと次がきつい
「要は“発射台”が高いという、そうすると次はきついって話はここでは何回かしましたが、そうならないようにですね、何とかしっかりと下げていく必要があると考えております」 国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長は、次の感染拡大が始まる前に、できる限り新規感染者数を減らすべき、と強調した。

医療提供体制も一段引き下げ
「通常の医療が一部制限されている状況である」 入院患者数は前回の1181人から751人に大きく減少。 医療提供体制についても、最も厳しい「赤」から、2番目の「橙」に一段引き下げ。 「橙」になるのは10ヶ月ぶりだ。
病床確保で新基準
「ここからは通常医療とコロナ感染症医療の両立をすることが重要」 会議では、病床確保について、縮小する場合と、拡大する場合の基準が新たに示された。いずれも3段階に分けて新規感染者数と増加比を目安として縮小・拡大を行う 。

さらに東京都医師会の猪口正孝副会長は、第6波にむけ病床確保とともに、宿泊療養患者のフォロー、治療薬と患者をいかに結びつけていくかが大事、としたうえで経口薬にも期待感を示した。
飲食店で・・・予防対策の“落とし穴”
「ちょっとリスクが高そうだなと思われる現場って言い方が適切かどうかわからないですけど、あるにはあります」
飲食店の感染予防対策の“落とし穴”を大曲氏に問うと、こう続けた。

「使われたテーブルであるとか、人々が多く触れるであろうところを非常にふき取り消毒、掃除と消毒ですよね。すごく頑張ってやってらっしゃるのはすごく理解はするんですけど、そこがすごく対策の中心になってしまったりして、意識が集中しすぎてしまっているように見えるところもあります」
つまり、拭き掃除や消毒は熱心に行っているが、本来行うべき換気、客同士の距離をとる、マスク着用などが徹底されておらず、「ちょっと薄れてしまっているような場をたくさん見る」と指摘した。

抗体の“残り”は?
「ここで油断しない、油断することなく継続した取り組みが重要であります」
小池知事は感染予防対策の継続を呼びかけるとともに、ワクチン接種による抗体がどれだけ残っているのかを調査し、3回目のブースター接種に向けて検討を進める考えを示した。
感染予防対策と経済を両立させつつ、少し“余裕”が出てきた今こそ、第6波への備えを着実に進めなくてはならない。
(フジテレビ社会部・都庁担当 小川美那)