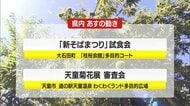クマは里で食べたものをもう一度食べようと、同じ場所やその周辺にねらいを定め、被害が出る事例が多く確認されている。専門家は、“里の味”を覚えたクマへの注意と、人の生活圏にクマを寄せつけないための対応の徹底を呼びかけている。
県内でのクマの目撃件数は、10月26日時点で1900件を超えるなど、過去に例をみないペースで増え続けている。
この要因について、クマの研究を50年以上続ける広島の日本ツキノワグマ研究所・米田一彦所長は、「ブナの大凶作と生息数の管理不足が重なった結果」と指摘する。
(日本ツキノワグマ研究所・米田一彦所長)
「クマの生息地のえさの量に対するクマの数を把握する必要があったが、なかなか調査は難しく、数の調整をしきれなかった。だから今は駆除を進めないと手に負えない状況」
県内でも人への被害が相次いでいる。
10月13日、飯豊町で83歳の女性がクマに襲われ、背中や右腕をひっかかれけがをした。
(襲われた女性)
「一瞬だったから怖かった。やられるかと思った」
クマが出てきたのは、ウシのえさが保管されていた小屋。
えさの袋が破られ、食べられた形跡があった。
町はそれまでも、ウシのえさの食害が多発していて、注意を呼びかけていた。
米田所長は、クマは“人が住む地域で食べた”いわゆる“里の味”を覚えていると強調する。
(日本ツキノワグマ研究所・米田一彦所長)
「クマは食べたところの近くで休む。牛舎のそばで休んで、また次の日も襲うというのを繰り返す。えさをとるのが簡単な所に通う。“味を覚える”という習性がある」
10月21日には、小国町の鳥小屋で“やまがた地鶏”のひな鳥34羽もクマに食べられた。
ここでは過去にも被害に遭っていて、今回が3回目だった。
農村地帯にとどまらず、クマの食害は市街地でも多く確認されている。
岩手・秋田ではコメの食害が相次ぐなど、「アーバンベア」の行動は徐々に大胆になっていると米田所長は指摘する。
(日本ツキノワグマ研究所・米田一彦所長)
「建物の中に入ってロッカーを荒らして玄米を食べるというのは、さらに一段進んだ“集落依存型”がものすごく強くなっている。それなしでは生きていけない」
また米田所長によると、クマの習性について、子グマは母グマを見失った場所の近くに生息し続ける傾向があり、母グマが捕獲されたり駆除されたりした後、人の生活圏で常に暮らしているクマもいるという。
(日本ツキノワグマ研究所・米田一彦所長)
「自分で開拓した地域を歩き回っている。“あそこに何がある”とよく知っている。玄米の次は白米を食べようとする。白米はだいたい民家の中にある。さらにステージが上がって、民家の中に入るのが普通な状態になってきている」
そして今の時期、特に注意が必要なのが“柿”。
中でも、住宅や小屋の軒先で風に揺られる“干し柿”が、クマを市街地に寄せつける要因のひとつになるという。
(日本ツキノワグマ研究所・米田一彦所長)
「東北の柿が晩秋から初冬にかけてねらわれやすい。通常は昼に行動するが、特に強い意志がある場合は、夜にねらって入る。静まったころに入ると、防御するのは非常に困難」
米田所長は、柿の木から早めに柿をとることや、コメやウシのえさ・漬物などが保管されている場所にしっかりと鍵をかけるなどを徹底し、少しでもクマを寄せつけないようにすることが必要としている。
よくニュースで見るクマは、“走り回っている姿”が多いと思う。
本来、山の中でクマは歩いているのだそう。
市街地で走っているのは“興奮状態だから”ということで、市街地のクマは山の中のクマよりも危険。
また本来、クマは昼間に行動する動物。
夜・明け方に目撃されることが多いが、昼間も油断してはいけない。
市街地のクマは本当に危険・昼間も油断してはいけないので、もし遭遇してしまった場合は電柱に隠れたり、以前伝えた頭や首を守る防御姿勢をとるなど、身を守る行動をとってほしい。