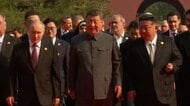高市早苗新政権が発足した。「強硬保守」と評されるこの政権がどのような対中・対韓政策を打ち出すのか注目され、中国や韓国では警戒感も広がっている。
この文章は高市新政権に対する、日本で暮らす中国人学者による提言である。以下は、東京大学のある中国人訪問学者が執筆し、東京大学大学院の阿古智子教授が翻訳したものを編集した記事である。
暴力的体制と情報戦にどう向き合うか
2025年10月1日、中国メディアは、9月3日に開催された「戦勝記念日軍事パレード」において、「武装警察の隊列の銃剣はすべて抜かれた」と誇らしげに報じた。放送や記事では「血潮が沸き立つ」といった表現を用いて、軍規と闘志を誇張していた。この見出しは、恐怖と暴力によって秩序を維持しようとする共産党体制下の中国の社会的気質を象徴している。

このような熱狂的なプロパガンダの背後には、中国にとって都合の悪い現実が隠されている。中国のインターネットでは多くの情報が検閲されており、政治的抑圧と闘う人々の活動を記録・発信するウェブメディア『中国数字時代(中国デジタルタイムズ)』は、「今月の声」と題した動画集に、毎月削除された映像をまとめている。そこには、土砂崩れ、鉱山や学校の事故、陳情者の拘束、病院の外で泣き叫ぶ家族、台風で吹き飛ばされた仮設住宅などが含まれている。
中国は、暴力的な統治体制を維持しつつ、海外ではプロパガンダ機関を通じて情報戦を展開している。こうした状況に直面する日本の新政権には、正確で効果的、かつ政治的に賢明な対中政策が求められる。
私は、新政権に向けて、以下の三つの政策提言を行いたい。
一、全体主義には毅然と、人には礼節と慈悲を
第一に、全体主義体制に対しては的確かつ毅然とした態度で臨むべきである。同時に、個々の人間に対しては礼儀正しく、慈悲深い姿勢を保つべきである。
中国共産党支配下の中国は、国連安全保障理事会の常任理事国でありながら、一党独裁、全体主義、権威主義体制を維持しており、報道の自由も法の支配も存在しない。
中国共産党は、独裁的なロシアや北朝鮮との友好関係を隠そうとせず、タリバン、イラン、シリアの独裁者とも連携している。2021年にはアメリカのアフガニスタン撤退後、主要国の中でタリバンを主賓として招待した最初の政府となり、2023年にはシリアの独裁者アサド氏を杭州の歴史的な寺院に招待し、伝統を破ってレッドカーペットを敷いて出迎えた。また、イランとは25年間の包括的協定を締結している。

一方で、中国共産党体制の最大の被害者は中国国民である。一般市民は人権侵害に苦しみ、まともな社会保障も受けられず、起業家は迫害され、知識人やメディア関係者は沈黙を強いられている。資金力のある人々は国外への脱出を選び、日本は人気の移住先の一つとなっている。
日本政府は、中国共産党体制に対して厳しい姿勢を取るべきであるが、それは体制に対してであり、一般の中国人や在日中国人に対してではない。共産党の代弁者とその被害者を区別することが重要である。
「なぜ憎しみに満ちた中国人がこれほど多いのか」を理解する
中国共産党による長年の歴史の歪曲と、憎悪を植え付ける教育の影響により、「憎しみに満ちた」中国人が生まれている。この点については、以前の記事でも指摘した。確かに、こうした人物は忌まわしい存在である。しかし同時に、彼らは情報統制の犠牲者でもあると言える。
中国を離れた中国人は、特に現代史について学び直す必要に迫られることが多い。例えば、中国本土で育った多くの人々は、1989年6月4日の天安門事件を知らず、日本政府が過去数十年にわたり中国に最大規模の援助を行ってきた事実も知らない。
毎年、多くの中国人が日本を訪れている。2025年の国慶節(建国記念日)の大型連休においても、日本は中国人観光客にとって最も人気のある旅行先であった。観光客は文明的であるべきであり、これは極めて基本的な要件である。
日本の長期滞在ビザや永住権を申請する中国人や外国人に対しては、民主主義や立憲主義に関する市民教育プログラムの導入を検討すべきである。具体的には、地域コミュニティや市民教育団体による学習プログラムの実施、国会や裁判所の見学、地域活動への参加などが考えられる。
中国政府の二面性を理解する
中国共産党は、日本や米国に対して憎悪を煽る教育を推進している。一方で、自身の財産や子息を、米国、欧州、日本などの先進国にできる限り送り出している。これは明らかに矛盾した行動であり、体制の本質をよく表している。
2021年7月26日、当時の中国外務次官・謝鋒氏は、天津でシャーマン米国務副長官と会談した後、記者会見を開いた。謝氏は米国に対し、「誤りを正すべき項目」として複数の要求を提示し,その最上位に「中国共産党員とその家族に対するビザ制限の無条件解除」を挙げた。中国国営メディアはこの要求を広く報道した。

その背景は単純である。中国共産党員の子弟は米国で教育を受け、家族は米国に財産を所有している。もし彼らが米国に渡航できなくなれば、共産党への入党をためらう人が増えることを懸念しているのである。
このように、中国共産党は「言行不一致」の典型である。したがって、日本政府は中国共産党が何を言っているかではなく、実際に何をしているかに注目すべきである。この原則を政策立案において適用することで、無駄な回り道を避けることができる。
二、排他的でない「日本の発展戦略」を確立する
第二に、日本は閉鎖的な姿勢ではなく、開かれた社会としての発展戦略を確立すべきである。
20世紀のアメリカの経験は、開かれた移民制度と科学研究システムが技術革新と産業発展の基盤であることを示している。2025年には日本と米国の学者がノーベル賞を受賞したが、科学の成果は国籍ではなく制度とエコシステムによって生まれることを改めて認識させた。
米中の政治的緊張により、中国系アメリカ人研究者の多くが米国を離れようとしている。これは日本にとって人材獲得の好機である。AI分野では、中国と米国が2大強国である。しかし、中国の有力チームが規制と政治リスクから逃れ、シンガポールへ移転する事例が出ている。業界で注目を集めた新星、中国のAIチームManusは2025年8月、中国での事業を閉鎖し、人員と技術をシンガポールに移転した。日本は、プライバシー保護や知的財産制度を整備し、起業家ビザや研究支援を提供することで、次世代技術者にとって魅力的な国となる可能性がある。
近年、米国が孤立主義へと傾き、人種間の緊張が激化する中、カナダや欧州は人材誘致のための政策を打ち出している。皮肉なことに、中国共産党でさえ国際的な人材獲得に躍起になっている。北京は2025年10月、科学技術や経済の分野で顕著な貢献を果たしたハイエンドの外国人人材に、より迅速な居住許可を与える「Kビザ」を導入し、世界中の人材を中国に呼び込もうとしている。
全体主義体制でさえ開放性の重要性を理解している中、日本が恐怖や外国人嫌悪から門戸を閉ざすことは、戦略的損失である。真の安全保障は、孤立ではなく、制御可能な開放性から生まれる。
三 、「文明的な中国人」を日本の同盟者として活用する
第三に、日本は法の支配、自由、多様性を尊重する「文明的な中国人」を、リスクではなく同盟者として捉えるべきである。
彼らは全体主義の最初の犠牲者であり、その実態を深く理解している。ロックダウン下の上海市を記録した動画「4月の声」や四川省江油市で少女への暴行事件をきっかけに起きた大規模抗議活動「江油事件」などでわかるように、彼らは嘘や暴力を見抜く力を持ち、公共空間で秩序を守る意志も強い。

また、彼らは中国共産党のレトリックを見抜く力があり、日本の政策立案やリスク評価に貢献できる。
いま、多くの中国のメディア関係者、芸術家、学者が、日本で表現と創造の場を見出している。香港国家安全維持法の施行以来、多くの人が日本で形成される中国語圏は「新しい香港」だと述べている。日本で活発に中国にかかわる学術講演会や文化イベントが行われ、中国語書店が次々に開店しているのは、日本の開放性と文化の成熟度の高さを雄弁に物語っている。日本が法的支援や文化交流のために小規模でも効果的な制度を整えることができれば、彼らは日本と中国、そして世界をつなぐ社会的なシンクタンクや文化の使者となるだろう。
米国が一部の中国人研究者や留学生に敵対的になると、日本の「温かさと確信」はさらに貴重なものになるだろう。

文明的な中国人は、日本の友人であり資源である。彼らを活用するには、中国事情に通じた日本の「知中派」の協力が不可欠で、垂秀夫前駐中国大使のような外交官は、日本の国宝とも言える存在である。
しかし、現在の日本の大学院で中国研究を専攻する学生の多くは中国人であり、日本人の研究者が減少している。将来の「垂秀夫」を育てるためにも、文明的な中国人とのネットワークを活用し、現代中国を専門的に研究する機関の設立が必要である。
松下政経塾の精神を今こそ活かすべき時
高市早苗首相は松下政経塾の卒業生だ。同塾の理念は、公共リーダーシップとグローバルな視点の融合である。中国と対峙するのに必要なのは、制度と技術の両面を重視した長期的な戦略である。「排他的でない日本の発展」には、世界の人材を活用し、産業構造を再構築する国家ビジョンが求められる。
文明的な中国人との連携は、民主主義と秩序を守り、次世代の科学技術と産業の未来を確保するために欠かせない戦略である。