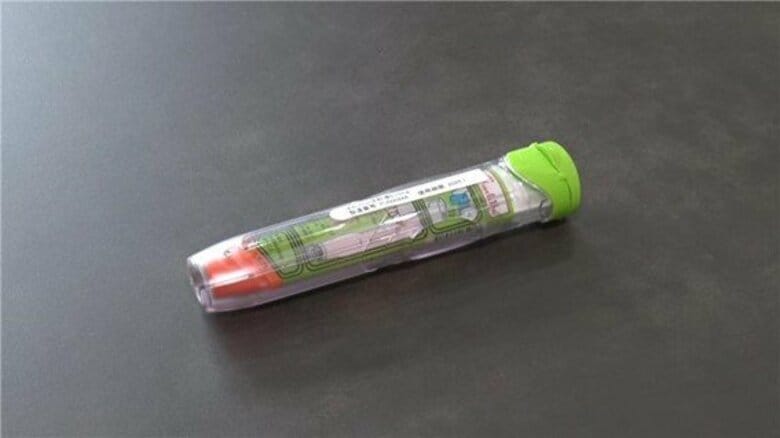「仕事を辞めたら?」——子どものアレルギー治療に付き添う母親が職場で浴びた言葉だ。アレルギー疾患を抱える“本人”と“支える親”が、治療と仕事の両立に苦しんでいる。症状の悪化を恐れて通院を優先すれば、職場の理解が得られず離職に追い込まれる。そんな現状に、医療と職場が連携する支援の仕組みが動き始めている。
アレルギー治療支える親の困難
息子が重度のクルミアレルギーを持つ女性は、週2回の在宅勤務と年10回まで使える「看護休暇」を使い、息子のアレルギー治療を支えている。
原因物質を実際に食べて症状が出るかを調べる「負荷試験」の治療は、基本的に1泊2日の入院が必要なため、子も親も学校や仕事を休まなければならない。1カ月後に再度診察が必要なため、1度の負荷試験に対して3日休みを取らざるを得ないという。
「そんなに頻繁に休むなら、仕事を辞めたら?」
過去の職場では、そんな心無い言葉をかけられたこともある。

「通院の付き添いはほとんどが母親。夫に頼みたいが、会社の理解を得にくい」。女性は苦しい心境を吐露する。
負担の大きい仕事との両立
日本で約2人に1人が何らか罹患しているとされるアレルギー。いま「大人」が仕事との両立をめぐり、2つの困難に直面している。
一つ目が「アレルギー症状で仕事を休みがちで、仕事を続ける自信がない」という、本人の疾患に伴うもの。二つ目が「共働きで子の通院の付き添いが難しい」という、子どもの治療の支援に伴うものだ。
従来は、幼少期に発症することが多かったアレルギーだが、大人になって新たに発症するケースも増えている。また、子どもの疾患であっても、重度なら親など「付き添い者」への負担が極めて大きい。
藤田医科大学総合アレルギーセンター長の矢上晶子氏らが2024年に院内で行った実態調査によると、アレルギー疾患が、本人や付き添いの学業や仕事に影響を及ぼした割合は約6割にのぼる。また、本人や付き添い者の約4割が、学校や職場でアレルギー疾患について相談できず、通院制限によって症状の悪化を招くケースもあるという。