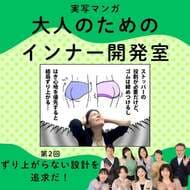帝人ソレイユ株式会社は障がい者雇用を目的に2020年から「Planet Hug Orchid(プラハグ)」のブランド名で胡蝶蘭の生産・販売を開始し、その高い品質が評価されて大手金融機関など250社を超える企業から注文を得ています。当社は、事業の面では「ノウフク・アワード2021」(農林水産省など)、障がい者雇用の面では「もにす認定」(厚生労働省)という外部評価を得ただけでなく、贈答品としての「問題点の多い胡蝶蘭を再定義」も事業コンセプトに掲げて、新たに枯れた胡蝶蘭の回収・引取サービスを通じたリサイクル・リユースにも取り組んでいます。障がい者雇用を目的とした事業の黒字化は難しいのが一般的ですが、当社の胡蝶蘭事業は創業当時から「黒字化を目指す!」を掲げ続けています。そんな胡蝶蘭事業の裏舞台での出来事をご紹介します。
引き取りサービスのある胡蝶蘭「プラハグ」: https://plahug.com/
帝人ソレイユ株式会社: https://teijin-soleil.co.jp/

1.創業秘話(会社が設立に至った背景)
帝人ソレイユは、家族に障がい者を持つ社員有志3人、鈴木崇之、黒木忠、升岡圭治の想いから生まれた特例子会社(障がい者雇用専門子会社)です。我が子のようなハンディキャップのある人々が働く場所をつくりたい―――。そんな原点を胸に3人で調査や企画立案に奔走し、会社を説得して帝人グループCEOの承認を得て、2019年春、千葉県我孫子市に農園「ポレポレファーム」(帝人ソレイユ我孫子農場)が開業しました。
プラハグの胡蝶蘭のメイキング映像
農場開設から遡ること3年半前の2015年秋、一つ目の「運命の分かれ道」が訪れました。43歳だった私(鈴木)は新規事業の激務から心身ともに疲弊し切り、上司に「プロジェクトリーダーを降板させて欲しい」と願い出たのでした。二人目(長女)がお腹の中にいる家内と一緒に行った心療内科に診察室の様子は、今でも脳裏に焼き付いています。
抗うつ剤と睡眠導入剤を服用しながら療養する中で、当時住んでいたマンションの家庭菜園に目が留まり、シニアの住民男性2人が参加していた畑俱楽部に頻繁に顔を出すようになりました。毎朝出社前に1時間ばかり、当時1歳だった長男坊を連れて畑作業に精を出しているうちに(写真)、頬をなでる風やミミズのいる土の匂いに癒され、次第に体調も回復していきました。会社を辞めて新規就農しようと思ったのは、ごく自然な流れでした。

自費で社会人向け週末農業学校「アグリイノベーション大学校」に通い、オーガニック野菜の生産技術を学びました。とはいえ、農業は素人が簡単に成功できるような甘い世界ではありません。家内は大賛成とは言わずとも反対はしませんでしたが、行政の新規就農担当部署に行っては「子供が小さいのに食べていけなくなる」と脅され、知り合いの農家に相談に行っては「43歳までに身に着けたことを農業に振り向けるのは、社会にとって無駄だ」と切り捨てられました。
さてどうしたものかとモンモンとしていた2016年の暮れ、私は職場の同僚だった黒木と二人で新橋のガード下の居酒屋にいました(写真)。これが「運命の分かれ道」の二つ目でした。黒木は、新規就農に突破口を見出せない自分に「農福連携」というものを教えてくれたのです。農林水産省や厚生労働省のホームページには「農福連携とは、障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組です。」とありますが、当時の自分には「ノウフク」なんて全く聞いたことのない言葉でした。

黒木は、「農業と障がい者とは相性がいいんだ」と言います。聞けば、彼の次男は重度知的障害の自閉症で、「日本では、重度の知的障害者が社会人になって働く場所はほぼゼロに近い。自分が面倒を見られなくなった後のことを考えると胸が押しつぶされそうになる」とのこと。私は「これだ!」と稲妻に打たれたようになりました。今まで農業を目的としてどのような農業をやればいいのかを思案していましたが、逆に障がい者雇用を目的に手段として農業をやれば、会社を辞めずに会社の給与を維持しながら農業ができることに気づいたからでした。

胡蝶蘭の栽培で活躍する黒木さんの次男(重度知的障害・自閉症)
それからは猪突猛進&電光石火、2017年の年明けすぐ升岡に声をかけ(新橋の居酒屋で黒木から、升岡の子供さんも障がい者だと聞いたからです)、鈴木・黒木・升岡の3人で農業を軸とした特例子会社の設立を会社に提案し、自ら経営・運営にあたることを目指すことになったのです(写真)。3人は自腹で全国の福祉事業所や特例子会社の優良事例の見学に行きつつ、私が企画書をまとめていきました。

2017年2月、当時の人事担当役員(CHRO)に私が「いいアイデアがあるから話を聞いてほしい」という趣旨のメールを送りました。そのCHROは障がい者雇用に困っていたのかもしれません。非常に理解を示してくれ、非公式ながらもプロジェクトオーナーになってくれることになりました。帝人グループとしての目的は、障がい者雇用に関する社会的責任を果たすこと(法定雇用率の達成)です。帝人ソレイユ設立前の数年間は法定雇用率未達が続いていたのでした。
その後は、さまざまな「社内の壁」に阻まれつつも何とか切り抜け、稟議書に帝人グループCEOのハンコが押されたのが2018年9月。これが「運命の分かれ道」の三つ目になりました。業務外で企画を練って社内を説得したわけですので、大企業としては早いほうだったのかもしれません。立ち上がり方が「とても社内ベンチャー的だ」と言われることもあります。
ときどき、社内の壁を突破できずに諦めそうになったころを思い出します。霞ヶ関本社(写真)から退社して最寄り駅から自宅マンションに向かって歩きながら、夜空を仰いで「このプロジェクトが世の中で必要とされるのであれば、必ず神様が応援してくれるはずだ」と毎晩のように手を合わせて祈っていたものです。

社内的には、帝人ソレイユ設立のハードルは3つありました。①子会社をつくること、②農業という本業とは全く関係のない新規事業をやること、③千葉県我孫子市という帝人グループ100年(当時)の歴史の中でまったく縁のない地域に事業所(農場)を開設すること。1つでも大変なのですが、新会社、新規事業、新事業所と3つ重なっていたために難易度は上がりました。それでも、経理部長の協力で経理担当者に収支計算のチェックをお願いできたり、CSR担当役員が元厚生労働省の高官だったために経営会議の場で「農福連携は国も力を入れて推進しているとてもいい取り組みになので、ぜったいにやるべきだ」と後押ししてくれるなど、幸運にも恵まれました。また、当時の上司は、本来の業務をギリギリこなしながら企画書を書いていた私の姿を知りながらも、片目をつぶって黙ってくれていました。この上司がストップをかけていれば、帝人ソレイユは生まれていなかったでしょう。感謝しかありません。
経営会議を通すための稟議書(写真)を書き上げるにあたって、「農業の黒字化」にこだわりました。実は多くの特例子会社の収支は実質的には赤字であることが多いので、これはけっこうなチャレンジでした。もとより、右肩上がりのグラフ抜きにCEOのハンコはもらえないのですが、鈴木・黒木・升岡としては働き手である障がいのある社員の「誇り」を大事にしたかったのです。赤字の会社・事業には「誇り」持てないのではないか、という素朴な思いです。この目標に苦しみ続けることになるのですが、今でも社内外に向けて「黒字化を目指す」と公言したことを後悔していません。
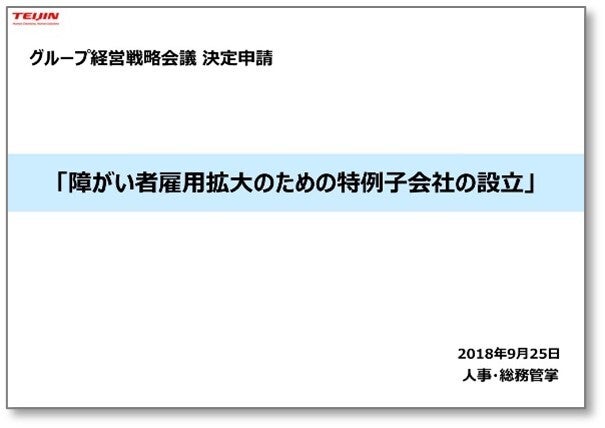
ところで、よく2つの質問をいただきます。それは、「なぜ農場の場所が(千葉県)我孫子になったのか?」と「なぜ胡蝶蘭を選んだのか?」です。
まず、「なぜ農場の場所が(千葉県)我孫子になったのか?」について。公式の理由は、千葉県東葛エリアは人口が多く障がい者の母集団が大きいから採用に有利、我孫子市は全国でも有数の福祉に手厚い自治体にため支援を得られやすい、帝人の本社のある霞ヶ関からアクセスが良く社員の協力を得られやすい、といったものです。実は裏の理由もあるのですが、それは「私の家内の実家が我孫子にあるから」です。私が横浜で家庭菜園をやっていたころに我孫子の農家とつながりたくて、いまの農場のある土地を耕していた農家からオーガニックの野菜ボックスを定期購入していたのです。家内の実家に帰省するついでにその農家といろいろと話をするうちに 「一緒にやろう!」ということになり、経営権を入れ替える形で帝人ソレイユ我孫子農場(ポレポレファーム)として再スタートすることになりました。

ポレポレファーム外観
次に、「なぜ胡蝶蘭を選んだのか?」。もともと新規就農したかった私がやりたかったのが、オーガニック野菜でした。でも一般的に野菜の収益性は厳しい。その野菜をカバーできるだけの高い収益性をもつ作物を探していました。一時はシイタケ菌床栽培にも目が向いて収支計算までやっていたのです。そんな折、週末農業学校のゼミの講師が「鈴木さんのやりたいことってこんな感じなんじゃないの?」とスマホを見せながら教えてくれたのが、ある福祉事業所が生産・販売していた胡蝶蘭だったのです。そこからヒントを得ました。ひょんなことから不思議な出会い(ご縁)があるものです。

障がいをもった職人によって胡蝶蘭は丁寧に栽培される
弊社の胡蝶蘭事業は、過去5年にわたって成長し続けてきました。この歩みは一過性ではなく、確かな実績と信頼の積み重ねです。私たちは、働く仲間の自信と誇りのために、また、社会性と収益性を両立させる新しいモデルとして、挑戦をさらに加速していきます。
【参考リンク:東京新聞web取材記事】
障害がある子たちの働く場をつくりたい 勤務先を説得し農園開設にこぎつけた父らの熱い思いとは:東京新聞デジタル
【プレスルーム】
https://plahug.com/pressroom.html
写真やロゴをダウンロードできます。
【お問い合わせ】
https://inquiry.teijin.co.jp/form/contact_sol_jp.html
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ