文章を読んで理解するという過程を脳の機能として見ると、まず言語中枢が働き、その情報が海馬に蓄えられた過去の経験や勉強によって得られた知識(長期記憶)と頭頂葉で照らし合わされ、前頭葉において自分なりの感想や解釈がなされます。つまり、脳をフル回転させる作業なのです。筋肉の緊張もともないます。
寝床ではリラックスして脳血流は減らないといけないのに、これではまったく逆の現象を起こさせていることになります。
「つぶやく」のも避けたい
これとよく似た現象が、不眠症、とくに「寝つけない」というタイプの不眠症で起きています。寝つけないで布団の中で悶々としているとき、人は心の中でぶつぶつと何かをつぶやいています。
「ああ、眠れないなあ」「このまま朝になっちゃったらどうしよう」「明日のプレゼン、うまくいくかなあ」「上司のあの一言、むかつくなあ」などです。

「つぶやく」という言語活動も当然言語中枢の働きで、同様にそこから記憶の中枢、頭頂葉、後頭葉、前頭葉などが働いて、脳全体が刺激される結果となります。
つまり、寝床で書類に目を通すという作業と、「寝つけない」タイプの不眠症は、同じ理由で脳を活性化しているのです。
それと同じ意味で、寝ながら音楽を聴くというのもおすすめできません。特に、歌詞のついた曲はよくありません。言語中枢を活性化させてしまいます。
歌詞がついていなくても、聴覚中枢を刺激するということには変わりなく、何らかのイメージを想起させたり、記憶の中から何かを引き出して感情に働きかけたりします。つまり、脳の機能を活性化させることには変わりないので止めておくべきです。
脳の活性化が不眠につながる、このことを肝に銘じ、そこに通じるようなことは極力避けることがいい睡眠を得るコツと言えます。
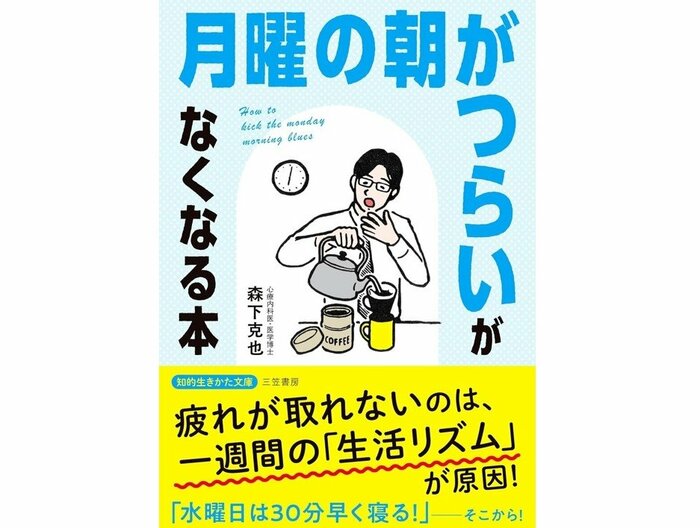
森下克也
心療内科医、医学博士。著書に『決定版「軽症うつ」を治す』(角川SSC新書)、『うつ消し漢方』(方丈社)、『もしかして、適応障害?』(CEメディアハウス)他、多数。






