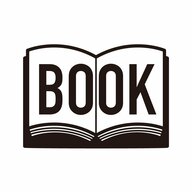こうした水道インフラは、チームではなく、個人に依存する構造に陥っています。設計・点検・修繕・住民対応・災害対応といった幅広い業務を、少人数でこなす日常。
給水人口5万人未満の事業体では、職員数が平均7人未満であり、その中で技能職や技術職が何人いるかを考えると、事業の脆弱さが浮き彫りになります。
老朽化施設の点検と人材不足
これまで見てきたように、高度経済成長期に整備された水道管の多くが、いま更新時期を迎えています。すでに法定耐用年数を超えた管は全体の2割を超え、年々増え続けていますが、更新や補修の体制は追いついていません。

厚生労働省が2016年に実施した調査では、全国約6000の水道事業体のうち、74%が「定期点検を実施していない」と回答しました。これは点検が制度上義務化される前のデータとはいえ、維持管理体制の脆弱さを示す数字です。
2018年の水道法改正により、点検や更新の計画策定が義務化されましたが、現場では「日常業務に追われて点検にまで手が回らない」「知識を持つベテランが退職してしまい、点検のやり方がわからない」といった声が上がっています。
とくに老朽化が進んだ施設では、設備の構造を深く理解し、異常の兆候を察知する感覚も求められます。それゆえ、経験豊富な職員からの技術継承が不可欠です。
一方で、点検業務の一部を民間業者に委託する動きも広がっていますが、民間でも人手不足は深刻で、無理な体制で作業を行う現場も少なくありません。
たとえば、2025年に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故では、下水道管の破損が原因とされました。点検では腐食は見つからなかったとされていますが、実際には地下に空洞が広がっており、調査の限界や人材不足による対応の遅れが背景にある可能性も指摘されています。
インフラの老朽化が進む中で、地道な点検や修繕作業の重要性は増しています。しかし、それに見合う人材の確保や育成が進まなければ、いずれ重大な事故が起きてもおかしくはありません。
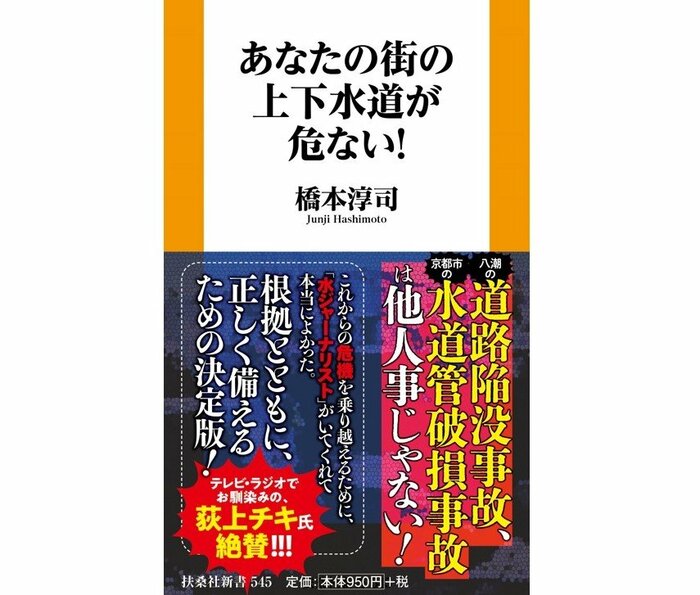
橋本淳司
1967年群馬県生まれ。アクアスフィア・水教育研究所代表、武蔵野大学工学部サステナビリティ学科客員教授。著書に『水辺のワンダー~世界を歩いて未来を考えた』(文研出版)、『水道民営化で水はどうなる』(岩波書店)、『67億人の水』(日本経済新聞出版社)、『日本の地下水が危ない』(幻冬舎新書)、『100年後の水を守る~水ジャーナリストの20年』(文研出版)、『2040 水の未来予測』(産業編集センター)など多数