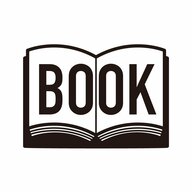事故が発生したのは早朝で、通勤・通学のピークにわずかに先行した時間帯でした。数時間遅れていれば、数多くの歩行者や車両が巻き込まれていた可能性があり、救出活動に時間がかかれば、復旧もここまで早くはなかったでしょう。
工法にも注目が集まった
この事故は、掘削時の選択された工法にも注目が集まりました。この時の現場では、硬い岩盤を対象とする「ナトム工法」が採用されていましたが、その岩盤の厚みが想定より薄く、地下水を含んだ砂層との境界が不安定だった可能性が指摘されました。
また、福岡市は国家戦略特区として「天神ビッグバン」「ウォーターフロント再整備」など都市の成長を掲げた再開発を進めていました。
博多駅周辺の開発と交通機能の強化が優先されるなかで、事故は発生しました。いまから思えば「空いた穴を埋めて終わり」ではなく、「見えない地下をどうするか」という教訓を残しておくべきだったかもしれません。
そしてこの問題は、福岡だけの特殊な出来事ではありません。都市の地下には、私たちの目に見えない無数のインフラが縦横に走り、年を経て劣化しつつあります。
ひとたび地下構造が破綻すれば、生活の基盤そのものが突然、崩れ落ちるのです。
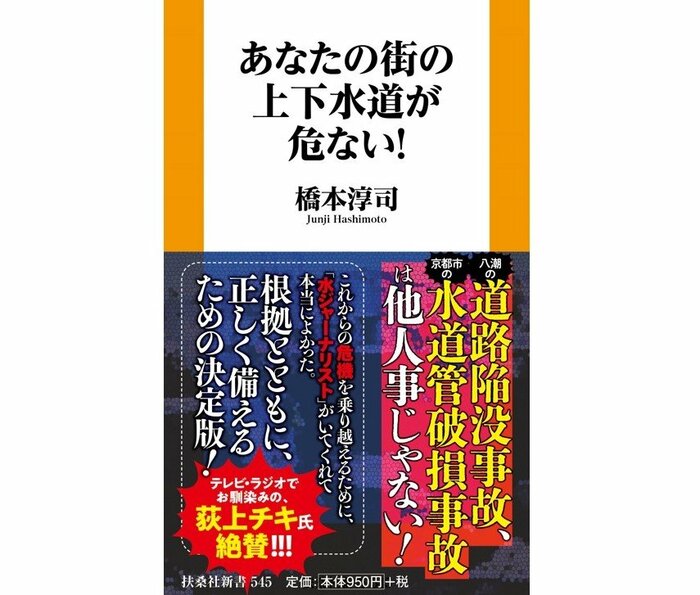
橋本淳司
1967年群馬県生まれ。アクアスフィア・水教育研究所代表、武蔵野大学工学部サステナビリティ学科客員教授。著書に『水辺のワンダー~世界を歩いて未来を考えた』(文研出版)、『水道民営化で水はどうなる』(岩波書店)、『67億人の水』(日本経済新聞出版社)、『日本の地下水が危ない』(幻冬舎新書)、『100年後の水を守る~水ジャーナリストの20年』(文研出版)、『2040 水の未来予測』(産業編集センター)など多数