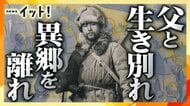網などにかかって取れても、食べることがなかったもったいない魚があるのを知っていますか?利用しない魚なので「未利用魚(みりようぎょ)」と言います。今回はこの未利用魚に注目します。
仙台放送キャラクター ジュニくん
「なんかいい匂いがするぞ!いただきます!プルプルしていておいしい!」
ショウガの効いた、ピリッと辛い、ソースで味付けされた、こちらのステーキ。
マルサン松並商店 松並理恵社長
「ジュ二くんおいしかった?これは今まで食べられてこなかった“アカエイ”から作られているんだよ」
開発したのは、宮城県塩釜市の水産加工会社。こちらは、エイの妖精…ではなく、社長さんです。
マルサン松並商店 松並理恵社長
「規格外だったり、見た目が悪かったり、取れる数量が少なかった、魚たちを『未利用魚』っていうんだよ」
未利用魚というのは、松並社長が言うように色々な理由でほとんど食べられることがない魚介類のこと。ステーキになっていたアカエイもそのひとつで、食べるとおいしいのに食べられていないのです。
マルサン松並商店 松並理恵社長
「これを今からさばきたいと思います。ぬめりがあるので、ものすごく加工しづらいんですね。包丁が入っていかないんですよね、ぬめりで」
アカエイは、もともと暖かい海にいますが、宮城県内でも年々取れる量が増えてきています。しかし、このように加工がしにくいことから、取れても、ほとんどは海に戻されているそうです。さらに…。
マルサン松並商店 松並理恵社長
「ここの部分が可食(食べられる)部分。アカエイは10分の1しかないです」
食べられる部分が少ないのも、理由です。
それでも、未利用魚を食べようとするのにはわけがあります。
マルサン松並商店 松並理恵社長
「限りある海洋資源を大切にしていきたい。普段取れるものも取れなくなってきて、温暖化、海水温の上昇によって、アカエイなど、取れなかったものが取れるようになったので」
日本では取れる魚の量が年々減り続けています。2022年は最も多かった1984年の3分の1以下。世界各国で漁業の競争が激しくなっていることや海の環境が変わって取れる魚自体が減っていること、漁業をする人も減っていることなど原因はいくつもあります。
宮城県でもサンマ、サケが取れないなど異変が続いています。
そうしたなかで、新たに食べられる魚介類として未利用魚が注目されているのです。
県水産技術総合センター 菅原幹太さん
「ジュ二くん、こんにちは。実験棟を案内するね」
石巻市にある宮城県水産技術総合センターでは、「未利用魚」をどうやって食べるかという研究も行っています。
県水産技術総合センター 菅原幹太さん
「公開実験棟には魚をさばいたりする機械や、焼いたり蒸したりする機械が46種類ほどあります」
研究員の菅原幹太さんは、「未利用魚」をおいしく食べるための研究をしています。この日、試作していたのは「ホシエイ」のヒレのみりん干し。
県水産技術総合センター 菅原幹太さん
「魚種によって仕上がりがいろいろ異なるので、不安な部分もあれば、できた時にすごい喜びはありますね」
何度か乾燥具合を確認し、一番おいしい状態を探るそうです。
県水産技術総合センター 菅原幹太さん
「できあがってますね。うん、おいしいです。ジュ二くんも食べてみる?」
仙台放送キャラクター ジュニくん
「うまみが強くなったね」
この機械では温度や圧力を変えて味のつき方や柔らかさ、色などを調べます。
別の部屋では…。
仙台放送キャラクター ジュニくん
「理科室みたい」
魚の「うま味」成分であるタンパクの量を調べています。
県水産技術総合センター 菅原幹太さん
「水分・タンパク・脂肪・灰分の分析を行って、このようにデータ化します」
魚は、種類や季節によっても成分が変わります。こうして分析することで、干物がいいのか、蒸した方がいいのかなどどういう食べ方が適しているのか分かってくるそうです。
県水産技術総合センター 菅原幹太さん
「もともとなじみがない魚が取れている。どういった加工利用をすべきかが難しい。成分分析や加工試作して、データを蓄積して、県内の水産加工企業のサポートができれば」
もったいない魚たち、未利用魚のおいしい食べ方が分かって、もっと食卓に上がるようになることで、漁業のいろいろな課題がよくなっていくことが期待されているのです。