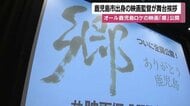粘土を使った造花「ラペリスフラワー」を知っているだろうか。美しい花をリアルに作るのではなく、その花特有の“らしさ”を形にするこのフラワーアートに魅せられ、約50年にわたって制作活動を続けている女性が秋田・八郎潟町にいる。毎日のように作品作りに没頭しているという女性にラペリスフラワーの魅力を聞いた。
作れば作るほどすてきな花に
秋田市にあるアトリオンの展示室に並んだ色とりどりの花。

この花は「ラペリスフラワー」と呼ばれる造花だ。石の粉と樹脂を混ぜた特殊な粘土で作られているこのフラワーアート。繊細な花びらの曲線に、美しい色合い。果物のみずみずしさも見事に表現され、息をのむほどの精巧さだ。

制作したのは八郎潟町の小野亮子さん(83)。アトリオンで5月、4年ぶりとなる個展を開いた。
ラペリスフラワー作家・小野亮子さん:
いまだかつてないほど一生懸命頑張った。来てくれるお客さんが口々に「すごいね、すごいね」と言ってくれたことがうれしい。
小野さんは30代の頃にラペリスフラワーに出合い、その魅力に夢中になった。

その後は技術を磨いて県内をはじめ岩手・盛岡市や仙台市に教室を開き、約50年間、講師として働きながら国の内外の展示会に出品するなど、多忙な日々を過ごした。
80歳になって教室は閉じたが、今も毎日のように作品作りに没頭している。6~7時間も作り続けるという小野さんは「とにかく作ることが何より好き。作れば作るほどすてきな花ができるようになった」と話す。
乾燥と着色を繰り返しつやを出す
小野さんは頭の中で植物をイメージして、それを作品にしている。この日は花びらや果物を作っていた。

花の個性や表情を表現するための大事な工程で、花びらの大きさや角度などを細かく調整。専用の型を使って葉っぱもリアルに表現する。

粘土が乾燥したら、粉末の塗料につやが出るうわぐすりなどを加えて塗っていく。乾燥させて色を塗る。この作業を繰り返すことでつやが出て、優雅な質感が生まれるという。
理想の色に仕上がるまで半年
陶器のような仕上がりになることから、焼かずにできる“陶器風の花”とも呼ばれるラペリスフラワー。
1日でできる作品もあるが、小野さんが今回の個展で展示したライラックやダリアは、完成までに半年かかった。

ライラックは理想の紫色に仕上げるために、淡いピンク色をベースに色を5回塗り重ねた。

ダリアは最初に中央の細かい花びらを、次に大きめの花びらを作るなど、3段階に分けて制作。地道な作業の繰り返しだったという。
モネの庭にあるような花々を作りたい
美しいものを作るために小野さんが意識しているのは、旅をしたり音楽を聴いたりして感性を磨くこと。特に海外旅行が大好きで、旅先で見た花や風景、出会いからインスピレーションを受け、作品へとつながっている。
小野さんが次に作りたい作品は、フランスで見た画家・モネのジヴェルニーの庭だ。

「モネの庭に咲いているような、数限りない色々な花を制作して楽しみたい」と語る小野さん。
これからも、小野さんの生み出すフラワーアートの世界から目が離せない。
(秋田テレビ)