日常が一変したあの日
2011年の東日本大震災の発生から2025年で14年。全国ではいまだに約2万8,000人が避難生活を余儀なくされている。福島第一原発事故の直後、5人の子どもを放射線の影響から守ろうと避難した女性がいる。
沖縄県沖縄市に住む長谷川牧子さん。当たり前だった日常は2011年3月11日に一変した。

長谷川牧子さん:
今まで経験したことのない揺れでした。震度3や4は茨城県でも割とあったので、それは日常茶飯事だったのですが、あれほどの揺れは初めてのことでした
当時、茨城県南東部の神栖(かみす)市で夫と5人の子ども、それに夫の両親と暮らしていた。

地震直後、頭をよぎったのは神栖市から200kmあまりの距離にあった福島県の原子力発電所。

2011年3月12日、不安は現実のものとなり、福島第一原発の原子炉建屋で水素爆発が起きた。
長谷川さんは夫や両親にすぐに避難すべきだと訴えるも考えが折り合わず、5人の子どもと車に乗り込んだ。
長谷川牧子さん:
私は放射性物質の影響を子どもに受けさせたくありませんでした。もうリスクを少なくするには避難、逃げるしかない。遠くに行くしかないと思いました。私は母親として子どもたちのこれからの健康と命が大事だったので実家のある佐賀に移動すると伝えて出発しました

日頃から、被ばくの恐ろしさや国の原発政策に対して危機感を抱いていた長谷川さんは原発事故が起きた際に備え、用意していた被ばくを抑えるための安定ヨウ素剤子どもたちにも服用させた。

長谷川牧子さん:
あくまでも放射性ヨウ素だけの影響のものなので、原発が爆発して果たしてどのぐらいの種類の核種が出ているかというのも素人にはわからないわけですよね
変わってしまった家族の形 自主避難者の苦悩
避難への考え方の違いから夫とは離婚。故郷の佐賀県でしばらく身を寄せていたが、佐賀県内で稼働する玄海原発の不具合などがたびたび報道されるようになり、ここも安心ではないと感じるようになった。
そんな時に出会ったのが、震災直後から放射能被害を心配する妊婦や親子の支援を続けていた沖縄県のNPO団体「つなぐ光」。
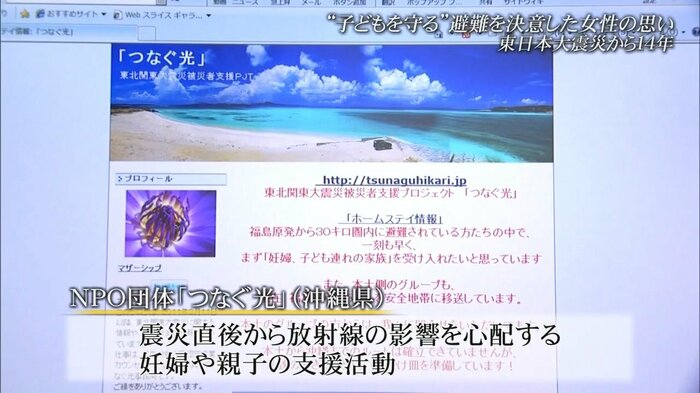
長谷川牧子さん:
原発から半径200km圏内の母子や家庭を保養に来たい人を受け入れされていて、それを知ったので2011年12月に2週間ほどそちらでお世話になりました
その縁もあり長谷川さんは、山村留学生を受け入れている沖縄県国頭郡国頭村の安田地区に移住する決意をした。

長谷川牧子さん:
子どもたちにとっては本当に最高の場所で。しかも地域の人たちが移住者を快く受け入れてくださるところでした。今考えるとあの収入でどうやって生活してきたかなと思うのですが皆さんの助けがありました。沖縄に来て初めて「ゆいまーる」(沖縄で助け合いの意)という言葉を耳にして本当にまさに「ゆいまーる」が地域の皆さんでなっているところなんだなと思いました

避難者にとって大切な地域とのつながりを感じ、地域ぐるみで子育てを応援してくれる安田地区での生活に心が落ち着いたと長谷川さんは振り返る。一方、支援が終了した後の生活は決して楽なものではなく、20以上の職を転々としながら、生活保護を受給する時期もあったという。
長谷川牧子さん:
沖縄県はまだ支援があった方かもしれません。いくつかあった支援も受けつつの状況でしたが、やはり指定された区域ではない自主避難なので何もないのです
沖縄県では被災地からの避難者に対して、応急仮設住宅の提供などを行ってきたが、そのほとんどが支援の期限を迎えていて、現在は福島県の一部地域の避難者に限り、受け入れを続けている。
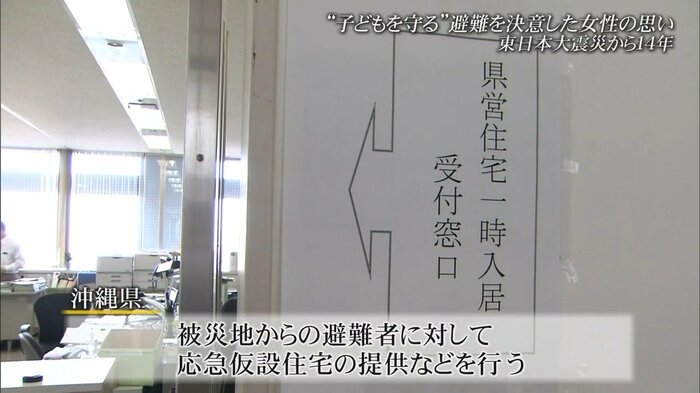
原発政策への不信 「誰が責任取るのか」
震災から14年、原発に翻弄された自身の生活を振り返り、長谷川さんは各地で再稼働が進む原発の現状に疑問を投げかける。
長谷川牧子さん:
事故が一つもこれからまた起こらないと誰が言えるでしょうか。福島の原発の事故が誰も責任を取っていません。国も東電も責任を取ろうと思っても取れないと思います

かつて暮らした茨城に戻ることは考えていない長谷川さん。取り返しのつかない事故の危険性を抱える原発に強い思いを抱き続けている。
東日本大震災では、いまだに全国でおよそ2万8,000人が避難生活を余儀なくされている。被災した方々が安心して暮らせるその日が訪れるまで。私たちは目を向け続ける必要がある。
※4月9日追記
「国連機関の UNSCEAR は、福島の原発事故による放射線被ばくの健康影響に関する報告書で、これまでも健康影響は報告されておらず、将来的な健康影響は見られそうにないこと、妊婦・胎児への健康影響も見られそうにないことを明らかにしています」
(沖縄テレビ)





