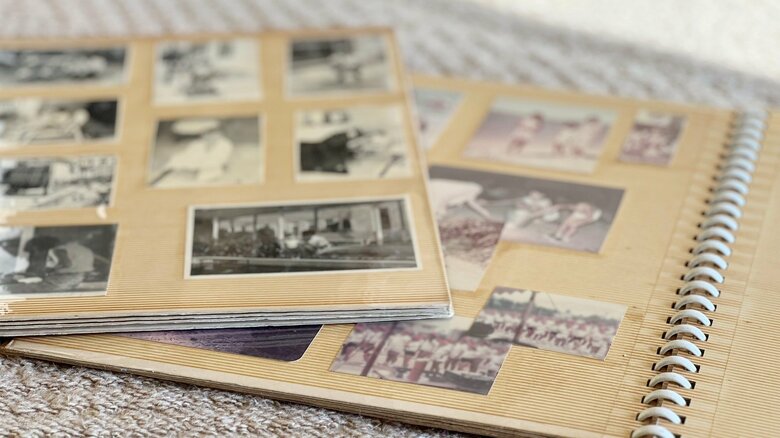「思い出の品を整理するときは、1人で行わないことがポイントです。1人で整理すると、写真やビデオ、旅行のお土産などが出てくるたびに思い出がよみがえり、作業が止まってしまいます。
一方、子供や親戚が『写真は数枚だけ残して、あとはデータ化しようか』『子供の頃に描いた絵は私が持ち帰ってもいい?』といった提案をしていくと、親御さんも判断しやすくなり、整理も進んでいくでしょう」
迷うものは1年取っておく
木村さんが教えてくれたもうひとつのポイントは、「捨てられない物をまとめるボックスをつくること」。
「親御さんが『今はまだ判断できない』というものは、『残すもの』『捨てるもの』とは別に保管場所を用意して、まとめて置いておきましょう。そのまま1年間使ったり見返したりしなかったら処分するなど、ルールを決めておくといいと思います」

遺品整理士認定協会で認定している遺品整理士には、依頼主が判断に迷っていたものは、引き取ってきても1週間程度は置いておくことをお願いしているという。
「後になって『やっぱり使いたい』と思うことがあるんですね。実際にあったケースでは、『持って行ってもらったあのけん玉、ボケ防止のためにやっぱり使いたい』という問い合わせがあり、そのままお渡ししました」
迷っているものがあれば、ムリして捨てないことも、実家片付けには実は大切。
教えてもらった段取りやポイントを意識しながら、親子で片付けについて話すところから始めてみよう。
(遺品整理士が教える片付けの「仕分け術」はこちらの記事で紹介)
木村榮治
一般財団法人遺品整理士認定協会理事長。第三セクター社員を経て病院および民間企業などで勤務。親の遺品整理に立ち会った際、整理業者のずさんな対応に心を痛め、2011年、一般社団法人遺品整理士認定協会を設立。2025年3月現在6万人以上の遺品整理士を誕生させている。著書に『遺品整理士という仕事』(平凡社)、『遺品整理士が教える 遺す技術と片付けの極意 家族の負担を減らす生前整理のすすめ』(メイツ出版)など。
取材・文=有竹亮介