トヨタが静岡県裾野市につくる実証実験都市「Toyota Woven City(トヨタ・ウーブン・シティ)」。
2月22日に豊田章男会長も出席して竣工式が行われ、その一部が報道陣に公開された。

豊田会長は、2020年にアメリカで行われた技術見本市・CESで構想を、そして2025年1月のCESでは詳細を発表し、ついに2025年秋から始動する。
自動運転や水素などを活用しながらどんなことが行われていくのか、街の雰囲気と合わせて解説する。

この街には発明家である「インベーター(Inventors)」と、住民として実証に参加する「ウィーバー(Weavers)」が存在する。
ウィーバーは一般人の視点で実証を評価・フィードバックをすることになる。

見学会で公開されたのは、秋から実証が始まるエリア。14の建物からなり、中央に位置する広場では実証に参加する「ウィーバーズ体験」が行われた。トヨタの「e-Palette」を活用したもので、街の日常を想像させるものだった。
コンセント付きの信号機?地下の道路?
ここでは「民間の土地」であることを生かし、公共の街では実現がしにくい実証実験を行う。
街に設置された信号機を見てみると、伸び縮みしそうなライト部分のほか、コンセントやローカルネットワークの差し込み口が設置されていた。

信号機の柱部分も、センサーやカメラなど後付けの装置が設置しやすいようになっていて、例えば歩行者を検知して信号の時間やモビリティと連動させる、というような実証が可能になるという。
また、車両専用の道路と歩行者専用の道路の間に設けられていたのは、「自転車」ではなく「パーソナルモビリティ」の専用道路。様々なモビリティが同時に存在できる環境となっている。
別エリアの建設が続いている奥には富士山も望める。

さらに公開されたのは、4つ目の道路である「地下の道路」。
この地下の道路は秋から実証が始まるエリアのすべての建物とつながっていて、各住戸への自動配送ロボットによる荷物の配送なども可能だという。
奥まで広がる地下空間の建設には、溶岩による岩盤の堅さも乗り越えたという。

地下は、光や雨を遮ることができるため実証には最適な場所で、「エンジニアの夢を叶えた場所」とのこと。
活用すれば、「配送」だけでなく、各住戸から出たゴミなどの「回収」作業もロボットで自動化できるかもしれないとしている。
また、地下の道路をはじめ、街すべてがデジタル空間にも存在する。デジタルの中で検証をしながら、リアルの街で実証を行うことで、開発を加速できるということだ。

モビリティのテストコースであるこの街には、自動車業界だけでなく、食品業界や教育業界の企業もインベーターとして参加する。
しかし、これだけの大規模な街が、なぜ富士山のふもとに作られたのだろうか?
そもそも…なぜ静岡県裾野市に?
実はこの場所は、トヨタの東富士工場の跡地。
工場は東日本大震災を受けて、被災地への長期的な貢献のために裾野市から東北に移転した。
その際に従業員から「東北に移住したくてもできない」との声があり、これに対して豊田会長(当時社長)は「自動運転などの“大実証実験 コネクティッドシティ”に変革させていこうと考えている」とのアイデアで答えたという。

現に建設中のエリアには建屋がまだ残っている。自動車工場はプレスの機械に対応などするため丈夫な構造となっていて、開発の場として建屋をリノベーションするとのこと。
一般の人が入ることはできるのか?
筆者自身、自動車担当ということで周囲の人から聞かれることが多いこの質問。
答えは「2026年度以降に、実証実験の参加者=ウィーバーとして参加することは検討している」。
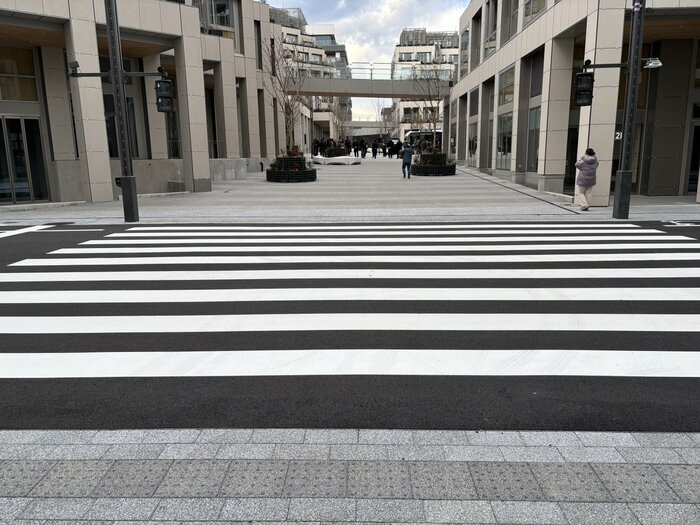
街の実証実験には、そこで住む人の協力が不可欠。まずは実証を行う風土作りとして関係者の入居からスタートする。そのため、将来的に風土ができてきたら公募をしたいとのこと。この街に住み、参加者になることができる日が来るかもしれない。
実証の開始は2025年の秋から
一部の建物ができあがったが、秋の始動に向けて内装工事などが着々と進んでいる。筆者自身、ウーブン・シティに対して「未来」のイメージを持っていたが、足を踏み入れて歩いていくうちに、実証のフェーズはすぐそこまできており、遠い未来ではないことを実感した。
トヨタは異業種やスタートアップとの連携で相乗効果を生み出しながら、トヨタの強みを生かしていくとしている。
秋以降にどんな実証が始まるのか。この街からどんなモビリティが生まれるのか。引き続き注目していく。
(執筆:フジテレビ経済部 丹羽うらら)





