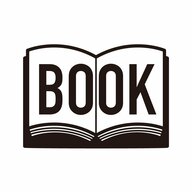先ほども触れたように、原始反射はそれぞれが関連し合っているため、必ずしも「○○にはこの動き」といった1対1対応ではありません。1つの動きをきっかけに原始反射が統合されていく可能性も大いにあります。
親御さんに1つだけ覚えておいていただきたいことがあります。原始反射が残っていると、反射に近い動きをやりたがる子と、逆に反射に近い動きに敏感なためにその動きをやりたがらない子、その両方を持っている子がいます。
その動きをやりたがる子をseeker(シーカー:求める人)、嫌がる子をavoider(アボイダー:避ける人)と呼びます。原始反射を統合するためには、最終的にはseekerの動き、つまりその子がやりたがる動きをとことんやらせてあげることが重要です。

次が「チャレンジ」です。「安全性」にもつながりますが、安全・安心な環境で、子どもが失敗を恐れずチャレンジできるようにしてあげることも大切です。
これは教室ならではの話になりますが、子どもがちょっと頑張ればできるような“余白”をつくってあげたり、難しいけど頑張ればできるようにサポートをしてあげたりすることも必要です。
そして、ピラミッドの最後、もっとも高いところに位置するのが「自立」です。これは文字通り、子どもが自ら考えて行動できるようにすることであり、最終目標です。自分で考えて、次にチャレンジする目標をつくるのも自立といえます。
たとえば教室では、なかなかみんなの中に参加できない子どももいます。すると、ある子が、「私が誘ってくる!」と言って、参加できない子に声をかけに行くことがあります。
こうした行動を見ると、成長を感じます。これも「自立」の1つととらえています。
家庭では、ぜひ、親が強制的にやらせたり、義務にしたりしないで、子どもが自分からやりたがるように導いてあげましょう。まずは毎日の生活の中で負担なく楽しく続けられるものから取り入れてみてください。LUMOでも、スモールステップをとても大切にしています。
少しずつ少しずつ、昨日よりも今日、ほんの少しでもできることが増えたり、前向きな発言が見られたり、笑顔が増えればOK!なのです。
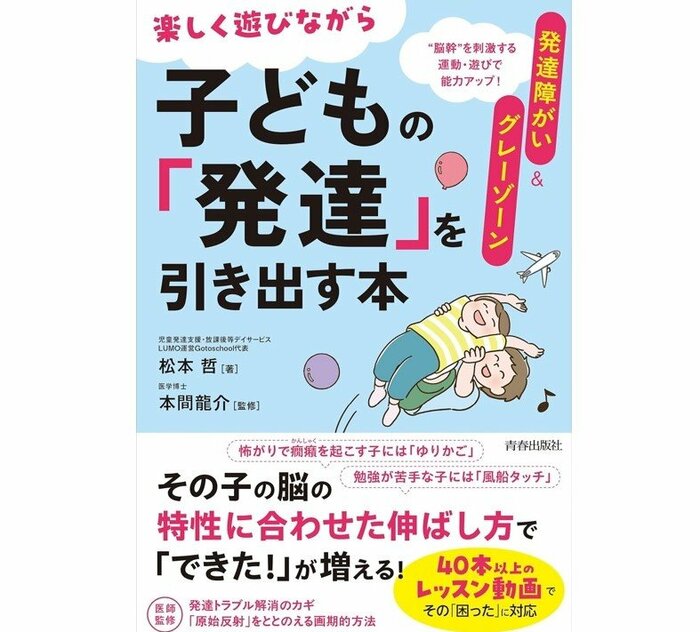
松本哲
2020年「あきらめを、チャレンジに」をミッションに株式会社Gotoschoolを設立。児童発達支援・放課後等デイサービスの「子ども運動教室LUMO(ルーモ)」や就労支援など、人の成長にかかわる課題解決にむけた事業を展開。原始反射の統合により発達を引き出す独自メソッドを構築。
本間龍介(監修者)
医学博士。スクエアクリニック副院長。米国発達障害児バイオロジカル治療学会フェロー。米国抗加齢医学会フェロー。近年は、副腎疲労治療を応用し、認知症状や発達障がいなど脳のトラブルにも治療効果を上げている。