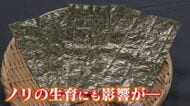道の駅などで販売されている手作りの漬物について。食品衛生法の改正に伴い6月から製造販売には保健所の許可が必要となり、今、漬物作りを断念する農家が増えている。
手作り漬物の販売に影響 食品衛生法改正
赤じそで漬けた真っ赤な梅干し。昔ながらの漬物が今、ピンチを迎えている。

岡山・津山市にある道の駅「久米の里」、地元で採れた野菜などが並ぶ中、漬物コーナーが設けられているが、この日、販売されていたのは「梅干し」のみだった。

なぜ、1つの商品しかないのか?道の駅久米の里・浅図美鈴事務長によると、食品衛生法の改正に伴い6月から漬物製造業の許可をとらなければいけないことになった。それに伴い、生産者が「そこまでお金をかけてできない」ということで、道の駅「久米の里」の漬物コーナーは、ゼロに近い状態になったという。

1年ほど前までは、20軒ほどの農家がたくあんなどの漬物を持ち込んでいたが今、販売されている商品が激減している。
買い物客は「おじいちゃんおばあちゃんが自分の家の味で作っているもののほうが昔懐かしい。しょっぱーい梅のほうがおいしい」と話す。
手作り漬物で食中毒…死亡も
食品衛生法の改正のきっかけは、2012年に北海道で白菜の浅漬けが原因で8人が死亡した食中毒だ。改正法は段階的に施行され、6月から漬物製造業は保健所の許可が必要になり、加工場は自宅の台所と兼用できないなど、高い衛生基準が設けられた。

これを受け、津山市内の加工グループは20年以上に渡って続けた梅干しの加工販売を5月末で終了することを決断している。

倭文加工グループ・片山恵子代表:
(商品に)虫が入らないようにとか、衛生的な事がいろいろある。自分たちで施設をつくってまでできない、年齢的にも。
不作と施設整備の二重苦
一方、県内有数のウメの産地、津山市久米地域では害虫が発生したことで2024年はかつてない不作に。

津山市梅の里管理組合・前原啓志組合長:
いつもなら小梅がびっしりつく。いっぱいつく。ことしは1個だけ
こちらの組合では、梅干しの加工販売を続ける方針だが、施設整備による負担にウメの不作も重なり、頭を悩ます日々だ。

津山市梅の里管理組合・前原啓志組合長は「あるものだけでもとる。平年の20分の1くらい。昔ながらの伝統がどんどん消えていくのは寂しい限り」と惜しみを込めて語った。
日本の食文化に深く根付く漬物。
食品衛生法の改正が伝統的な手作りの味に大きな影響を与えている。
(岡山放送)