新型コロナウイルスが5類に移行して1年。世の中が“平常運転”を続ける一方で、ひとり親家庭を支えるフードバンクは危機的な状況に直面している。2023年に比べ、食料品の支援が100分の1に激減しているのだ。その理由と、ひとり親家庭をとりまく現状を聞いた。
食料品の備蓄激減「去年の100分の1」
新潟県三条市にある県フードバンク連絡協議会の大型倉庫。

新型コロナ禍では、企業からの大口の寄付が多く寄せられたことから、大量の食料品をフォークリフトで積み込み、そのまま保管するために協議会が借りた場所だ。

しかし、現状、倉庫には空きスペースが目立つ。
「ここ数カ月、この倉庫が必要となるような大口の寄付は1件もない」県フードバンク連絡協議会の小林淳事務局長は肩を落とす。

倉庫の中には多少のダンボールがあるものの、その中身のほとんどがマスクや衛生商品で、食料品はレトルト食品と即席麺・コーンフレークのみと、ごく一部。

そして、小林事務局長の口から衝撃の数字が語られた。
「5月単体で言うと、新潟県フードバンク連絡協議会で受け付けた食料品は2023年と比べて100分の1ぐらいになっている」
ウイルス禍には大量の寄付も…
新型コロナ禍で企業からの寄付が大量に寄せられたのには理由があった。
例えば、感染拡大でイベントが中止になった企業が、すでに発注していた食料を持て余し、寄付するケース。また、外食産業などが確保していた食料を使い切れないとして寄付するケースだ。

新型コロナ禍で、食品ロスを軽減しようという観点からも注目されたフードバンク。しかし、ひとり親家庭を支援するという目的に沿った支援は根付かなかったと言える。

また、個人が食料を寄付する場である「フードドライブ」も、新型コロナ禍に比べ、その量は10分の1ほどに減っているという。
この理由について小林事務局長は「行動制限でお金を使う場所が減ったこともあってか、食料品を購入して寄付してくれる方も多かったが、5類移行で日常が戻り、個人からの寄付も減っている」と話す。
フードバンクの登録数は約2.5倍増
一方で、支援を求める人の数は増えている。
新潟県フードバンク連絡協議会への登録数は、2020年には3500世帯だったが、現在では8500世帯に。

アンケートに記載された登録理由の多くには“物価高騰”の文字が並ぶ。「親子で病弱。物価高騰のため買い物をするお金もない」「値上げもあり、食費・光熱費にお金がかかる。友人からお金を借りるなど大変すぎる毎日」
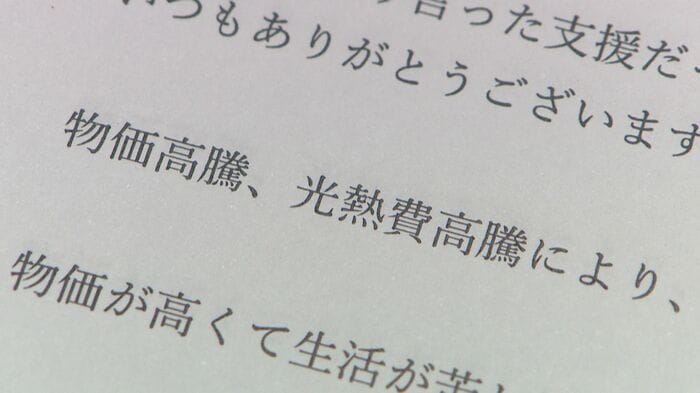
小林事務局長は「食料品の支援を受けたい方は増え続けている一方、前から利用されている方も減ってはいない。格差が固定化している」と見ている。
登録者が増えた背景には、新型コロナ禍にフードバンクが認知されたこと、また、行政との連携が深まり、生活保護世帯や児童扶養手当を受給している世帯に県や市町村がフードバンクのチラシを配布していることがある。
しかし、掘り起こされた需要に応えられる物資がないのが実情だ。
子どもたちには「社会的擁護が必要」
寄付が激減する中、小林事務局長は生活が苦しい子どもたちにもっと目を向けてほしいと訴える。

「新型コロナが5類に移行しても生活が上向いていないひとり親家庭が多い。その中でも、子どもたちは毎日食べたり、勉強したりしている。そうした子どもたちには社会的擁護が必要だということに、もっと理解を広げていかなければいけないと思っている」
「お腹いっぱい食べさせたら…」
この日も、新潟県フードバンク連絡協議会には、食料品を受け取りに来る母親の姿があった。

2人の男の子を育てているという母親は「こういった制度を使わせていただき助かっている。物価高の中で子どもたちにお腹いっぱい食べさせると、どれくらいお金がかかるんだろう…」とつぶやいた。
「お腹いっぱい食べさせてあげたい」その思いに真に耳を傾けるならば、ひとり親家庭やその子どもたちを支える姿勢とはどういうものなのか、改めて社会全体で見つめ直す必要がある。
(NST新潟総合テレビ)





