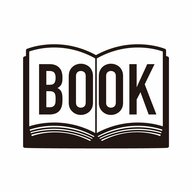新NISAが始まり、約34年ぶりに円安水準を更新、著名人が使われた“投資詐欺”広告でプラットフォームが訴えられるなど、今、“お金”に関するニュースが溢れている。
そんな中、経済学者・嘉悦大学教授の髙橋洋一さんは、「高齢者の財布を狙う『FX』『暗号資産』業者にご用心」と注意を呼びかける。
我々は“お金”について何を理解して、どんなことに気をつければいいのか。高橋さんの著書『60歳からの知っておくべき経済学』(扶桑社新書)から、一部抜粋・再編集して紹介する。
「暗号資産」のほとんどは眉唾?
相変わらず高齢者を狙った詐欺のニュースが相次いでいる。
なかでも、インターネット上で取引されるデータ資産「暗号資産(仮想通貨)」は、ほとんど眉唾だと個人的には思っている。
その理由は、規制があるにもかかわらず、相場が投機的で、適正相場を歪める相場操縦が可能なデジタル通貨だからだ。それに最近は減ったのかもしれないが、暗号資産関連の民間セミナーの多くは怪しいものだ。
もっとも、それは暗号資産をあくまで「投資」手段としてみたときのことであり、「決済」手段として持つのならさして問題はない。

必要な分だけを持ち、送金するときにだけ使う、というように自分でしっかりルールを設ければいい。
今やフリマアプリのメルカリをはじめ、暗号資産を使って取引決済できるサービスも出てきているようだ。
ただし、将来的には、中央銀行による暗号資産の発行が拡大する可能性があり、民間の暗号資産は駆逐されるだろう。暗号資産は単なるプログラムなので、中央銀行が本当のお金を裏づけにして、正しい便宜性のために暗号資産を発行するのは容易だからだ。
暗号資産vsクレジットカード
民間が発行している暗号資産には、ビットコインをはじめたくさんの種類がある。
しかし、もし国家が保証している暗号資産がそこに追加されれば、投資家はどちらを買うだろうか。信用力などの観点から、どうしても民間の暗号資産は見劣りしてしまう。
中央銀行の立場なら、貨幣を紙で発行するか、暗号資産としてデジタル発行するかを選択することができる。中央銀行としては、どちらで発行したかさえはっきりさせておけば、金融市場に混乱が及ぶこともない。
中央銀行が暗号資産を発行すれば、クレジットカードの利用はかなり減るだろう。
すでに中国では、中央銀行がデジタル人民元を発行し、2023年12月に初めて国際金取引が行われた。これは、中央銀行による暗号資産の発行が進む流れの一環だ。

もし、デジタル人民元でクレジットカード的な機能が日本でも実装されれば、日銀が同様の機能を持っていないため、デジタル人民元を利用する人が国内で増えるかもしれない。
これは、国家運営としてはかなり危険な話だ。日本もせっかくデジタル庁を設立したのだから、同様の取り組みを早急に実行したほうがいい。
FXは素人が手を出すべきではない
また、外国為替証拠金取引(FX)に関しても、為替の動きを短期間で読むことは不可能であり、素人が手を出すべきではない。
FXは各国通貨の取引を行い、その差額で利益を得る投資だ。為替の動向をちょっと理解しているからといって、簡単に利益を得られるわけではない。
例えば、米国がインフレで日本がデフレの場合、インフレ率の差で為替が減価するという一般的な理論がある。つまり、インフレ率が高い国の通貨は安くなり、低い国の通貨は高くなるという考え方だ。
しかし、このような定性的な理解だけでは、現在の為替水準が割安なのか割高なのかを定量的に判断することができない。

そもそも、為替は何かの算式でぴったり導き出せるようなものではない。
為替レートは二つの国の通貨の交換比率だが、それを完全に予測するのは不可能だ。もちろん、二つの国のマネタリーベース比から推測することは可能だが、それは完全な予測ではない。予測するための経済理論もあるが、このくらいの期間でみれば何割かの確率で当たる、といった程度の話だ。
あえて定量的にいえば、為替動向は2〜3年のスパンでみて7割くらいしか当たらない。
3ヶ月以内の為替動向は“予測不可能”
経済理論が通用するのは、あくまで長期的な市場の動向であり、短くても3〜5年ほどのスパンの話だ。それでも「まあまあ当たるかな」というレベルで、特にFXのような超短期投資では経済理論から外れるのはよくあることである。
さらにいえば、3カ月以内の為替動向は予測不可能といっていい。
経済学的には「ランダムウォーク」と呼ばれ、過去の出来事から将来の動向や方向性は予測できない。日本語では「酔歩」とも表現され、酔っ払いがふらふら歩いていると一歩先すら予見できないように、予測がつかないほどランダムな動きをすることを指す。

したがって、FXにより短期間で利益を得たい場合は、ほとんど勘で投資をするしかない。
金融業者もこうした事実はよくわかっているから、短期投資よりも長期投資のほうが、投資コストがかかるような仕組みにしている。
いずれにせよ、この手の投資はより深い定量的理解がないとまず儲けられない。
FXや暗号資産などの投資に平気で勧誘してくるような業者は、適当な経済用語を並びたてて商品説明をしてくるかもしれないが、実際には本質を理解してはいない。くれぐれも読者は騙されないよう注意してほしい。
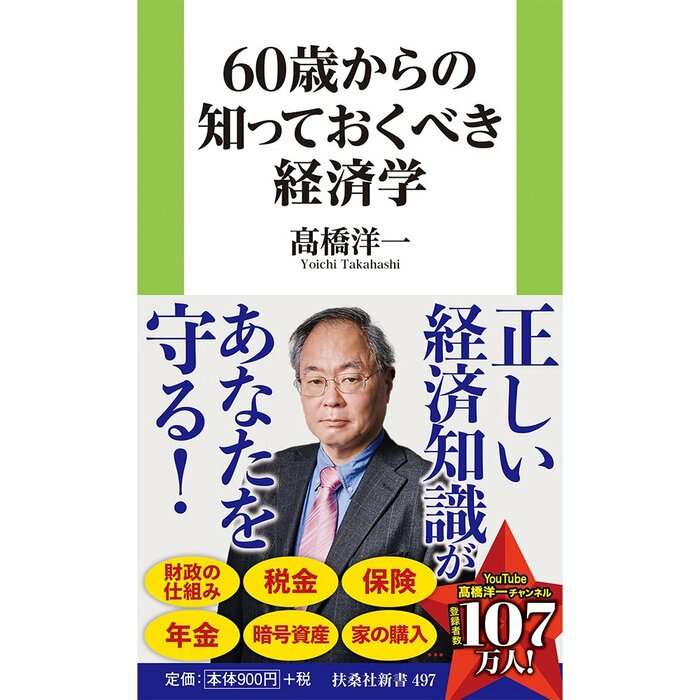
髙橋洋一
1955年東京都生まれ。数量政策学者。嘉悦大学ビジネス創造学部教授、株式会社政策工房代表取締役会長。東京大学理学部数学科・経済学部経済学科卒業。博士(政策研究)。
1980年に大蔵省(現・財務省)入省。大蔵省理財局資金企画室長、プリンストン大学客員研究員、内閣府参事官(経済財政諮問会議特命室)、内閣参事官(内閣総務官室)等を歴任。小泉内閣・第一次安倍内閣ではブレーンとして活躍。「霞が関埋蔵金」の公表や「ふるさと納税」「ねんきん定期便」などの政策を提案。2008年退官。菅義偉内閣では内閣官房参与を務めた。