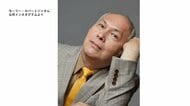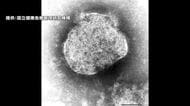高い枕で寝ると、脳卒中の原因の一つであるの発症リスクが高まることが分かった。
国立循環器病研究センターの脳神経内科・江頭柊平医師、田中智貴医長、猪原匡史部長らのグループが、脳卒中の原因の一つである「特発性椎骨動脈解離」は、枕が高いほど発症割合も高いことを立証し、「殿様枕症候群」という新たな疾患の概念を提唱した。
この研究成果は1月29日、国際学術誌「European Stroke Journal」のオンライン版に掲載された。
「脳卒中」は若年~中年者にも特殊な原因で起こる
研究グループによると、脳卒中は通常高齢者に起こる病気だが、若年~中年者にも特殊な原因で起こることがあるという。「特発性椎骨動脈解離」は、その原因の一つで、首の後ろの椎骨動脈という血管が裂けてしまうことで脳卒中を起こす。
働き盛りの年齢である患者の約18%に何らかの障害が残り、根本治療がないことから、発症予防のための原因究明が求められていたが、約3分の2の患者では原因不明だった。
こうした中、研究グループは起床時の発症で誘因のない「特発性椎骨動脈解離」の患者の中に、極端に高い枕を使っている人が存在することに着目。
「高い枕の使用は特発性椎骨動脈解離の関連があるか」「どのくらいの割合の特発性椎骨動脈解離が高い枕に起因するのか」について検討した。
12センチ以上の枕を「高値」と定義
国立循環器病研究センターにおいて、2018~2023年にかけて「特発性椎骨動脈解離と診断された症例群(以下、症候群)」と「同時期に入院した年齢と性別をマッチさせた脳動脈解離以外の対照群(以下、対照群)」を設定し、発症時に使用していた枕の高さを調べた。
なお、高い枕の基準については外部専門家の意見から、12センチ以上を「高値」、15センチ以上は「極端な高値」と定義した。
「症例群」53人と「対照群」53人を調査した結果、高い枕の使用は「症例群」が「対照群」より多く、12センチ以上の枕では34%対15%、15センチ以上の枕では17%対1.9%で、高い枕の使用と特発性椎骨動脈解離の発症には関連が見られたという。また、枕が高ければ高いほど、「特発性椎骨動脈解離」の発症割合が高いことも示唆された。
さらに、この関連は枕が硬いほど顕著で、柔らかい枕では緩和された。

この研究では、枕が高ければ高いほど、「特発性椎骨動脈解離」の発症割合が高いことが示されたわけだが、その理由としてはどのようなことが考えられるのか?また、「特発性椎骨動脈解離」の予防のためには、どのような枕を使えばいいのか?
国立循環器病研究センターの担当者に聞いた。
発症後の根本的な治療がない「特発性椎骨動脈解離」
――「特発性椎骨動脈解離」は、どのような病気?
首の後ろに、頚椎の骨の中を走り、脳に血を送る「椎骨動脈」という動脈があります。動脈の壁は3層の膜が重なってできているのですが、一番内側の内膜が何らかの原因によって裂けてしまうことがあります。
裂けた部位は壁の裏打ちがなくなり脆くなってしまうので、瘤を作って破裂して、くも膜下出血を起こしたり、破れた部分に血栓という血の塊が湧いて、そのまま血管が詰まってしまって脳へ血流がいかなくなり、脳梗塞になったりしてしまいます。くも膜下出血や脳梗塞を起こさなくても、頭痛や首の痛みだけの患者さんも多くいます。
脳卒中は通常、高齢者に起きる病気ですが、この「特発性椎骨動脈解離」では働き盛りの年齢の30~50歳台にも多く発生し、若年性脳卒中の原因の8~11%を占めます。
発症すると18%程度が何らかの後遺症が残るにもかかわらず、発症後の根本的な治療がないので、予防のためにどのようにして起きるのかを解明することが我々の主要な関心ごとでした。

――特発性椎骨動脈解離の「約3分の2の患者では原因不明」、では残りの約3分の1の患者の原因は?
「特発性椎骨動脈解離」の患者さんに、何か思い当たることはないかと聞くと、発症する直前に頭頸部の急な動きがあることがあります。有名なのはヨガやマッサージなどで、他にもゴルフのスイングや、美容室で首をもたれた際などもあります。
動脈が裂ける病気なので、外からの力が血管の壁に負荷をかけるようなことが原因と想定され、これらのエピソードは「軽微な先行外傷(英語ではminor preceding trauma)」として有名でした。
これらの軽微な外傷により解離が起きるメカニズムは注目され、かなり熱心に調べられてきましたが、これが見つかるのは3分の1程度で、残りの3分の2は何も思い当たることがなく、予防にもつながりづらい患者さんが多くいました。
今回、示した枕などの睡眠習慣はとても個人差の大きい、何気ない習慣であり、意識に上らないためか患者さんたちも原因として思い当たらなかったようでした。
また、 正確には特発性に含まれず遺伝性にカテゴライズされますが、「遺伝的に血管が脆い患者さん」という一群もいます。
「特発性椎骨動脈解離」の中に、遺伝的に血管が脆い患者さんたちが紛れている可能性がありますが、ゲノムワイド解析などの包括的な研究を行なっても、はっきり関連が示唆される遺伝子は、現状、見つかっていませんでした。
「極端に高い枕を使わないこと」
――「特発性椎骨動脈解離」と「枕の高さ」の関係に着目した理由は?
着目した理由は臨床経験からです。日中は救急対応や処置で忙しいので、我々は朝回診と言って、入院している患者さんを、朝、回診して、具合が悪くなっていないか確認する文化があります。
原因として思い当たることがない「特発性椎骨動脈解離」の患者さんの病室を、朝、訪ねると、枕に布団を積み上げて、20センチ弱にして寝ていました。
話を聞くと、患者さんには胃食道逆流症という、寝ると胃酸が上がってくる病気があり、胸焼けがひどくて、枕を高くしないと眠れないようで、今回も枕を高くて硬い、へこまないものにした翌日に起きたら発症していたとのことです。
枕などの睡眠習慣はとても個人差の大きい、何気ない習慣であり、意識に上らないためか、本人も原因として思い当たらなかったようでした。
このような経験から「特発性椎骨動脈解離」の患者さんに熱心に聞いていったところ、思いのほか、枕が高い患者さんが多くおり、それを定量的に示した、というのがこの研究の趣旨です。

――枕が高ければ高いほど「特発性椎骨動脈解離」の発症割合が高くなる理由は?
枕が高い方が、椎骨動脈の血管壁への負荷が強くなり、結果的に病気の発症リスクが上がっている可能性があります。
――柔らかい枕では緩和された理由は?
枕は高くても柔らかければ、頭をのせれば、へこむので、結果的には首の屈曲や姿勢異常への効果は弱まると推察されます。
――「特発性椎骨動脈解離」の予防のためには、どんな枕を使えばいい?
我々の研究から言えるのは、12センチ以上のような極端に高い枕では、「特発性椎骨動脈解離」の発症リスクが高まる可能性がある、ということです。
もちろん枕の好みは人それぞれですし、先述の胃食道逆流症の患者さんや、他にも頚椎症の患者さんなど、枕を高くしないと辛い人たちもいるのは、我々も認識しています。
重要なのは首に負担がかかるような極端に高い枕を使わないこと、使う場合も、なるべく柔らかいものを使って首への負担を緩和すること。
そして、頸部屈曲も悪影響を及ぼしていそうなことは、今回の解析からわかっているので、もし頭を上げないと辛い方は、肩から枕を入れて緩やかな傾斜を作るようにして、なるべく頸部屈曲をしないようにするなどの方策が考えられるかもしれません。
また、「特発性椎骨動脈解離」自体は滅多に起こらない、発症率が低い病気ですので、現時点で高い枕を使っていたとしても、 たちまち問題になるというわけでもありませんので、必要以上に不安になることもないことも付記しておこうと思います。

枕が高いほど発症割合も高いことが分かった「特発性椎骨動脈解離」。研究グループが予防策として示したのは「首に負担がかかるような極端に高い枕を使わないこと、使う場合も、なるべく柔らかいものを使って首への負担を緩和すること」だった。
発症率が低い病気とはいえ、発症するリスクを軽減するため、予防策を試してみてほしい。