なぜ力が弱く、抵抗もできない子どもへの性暴力を繰り返すのか。
性加害者が自らの加害者性を自覚してクリニックに受診することはほとんどなく、性加害が発覚したり、事件化されたことで専門機関へとつながることが多い。
こう述べるのは、精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳さん。
著書『子どもへの性加害 性的グルーミングとは何か』(幻冬舎新書)から、子どもへの性犯罪の背景と依存性について一部抜粋・再編集して紹介する。
自ら受診することはほとんどない
2006年5月から2018年12月まで、私が勤める大船榎本クリニックでは、子どもへの性犯罪者117名に対して治療を行ってきました(2023年9月時点で200名を超えています)。
ここであらためて当院のデータを参照しながら、子どもへの性犯罪者の背景をつまびらかにしていきたいと思います。
当然、これは当院におけるデータですので、世のすべての小児性犯罪者を表したものではありませんし、あくまでも氷山の一角です。しかし、一定の実態を浮かび上がらせるものだと思います。
まず、性加害者が何歳のときに当院につながったか、という「初診時の年齢」についてです。
初めて受診した年齢において、最年少は17歳、最年長は62歳でした。ボリュームゾーンは20〜40代で、平均年齢はおよそ35歳です。
ここで注意しなくてはならないのは、あくまでもこれは「初診時」に彼らが何歳であったかというデータであり、初めて性加害をした年齢ではないことです。
彼らは性加害が発覚したり、事件化し逮捕されたことで初めて専門機関へとつながります。

逆にいえば「僕、子どもに性加害をしてしまって…」「自分はひょっとして、このままいくとやばいのでは?」などと罪悪感を抱いたり、自らの加害者性を自覚して、当院に自分からアクセスするというケースはほとんどありません。
クリニックでは、彼らが初めて問題行動を起こした年齢、つまり子どもに初めて加害行為をした年齢を聞いています。
これはあくまでも自己申告ではありますが、下は8歳、上は57歳とこれまた幅広く、平均すると約21歳という結果になりました。
受診までが長ければ加害行為の回数も増える
ここで立ち止まって考えたいのが、「その間にどれぐらいの被害者がいたか?」という問題です。
個人差がありますが、一般的には専門機関につながるまでの時間が長くなればなるほど、加害行為に及ぶ回数は増えていくと考えられます。
また、ひとりの被害者に時間をかけてグルーミングをすることも考えられるので、加害回数と被害者の人数は分けて考えたほうがよいでしょう。
しかし、アメリカの研究者ジョナサン・エイブルの「未治療の性犯罪者は生涯に平均して380人の被害者に対し、延べ581回の加害行為をしている」という言葉からわかるように、治療機関につながるまでの時間が長くなればなるほど、被害にあう子どもの数も増えると見てよいと思います。

クリニックのデータでは、初診時の年齢と初めて性加害に及んだ年齢の開きがもっとも大きかった人は、なんと49年でした。
その人は最初に加害行為を始めたのが8歳で、57歳になって初めてクリニックにつながりました。その間、一度も周囲に発覚せず、問題行動を繰り返していたというわけです。
これらのデータをあらためて平均すると、彼らが初めて子どもに加害行為をしてから当院を受診するまでの平均は、約14年となりました。
また、受刑歴がある人と逮捕歴がある人は合わせて85%にのぼっています。つまり、平均14年もの間、一度も罰せられることなく、子どもへの加害行為を繰り返していたということになります。
ちなみに痴漢が平均約8.1年、盗撮が平均約7.2年ですから、加害行為をし続ける時間としてはあまりに長すぎるといえます。
依存性がある子どもへの性加害
再犯のリスクを自覚している加害者は「好みの子どもを見ると、まるでそれに吸い込まれるように近づいてしまう」とも言います。
子どもへの性加害は、その反復性や衝動性の高さから“アディクション”としての側面もあります。
日本語でいえば依存症(嗜癖・しへき)であり、性的嗜癖行動は行為依存に分類されるといえるでしょう。
この加害者の言葉は、その病的な状態を端的に表していると思います。
依存症とは「ダメ(有害)だとわかっているのに、やめたくてもやめられない」状態です。
一番イメージしやすいのは薬物でしょうか。
「次またやったら捕まる」と頭ではわかっているのに、テレビで覚醒剤のイメージ画像を見ただけでそれが引き金となり、手を出してしまう…というのが依存症のポピュラーなイメージです。
社会的損失や身体的損失があるとわかっているのにもかかわらず、執着がやめられず、すっかり習慣化してしまっている状態です。
3つのタイプがある依存症
依存症は、大きく3つのタイプに分けられます。
(1)物質依存
なんらかの精神作用物質を習慣的に体内に取り入れることで生じる依存症のことです。
主に薬物やアルコール、処方薬やニコチン、カフェインなどに耽溺(たんでき)することを指します。
(2)行為依存
ある行為自体やそのプロセスに耽溺(たんでき)してしまう種類の依存症です。
具体的には、ギャンブルやリストカット、抜毛癖(トリコチロマニア=髪の毛や眉毛など体毛を抜く行為)などの自傷行為、さらに買い物やゲーム、万引きをやめられないクレプトマニア(窃盗症)も行為依存にあたります。

たとえば万引きを繰り返してしまう窃盗症者なら、その商品自体がほしいのではなく、そこに至るまでのリスクやスリル、高揚感や緊張と緩和のサイクルにハマっていくことをイメージするとわかりやすいと思います。
手段が目的化していく、いわば「窃盗のための窃盗」です。また、痴漢や盗撮などの性的な逸脱行動を繰り返す人、さらに広い意味ではワーカホリック(仕事依存)もこのカテゴリーに当てはまります。
(3)関係依存
恋愛や、親と子の密着した関係に依存することです。DVや児童虐待など、家庭内における暴力の問題もはらんでいます。これらは完全に分けられるものばかりではなく、子どもへの性暴力は、行為依存や関係依存の両方の側面を持ち合わせています。
依存症のメカニズムについてここでは深掘りは避けますが、特定の行動や状況、条件下によって脳にある「報酬系」と呼ばれる神経回路が刺激され、満足感や快感を得るドーパミンが分泌されると、この報酬系は問題行動による達成や成功という条件付けによって強化され、やがて条件反射の回路ができあがっていきます。
子どもへの性暴力の場合は、「子どもに触れたい」「子どもと性行為をしたい」などという持続的かつ慢性的な願望や行動が報酬系回路を刺激し、その成功体験が重なるたびに学習された行動は強化され、やがては嗜癖行動へと発展していくのです。
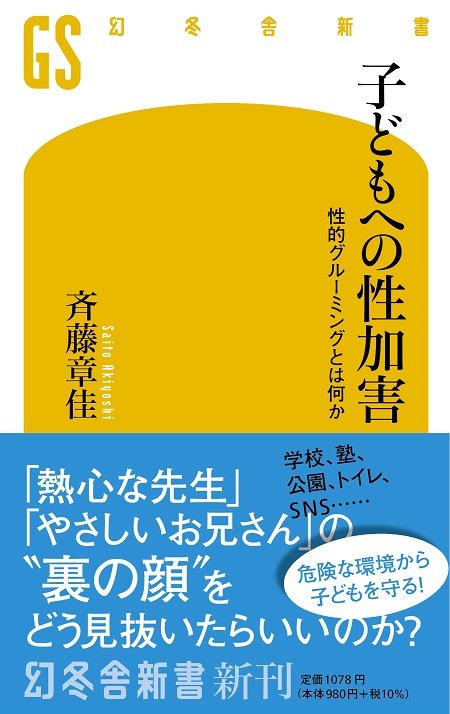

斉藤章佳
精神保健福祉士・社会福祉士。大船榎本クリニック精神保健福祉部長。大学卒業後、アジア最大規模といわれる依存症回復施設の榎本クリニックでソーシャルワーカーとして、アルコール依存症をはじめギャンブル、薬物、性犯罪、児童虐待、DV、クレプトマニア(窃盗症)などあらゆる依存症問題に携わる。専門は加害者臨床で、現在までに2500人以上の性犯罪者の治療に関わる






