東大で筋肉の研究をしながらボディビル選手としても活躍した石井直方さんは、2度がんに罹患し、「2度死んでもおかしくない」ほどの危機を乗り超えた。
そんな石井さんが入院中に意識的に行っていたのは筋トレだ。最近では、手術前後の筋トレが治療過程に組み込まれることも増えているという。なぜ“筋トレ”はそれほどにまで重要なのか。
石井直方さんの著書『いのちのスクワット 鍛えれば筋肉は味方する』(扶桑社)から、一部抜粋・再編集して紹介する。
術前の「プレコンディショニング」としての筋トレ
悪性リンパ腫での1回目の入院後に足腰の衰えを実感して、その後の2回目、3回目の入院時や、肝門部胆管がんの手術の前後にも、スロースクワットを柱とした筋トレを続けてきました。
近年では、がんに限らず大きな手術の前後には、しっかりと筋トレなどの運動を行って体力をつけるとよいという考え方が広まってきています。
私自身も、肝門部胆管がんの手術日の約3週間前から、定期的な筋トレを始めました。
スクワットはもちろんですが、自転車エルゴメーター(エアロバイク)や、呼吸筋のトレーニングも行いました。
予定されていた手術では、みぞおちの下からおよそ40センチにわたって大きく腹部を切り開きます。筋力が足りないと、このような手術後には、横隔膜の上げ下げがうまくできなくなってしまう人もいるのです。
そうした障害を避けるため、前もって専門の器具(簡単な器具ですが)を使って呼吸筋を鍛えます。
吸気の体積を測りながら、目標値まで息を吸っていきます。
これを、1セット10回、1日3〜5セット。私は、普通の患者さんよりも吸う力が強く、器具の上限値の2.5リットルを1日10回、朝昼晩やっていました。

呼吸筋のトレーニングだけに限りませんが、こうしてさまざまな「プレコンディショニング」を行い、筋力・体力を少しでもアップさせておくことが、手術の成功や予後を左右するとされています。
スロースクワットも、もちろんメニューに入っていました。
このときは、本書で紹介しているスロースクワットより、少し刺激の強い方法で行いました。
それは、4秒かけて腰を落としたら、そこで4秒キープ(ここが本書で紹介のスクワットよりきつい部分)、次に4秒かけてゆっくり立ち上がるというものです。これを8回×3セット行いました。
スロースクワットを行うのは週に2〜3回、合間に体幹や上肢のトレーニングを挟むようにしました。
また、以前共同研究も行ったことのある、立派なリハビリ室に赴き、エアロバイクこぎなども行いました。
術後もチューブをつけたまま筋トレ
2020年10月21日に肝臓と胆管の切除手術。12時間以上かかる大手術でした。
一人の人間の周囲に執刀医、麻酔医をはじめとして何人もスタッフがつきそい、12〜13時間という長い時間をかけて手術を成功まで導いてくれたのです。主治医の先生やスタッフのみなさんにはいくら感謝してもしきれません。
術後2日目までは集中治療室。
その後病室に戻ると直ちに、全身にチューブを9本つけたまま、ベッドから立ち上がって、また腰を下ろすという「イスから立つだけスロースクワット」を始めました。
最近の臨床研究では、術後もできるだけベッドに寝ている時間が少ないほうがよいとされているそうです。

術前、術後の筋トレのかいもあって、11月7日に退院。術後これほど短期のうちに退院できる例はまれだそうです。横隔膜の上げ下げにも全く問題は起こりませんでした。
こう書いてしまうと、術後から直ちに元気満々という印象を受けてしまうかもしれません。しかし実際はというと、傷口は痛く、おなかは重く、とてもしんどかったのです。
おそらく知識がなかったら、安静にしているだけで、筋トレなどしなかったでしょう。知識は大事です。本を書いた理由もそこにあります。
大腰筋が太いほど術後の回復が速い
検査で肝臓のCT画像を撮影すると、腰部のインナーマッスルである大腰筋がいっしょに写ります。
東大病院では、この大腰筋の太さと、手術後の回復の速さとの関係を調べていました。私の大腰筋も、データの一例に加わりました。
多くの患者さんのデータの分析から、大腰筋が太いほど、つまり体幹の筋肉がしっかりしているほど、術後の回復が速いことがわかってきたということです。
実際、私自身の大腰筋はかなり太かったらしく、そのおかげで早期の退院が可能となったのかもしれません。
こうして私は、無事に元気な体で自分の家に帰ってくることができました。筋肉を鍛えていなかったら、私のようなケースでは2度死んでいてもおかしくなかったかもしれません。
治療に筋トレが取り入れられてきている
実際に、困難ながん治療と手術を経験して、「筋肉をしっかり維持しておくことが、いのちを助ける大きな力となる」と改めて実感するようになりました。
大腰筋の太さが回復の重要なカギとなるように、いかに日頃から筋肉を鍛えているかが、いざというときにも生きてきます。
私自身も体験しましたが、筋トレが大きな手術の成否を左右する要因のひとつとして認められて、治療の過程の中に組み込まれるケースが増えています。
手術前の筋トレ(プレコンディショニング)と、手術後の筋トレ(リハビリテーション:リハビリ)の両方が、手術の成功率や回復速度を左右する重要なファクターと見なされるようになってきているのです。

もし、みなさんがこれから大きな手術をお受けになるとしたら、こうした情報を役立てていただければ幸いです。
ただ、現在では、どの病院でも術前のプレコンディショニングや術後のリハビリに筋トレを取り入れているわけではないでしょう。
そうした場合でも、スロースクワットであれば、無理のない範囲で病室で行うことが可能です。むろん、主治医や担当の理学療法士と相談したうえでのことになりますが。
がんによる死亡には筋肉量が関係
私自身、がんになると筋肉がやせ細っていく体験をしています。筋肉を維持することでがんを持ちながらも、延命する可能性があるという研究もあります。
今後研究が進めば、がん治療においても筋肉を鍛えることが重要となることがより確かになってくると思います。
マウスの実験では、がんを移植されたマウスは、筋肉が萎縮し、急激にやせ細っていきます。移植後15日から死亡するマウスが増えはじめ、35日までに全滅します。

このマウスに、筋肉増強剤(正確には、筋の成長を抑制しているしくみをブロックし、筋肥大を誘導する物質)を投与すると、がんの成長自体には差が生じなかったにもかかわらず、移植後35日の時点で、まだ80%以上のマウスが生存していたと報告されています。
この実験から、がんの進行による死亡に、筋肉量の減少が密接に関連していることがわかります。
また、がんと共に生きるような状況になっても、筋肉を減らさなければ長生きできる可能性もあるといえるでしょう。
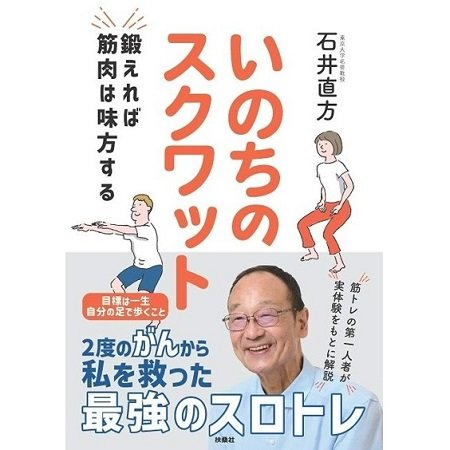
石井直方(いしい なおかた)
現在、東京大学名誉教授。専門は身体運動科学、筋生理学、トレーニング科学。筋肉研究の第一人者。少ない運動量で大きな効果を得る「スロトレ」の開発者。エクササイズと筋肉の関係から老化や健康についての明確な解説には定評があり、現在の筋トレブームの火付け役的な存在。著書に『スロトレ』(高橋書店)、『筋肉革命』(講談社)など多数





