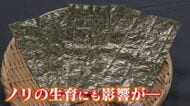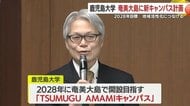6月23日、国の文化審議会が熊本・山都町にある通潤橋(つうじゅんきょう)を国宝に指定するよう文部科学大臣に答申した。秋ごろには正式に国宝に指定される見通しで、指定されれば人吉市の青井阿蘇神社に続き、熊本県内2例目となる。
熊本城を参考に 石造りアーチ水路橋
熊本・山都町にある通潤橋は、高さ約21メートル、長さ約78メートルのかんがい用の橋。石造りのアーチ水路橋としては日本最大級で、「世界かんがい施設遺産」や国の重要文化財にも指定されている。

通潤橋は笹原川の水を白糸大地へと運ぶことで田を潤している。

「鞘石垣(さやいしがき)」と呼ばれる刀の鞘のように反り返った石垣は、熊本城の「武者返し」の石垣を参考にして作られたといわれている。

通潤橋には石でできた通水管が3本通っており、その重さに耐えられる頑丈さと安定性を備えた石垣が必要だった。そこで、大きな城を支える熊本城の石垣の技術に目を付けたという。このように当時の技術の粋を集めて作られた通潤橋は、“近世石橋の傑作”と、国宝指定の答申にあたっても評価されている。
水を運び大地を潤す通潤橋も熊本地震で被災
通潤橋は、江戸時代の1854年、惣庄屋・布田保之助によって、当時の技術の粋を集めて造られた。

通潤橋の完成によって、水の便が悪かった白糸台地に笹原川から水を引くことができるようになった。今でも、約100万平方メートルの水田を潤している。

豪快な放水は、もともとは水路に詰まった土砂などを取り除くために行われていたが、いつしか観光の名物へと変わっていった。

しかし、2016年の熊本地震で壁石が一部せり出し、水が漏れるなどの被害を受けた。さらに、復旧工事中だった2018年にも大雨の影響で石垣の一部が崩れた。こうした災害を乗り越え、2020年に復旧工事が完了した。
観光も潤す通潤橋 梅田山都町長「絶好の機会に」
通潤橋は白糸台地で農業を営む人や山都町の観光にとってもなくてはならないものだ。

今回、国宝に指定される見通しが立ったことについて、山都町の梅田穣町長は「多くの人に通潤橋、山都町の魅力を知ってもらう絶好の機会になれば」と期待を寄せた。
(テレビ熊本)