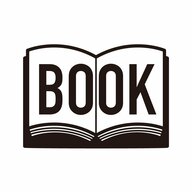プロのオーケストラ団体の中でも最高峰に君臨するのが、1842年に生まれたウィーン・フィルハーモニー管弦楽団だ。
180年という長い歴史の中で戦争や紛争、最近では新型コロナウイルス、ロシアのウクライナに対する軍事侵攻などによって翻弄翻弄(ほんろう)されてきた。そんな苦しい時代でも彼らは音楽のパイオニアであった。
音楽プロデューサーとしてのかたわら、彼らの公演収録に携わり、ウィーン・フィル楽団員の取材を続けてきた渋谷ゆう子さんの著書『ウィーン・フィルの哲学—至高の楽団はなぜ経営母体を持たないのか』(NHK出版新書)より、一部抜粋・再編集して紹介する。
女性の正会員採用は1997年から始まった
ウィーン・フィルの奏者は1997年まで正会員は全員男性で、ウィーンで音楽を学んだオーストリア人がそのほとんどを占める、かなり同質性の高い集団だった。
親子二代、三代や兄弟でウィーン・フィル奏者という団員も少なくなく、奏者の4分の1が親族に団員を持つ者で占められていた時期もある。

地の利や男性、血縁優位で成り立ってきた彼らも、現在では世情に倣い、試験や採用方針を転換。
ウィーン国立歌劇場の正会員採用では、出自や国籍、性別が採用基準を左右しないことはもちろん、オーディションではカーテン越しの演奏で合否を判定している。
それでも、もっとも遅れていたのはジェンダーバランスの問題だった。
女性奏者の正会員採用が始まったのは1997年。創設以来、奏者たちは「フィルハーモニカー」と呼ばれていた。これは他のオーケストラと一線を画すという音楽的賛辞を含む呼称だが、ドイツ語の男性名詞。
男女の雇用機会均等が世界のスタンダードとなり、1980年代にはオーストリアを含む欧米各国ですでに女性雇用におけるガイドラインや法律が制定されていた。
もちろん当のウィーン・フィルも、奏者に力量があれば男女問わず採用したいという意向はあったようで、彼らの公式史とも言える『王たちの民主制─ ウィーン・フィルハーモニー創立150年史』(1992年)の中で、著者の元楽団長のヴァイオリニスト、クレメンス・ヘルスベルクは、女性採用について「オーストリアの法律や規定とのジレンマ」があると述べている。
どういうことだろうか。
オーストリアでは1990年代当時、妊娠や出産・育児に際して、公務員や教師、看護師などの職業に就く人は3年間休職でき(報酬はなし)、また必ず復職できる権利が認められていた。第二、第三子の出産を合わせれば合計6年、9年となる。一方、男性の場合は同様の権利は1年に限定されていた。
男性奏者に対する出産育児休暇は国立歌劇場でもウィーン・フィルでも、退職者などの相応の奏者の代役が可能である場合にのみ認められていた。休暇中はCDなどの印税収入を除いて演奏料は一切支払われず、無給での休暇を強いられる。女性奏者を採用すれば、法律どおりの休暇を与えると、人数の少ないオーケストラで何年も席を空けるメンバーを抱えることになる。
国の制度が整い厳格に運用されていることが、かえって現場の首を絞めることになった。
“女性登用”世界との意識の差
非営利団体に属する個人事業主の集合体である彼らにあって、あえて積極的な女性登用をするという総意が形成できなかったのはここに理由がある。
簡単に言えば、子供を産まない男性側の理解が進まなかったのだ。この点については当時、オーストリア国内での批判も相当あり、多数の政治家からも是正の声があがった。
しかし、これは何もウィーン・フィルに限ったことではない。女性の就業と子を持つことに対する現場の理解は必ずしも浸透していない。一非営利団体の女性登用が遅れたのも、その歴史や社会的背景の中にあって理解できないわけではない。
比較的早い段階から働く女性への権利を保障したベルリン・フィルでさえ、カラヤン(当時ベルリン・フィルの終身首席指揮者兼芸術総監督)が熱心に働きかけた女性クラリネット奏者の採用が叶わなかった騒動などを経て、女性奏者が正式に入団したのは1982年のこと。
ヘルスベルクは先の著書の中で、「男性跋扈(ばっこ)の構造が、ウィーン・フィルの伝統的楽器使用と同様に、その重要な構成要素となっている」として、これまでのウィーン・フィルの音楽と歴史が男性のみで培われてきたことを擁護し、「女性を採用することによって、オーケストラの名声に傷がつくのではないかという多分の怖れ、未知な要素への不安が潜む」と正直に吐露している。
しかし現代は、その懸念こそが逆にマイナス評価として作用する時代である。女性の妊娠・出産・育児の権利と共に、男性の父親としての権利の保障も同様に尊重されるべきであり、国の制度が整備されているならばなおのこと、リーダーには現場の意識改革の推進が求められる。
また、外圧の影響も大きかった。当時アメリカはこうした動きに先んじており、カーネギーホールはウィーン・フィルに対して、1998年までに女性奏者がいなければ舞台に立たせないとする通牒(つうちょう)を突きつけている。
多様性に理解を示すことが時代に要求される正しい在り方であると理解したウィーン・フィルもまた、ヘルスベルクを筆頭に、1990年代後半から変わり始めた。
女性コンサートマスターの誕生
初の「フィルハーモニカーリン」(ドイツ語の女性名詞)になったのはハープ奏者のアンナ・レルケス。ハープ奏者は伝統的に女性奏者の数が圧倒的に多く、オペラで必要なハープ演奏も女性が多く務めていた。
ウィーン国立歌劇場でも同じで、レルケスも国立歌劇場の奏者の一人だった。またシンフォニーの演奏にも必要な場面が多く、レルケスは26年間もの間、正会員の資格が得られないまま、彼らがハープを必要とするときにだけ演奏に参加し続けてきた。

ウィーン・フィルがようやく彼女を正会員と認めたのは、彼女のキャリアの終盤になった1997年のこと。当時は本拠地である楽友協会の控室に女性専用の部屋がなく、着替えにさえ苦労したという。舞台衣装の支給がなかったことなど現実的な問題もあった。
2011年にはブルガリア出身のアルベナ・ダナイローヴァが、ウィーン・フィルとして初の女性コンサートマスターとなっている。「ドイツ首相も女性だし、今や性別や肌の色で区別する時代ではない」と彼女が日本のメディアに語ったように、ダナイローヴァは「ミストレス(女性のコンサートマスター)と表現してほしくない」と言う。
しかしウィーン・フィルの他の正会員の意識は、それほど革新的ではなかったようだ。
ダナイローヴァの国立歌劇場入団とコンサートマスター就任を振り返って、当時の楽団長ヘルスベルクは「簡単なことではなかった」と語っている。オーディションに合格したのち本採用になるかどうかは、試用期間中の活躍と他の奏者からの評価にかかっている。
ダナイローヴァがもしも本採用にならなかったら、その理由を対外的に説明しなければならない。実力の判断以外の思惑、つまり「女性がそのポジションに就くことを良しとしない古い意識しか持ち合わせない」という風評が広まれば、国立歌劇場やウィーン・フィル自体の信用に関わるだろう。
そう判断したヘルスベルクは、自らダナイローヴァのメンターを買って出たという。ダナイローヴァが良い楽器を使えるよう手配し(国立歌劇場もウィーン・フィルも、それぞれが所有している楽器を奏者に貸し出すシステムをとっている)、オペラのソロという大役を任せた。
実力が十分発揮される機会があれば、他の団員は彼女の演奏の力量を公平に判断するはずだと、ダナイローヴァと他の奏者の双方を信用する姿勢をとったのである。
ヘルスベルクのこの采配が功を奏し、長い歴史の中ではじめて女性コンサートマスターを擁するオーケストラへと転換できた。ヘルスベルクは17年という長い期間楽団長を務めており、彼の楽団員への信頼と同様に、楽団員から彼への信頼も厚かった。
ヘルスベルクのような旧時代の正統派奏者、そして楽団長でありウィーン・フィル音楽史の専門家が、女性コンサートマスターの誕生に尽力したことは、以後の女性登用や若手のための組織変革にも大きな影響を与えている。
こうした取り組みはその後も続き、女性奏者は試用期間やエキストラ採用を含め23名(2022年12月時点。正会員は19名)となった。だが正会員が147名であることを考えると、彼らにとってこの変革は始まったばかりとも言える。
ただし、オーストリアでも日本と同様に、同職種における男女の賃金格差の是正を訴える世論があるが、この点についてはウィーン・フィルでは報酬に男女差がないことを公にしており、ある意味現代的と言われるようにすらなっていることも付言しておきたい。
ワーク・ライフ・バランスの変化と伝統の継承
近年、ウィーン・フィルでは定年を迎える団員が多く、入れ替わる形で若い奏者が増えていることから、楽団の平均年齢が下がっている。これに関して楽団長は、「若い世代や女性が増えたことにより、これまでよりもワーク・ライフ・バランスや妊娠・ 出産や子育てとの両立などを現実的に考慮しなければならない」と述べている。

ウィーン国立歌劇場管弦楽団員としてほぼ毎日のようにオーケストラピットで演奏しながら、同時にウィーン・フィル奏者としても働くことは、たとえ家庭を持たない単身者であっても負担の大きいダブルワークである。
妊娠や出産の機会がある女性奏者はなおさらで、他の奏者と同じ待遇では無理が生じるのは当然のことだろう。男性だけの個人事業主団体として長く活動してきた彼らには、女性の身体的差異に考慮した規約も規定もない。長期の産休・育休の扱いや、それに伴う年金制度への対応など、通常のギャランティ以外の福利厚生面の問題もある。
こうした現実の中で近年、新たな対応が進められている。
今後の女性奏者の増加についてどう考えているか、楽団長に話を聞いたところ、「今では逆にその質問自体が不自然だ。オーディションでは演奏をブラインドで評価する。ジェンダーが何であるかすら、すでに問題ではない」と回答した。
ことさらにジェンダーの問題として取り上げるのではなく、どのような性別、世代、国籍でも等しく門戸が開かれ、等しく評価される時代であると答えを出しているようだ。
しかしながら一方で、かつてヘルスベルクが憂慮したとおり、この多様性ある正会員採用の方針転換によって、彼らの音楽的な特徴、ウィーンの楽器による伝統に則った特異な奏法と音楽的な差異が失われ、世界標準化してしまったのではないかという意見は散見される。

ウィーン・フィルはある種、独特の辺境的な音楽文化を担っていた。ワルツなどに代表される民族的音楽性、楽器の特殊性に加えて、ウィーンという、ハプスブルグ帝国では中枢の、その後は欧州の小国の首都としての土地性がもたらす文化である。そうして生まれ育った音楽を、その地で生まれ育った男性の音楽家のみが偏屈なまでに演奏するオーケストラが、古き良きウィーン・フィルであった。
そこには、俗に言う「ウィーン奏法」と呼ばれる独特な弦楽サウンドが存在しており、現在でもこの奏法を専門に研究している学者もいる。現在のコンサートマスターであるシュトイデもその一人。そうした音楽の特徴は奏者間で受け継がれていくだけでなく、その音楽を理解する指揮者によっても伝承される。
閉じたウィーン音楽界だからこそ残ってきたそれらの歴史や辺境的特徴は、グローバル化した社会では容易に失われてしまう。これはウィーン・フィルだけの問題ではなく、現在世界中のオーケストラが抱えている均質化への懸念である。それぞれのオーケストラが持つ特徴的な差異を失うことは、果たして音楽の世界にとってより良い未来なのだろうか。
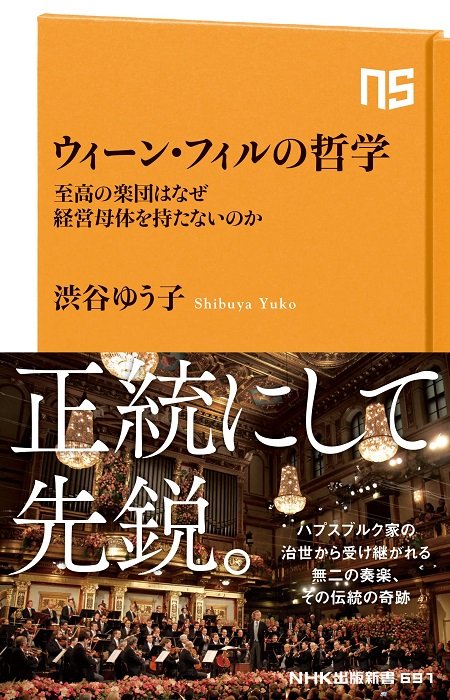
渋谷ゆう子
音楽プロデューサー、文筆家。株式会社ノモス代表取締役として、海外オーケストラをはじめとするクラシック音楽の音源制作やコンサート企画運営を展開。また演奏家支援セミナーやオーディオメーカーのコンサルティングを行う一方、ウィーン・フィルなどに密着し取材を続けている