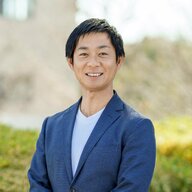我が子がやるべきことをやらない、言うことを聞かない…。
「言い聞かせる」「注意する」「叱る」といった「教えたい」気持ちをいったん捨てて、とにかく目の前の子どもを「ただ見る」こと。
たったそれだけで、子どもとの関係が大きく変わる一歩となると、学校の「先生の先生」として活躍中の現役小学校教師・庄子寛之氏は言う。
多くの子どもとその保護者と接してきた経験から、子どもの可能性を伸ばし、やる気を引き出すことができる家庭には「待ち上手」という共通点があるという。
庄子氏が学校の教室で行ってきたこと、保護者の方から学んだケーススタディなどをもとに、5つのステップと5つのマジックワードにまとめた著書『子どもが伸びる「待ち上手」な親の習慣』(青春出版社)から、一部抜粋・再編集して紹介する。
洋服を脱ぎ散らかしてしまう我が子
【ケース】
うちの子は毎日服を脱ぎ散らかして、片付けません。
「片付けなさい!」
「昨日も片付けてなかったわよ」
「何度言ったら分かるの!」
と怒ってばかりです。
時には、ほめていますが、うまくいかず、自己嫌悪になります。
どうすればいいのでしょうか?
ここで大事なことは、むやみに口を出さず、「ただ見る」こと。
毎日言われているなら、子どもだって親を怒らせたくてやっているわけではありません。
ついつい忘れてしまうのです。
そもそも脱ぎ散らかすことが習慣化してしまっていて、抜け出せないのでしょう。
大切なことは、ポイントの1つ目「人はすぐには変われない」ことを理解することです。
習慣というのは厄介で、無意識のうちにさまざまなことをしてくれます。
毎日靴を右足から履いて、自転車のサドルを踏んで…なんて意識していませんよね。
人は一日の中で無意識にたくさんのことをしています。
我が子にとって、服を脱ぎ散らかすことはその1つなのでしょう。一度叱ったところですぐには直らないものです。

そこを叱り続けると、「ぼくは直そうとしているのにできないだめな子だ」と無意識に思うようになり、子どもの自己肯定感が下がります。
自己肯定感が下がると、子どものやる気や自信がどんどん下がってしまいます。
服をしまうことができるようになることと引き換えに、「ぼくはどうせできない子だ」と思ってほしいという親はいませんよね?
子どもの「やらない権利を認める」
一度言ってもできない我が子を見たときには、「人間だから、すぐには変われないんだ。私だってこんなところあるもんな」と、子どもに注意する前に考えてみてください。
そして、ここでポイントの2つ目、「やらない権利を認める」のです。
まずはだまされたと思って、どんなことにも子どもにはやらない権利があると思いながら接してみてください。
「えっ、服を脱ぎ散らかすのを、この先もずっと認めろってこと?」と思うかもしれませんが、そうではありません。

そもそも服を脱ぎ散らかすことで、我が子の人生にどう影響するのでしょう。
ここで言わないと、子どもは一生服を脱ぎ散らかしてしまうのでしょうか。
逆に、ここで言えば、この先は必ず脱いだ服を洗濯カゴに入れる子に育つのでしょうか。
きっとそんなことはないですよね。
ですので、とにかく、今はやらない権利を認めましょう。あなたにとって最初はじっと我慢をしてただ見ることになるかと思います。
脱ぎ散らかすのが課題だとしたら、脱いでいる瞬間の我が子をどれだけ見ていますか?
どうやって脱ぎ散らかしていますか?
脱ぎ散らかした後、何をしていますか?
我が子が脱いでいるとき、親であるあなたは、どこにいて、何をしているのでしょう。
そう。私達親は、よく見ているようで、実はあまり見ていないのです。
あなたが我が子に「やらせたい」と思っていることがあるとしたら、まずはやらない理由に興味をもって、その行動をただ見ることです。
一回ではありません。継続して見るようにします。
忙しくてそんなことできないと思うかもしれませんが、騙されたと思って3日間だけでも続けてみてください。その中で必ず変化が見えてきます。
その変化を見逃さないように、ただただよく見ましょう。
毎日脱ぎ散らかしている中にも、必ず変化が見られます。
これがポイントの3つ目「小さな変化を感じ取る」です。
「小さな変化を感じ取る」ことで生まれる変化
着替える前にテレビを見ていて、急いで着替えてまたテレビを見るから脱ぎ散らかしているんだな。
そもそも、このテレビはなぜおもしろいと思っているのだろう。
何も言わないで見ていると、片付けることもあるんだな。
いつもはここに脱ぎ散らかしているのに、今日はここにまとまって置いてあるな。
…などなど、どんどんちょっとした変化が見えてきます。
片付けがちゃんとできていなくても、プラスの変化には声をかけます。

「服ここにまとめてあるじゃん。すごいじゃん」
「ここで、洗濯物カゴまで持っていくと、100点だね」
「今日は朝起きてすぐ着替えたじゃん!寒いのにさすがだね」
声をかけるときのポイントは、我が子が服を脱ぎ散らかさないようになってほしいという思いを捨てて、素直に行動の変化を認める言葉がけをすることです。
ただただよく見ることを意識し、お子さんにそれが伝われば、子どもにも変化が生まれてきます。その変化に気づけるようになれば、子どもは少しずつ自分から片付けるようになっていくものです。
もちろんすぐには変わりません。
変わるのは明日かもしれないし、一年後かもしれません。
とにかく興味をもってただ見ましょう。
たとえ脱ぎ散らかすことがすぐには直らなくても、我が子の違う良いところが見えてくるはずです。
人間は承認欲求の強い生き物です。
子どもたちは、どんなときでも親の承認を求めています。褒ほめられたくて仕方ないのです。
人はすぐに変われないことを自覚しながら、ささいな変化に目を向ける。
できていないことに関しては、我が子のやらない権利を意識して言わない。
ただよく見て、小さな変化を感じ取る。
ただ見るというのは、思っているよりも大変な作業です。ついつい言いたくなってしまいます。
でも、それが家族ではなくて職場の方だったら言いますか?まあ、職場で脱ぎ散らかしている人を見ることはないと思いますが(笑)。

職場のとなりの人が、片付けができなくてデスクの上がぐちゃぐちゃでも、ちゃんと仕事をしていれば「片付けたほうがいいですよ」とは言わないはずです。
我が子だから言ってしまうのです。
我が子だからつい口に出して指摘してしまうことを、指摘しないでただ見るクセをつけましょう。小さな変化を感じ取ろうと「ただ見る」のです。
まずは、「やらない」「言うことを聞かない」我が子の気持ちに寄り添いましょう。
そして、あなたがそれを意識することができたら、片付けなかったときにただイライラをぶつけるだけだったあなたと子どもとの関係にも変化が出てきます。
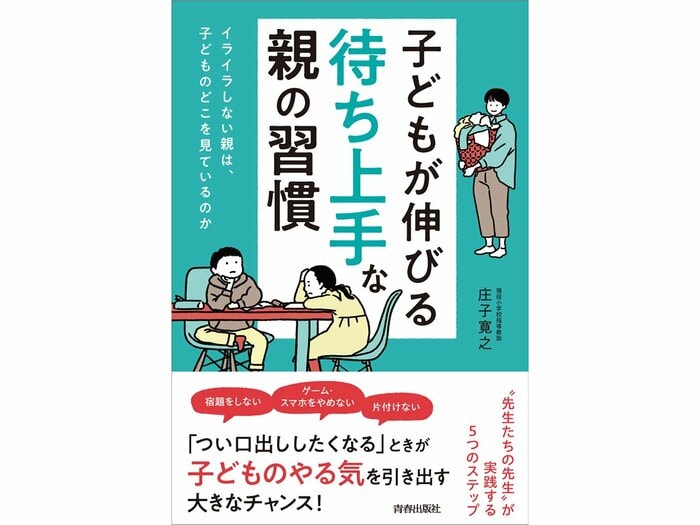
庄子寛之(しょうじ ひろゆき)
東京都公立小学校指導教諭。
学級担任をするかたわら、「先生の先生」として全国各地で講演を行っている。担任した児童は500人以上、講師として直接指導した教育関係者は2000人以上にのぼる。
元女子ラクロス日本代表監督の顔も持ち、2013年、U-21日本代表監督としてアジア大会優勝、2019年、U-19日本代表監督として日本ラクロス史上トップタイの世界大会5位入賞を果たす。
著書に『叱らない技術』『with コロナ時代の授業の在り方』(ともに明治図書出版)、『オンライン学級あそび』(学陽書房)など多数。