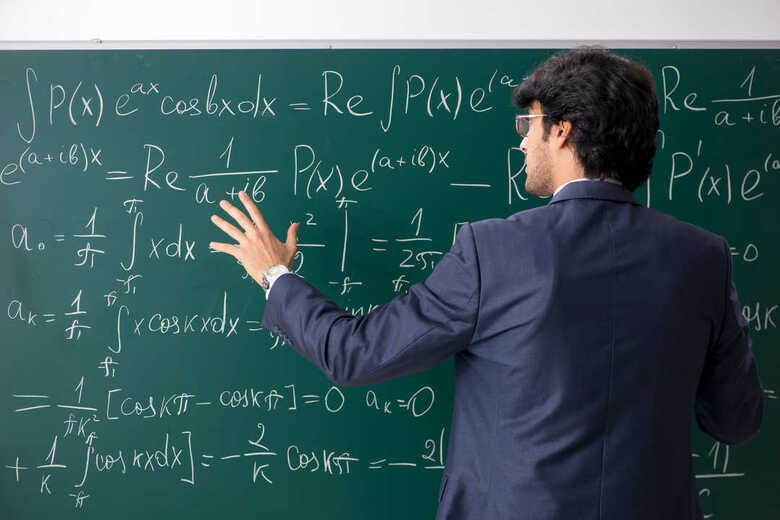就活の教員人気は「ブラック職場」のイメージ定着で下がり続けている。さらに新卒採用は人手不足による「売り手市場」だ。このため教員の志願者数は年々減少し、教員採用試験の倍率低下が止まらない。
ベテラン教員の大量退職時代
教員の世界は、ベテラン職員の大量退職時代が到来している。彼らは第2次ベビーブームに対応するため大量採用された世代で、不足分を補うため、いま教育現場ではこれまで以上に新卒採用が必要となっている。
小学校教員の新規採用者数は2000年に4千人だったが、2018年には1万6千人と4倍になっている。これにともない採用試験の倍率は低下し、2000年は12.5倍の狭き門だったのが、2018年には3.2倍になった。
特に東京都内では教員志望者が激減し、倍率は2倍を切る状況となっている。これによって教育現場で懸念されているのが、教員のレベル低下だ。
「採用試験の倍率が2倍を切るということは、実質的に試験を受ければ採用されるということです。昨年度も教育実習でこのひとは使えないなあと評価した学生が、ほかの学校で教員として採用されたのを見てびっくりしたことがあります」(都内の小学校関係者)
教育実習を受けさせない企業も

こうした状況に対して、文部科学省は危機感を募らせている。
2017年の学習指導要領の改訂を担当し、「学習指導要領の読み方・活かし方」などの著書がある文科省初等中等教育局の合田哲雄財務課長はこう言う。
「教員免許制度のもと、倍率が下がっているから直ちに教員のレベルが低下したとは考えていません。しかし、売り手市場が続く中、企業側は採用に必死で、人材獲得競争は激化しています。最近は採用内定を出す際、教育学科の学生に対して、教育実習を受けないことを確約させる企業もあると聞きます。教育実習をしないと教員免許はとれませんから、学生はその時点で教員になることを諦めないといけなくなります」
小学校の教員免許を持って卒業し、教壇に立ってほしいと期待されていた学生が、企業や自治体の行政職などに就職している話は、いま全国で聞かれる。
新卒を採用できなくなれば、やがて学校が存続できなくなる可能性もある。そのため合田課長は、「守りではなく攻めの姿勢が不可欠だ」と言う。
「教職の魅力を高めるために、教職員の定数を改善し、部活動の指導員を充実させ、勤務時間に上限ガイドラインを定めるなど、学校の働き方改革を行政と学校が一丸となって進める決意です。同時に、一度企業などに就職したり、家庭で育児に専念している『潜在教員』を取り戻すことも必要です」
そのために必要なのが、これまでの教員免許のあり方にとらわれず、さまざまな分野や職歴をもった、より多様で豊富な人材を獲得することだ。
先月柴山文科大臣の諮問を受けて、中央審議会で「新しい時代の初等中等教育の在り方部会」のキックオフが行われた。そのテーマの一つが、「優秀な人材をどう学校現場に獲得するか」。諮問では「免許制度や教員の養成・採用・研修・勤務環境の在り方」が取り上げられた。

多様化が求められる教員の同質文化
教員になる学生が減少する中で、いま注目されているのが「特別免許」だ。
特別免許とは、大学などの教職課程を履修していないが、専門的な知識や経験をもっている外部人材を教員として採用する制度で、1988年に創設された。小・中・高等学校のすべての教科や、特別支援学校の活動について授与されるが、都道府県の教育委員会が行う検定に合格する必要がある。
しかし特別免許が授与されたのは2016年までの約30年間で、全国の公立小学校でたった2人、公立中学校で38人に過ぎない。
なぜ教育現場はこの制度を活用しないのか?
「小学校の教員は基本的に全教科を担任しますから、小学校には『全教科を教えられないと教壇に立てない』という風土があります。それを前提とした教員免許カリキュラムを組んでいるのが地元国立大学の教育学部ですが、そこを卒業した人たちが退職校長会や校長会、教育委員会の指導主事などでマジョリティを占めています。この同質性の高い教員文化の『当たり前』が強すぎることも、特別免許の授与に消極的な背景になっています」(合田課長)
つまり同じ経験や経歴を持つ教員の「当たり前」が、「異質」な教員を受け入れて教員文化の多様性を高める上で、壁となっているのだ。
しかし来年教育改革がスタートすれば、小学校中・高学年から英語教育が本格的に始まる。教員の負担は増えるばかりだし、そもそもこれまで触れてこなかった英語を、教員が教えることができるのかという懸念もある。英語を教えられる外部人材を教育現場に獲得するのは急務なのだ。
戦後生まれの教員免許制度

現行の教員免許が法制化されたのは、戦後間もない1949年。その後も大きな体系は変わっていない。当時の教員の人生モデルは、「18歳で教員になろうと教育学部に入学し、22歳で教員になり60歳まで勤め上げて退職する」だった。しかし人生100年時代を迎え、教員の人生モデル自体も大きく変容している。
さらに令和となり、子どもたちはAIやビッグデータの時代を生きている。最適な教員の人材確保のためには、理系学生が教職課程を履修しやすくすることも必要だ。いまの免許制度では、中学校の理科の教員は、小学校の算数を教えられない。
こうした「参入障壁」も、見直さなくてはならないだろう。
戦後に生まれた教員免許制度が、はたして令和の時代に通じるのか。
「志高く優秀な人材、新規採用だけでなく中堅層の獲得でも、これまでの免許制度や教員養成にとらわれてはいけないと思います。より多様な人材が教壇に立つためには、企業やNPOなどと『回転ドア』方式で人材の流動性を高める必要もあります」(合田課長)
教員免許改革は待ったなし
いま教育現場で求められている教員像は、「一回一回の授業という舞台の『主演俳優』という役割だけではない」と合田課長は言う。
「単元や年間という単位で学びのシナリオを作り、学校外からゲストを呼んだり、子どもたちの思いもよらぬつぶやきや発想を即興で活かして、授業の展開を組みかえたりといった、『脚本家』や『演出家』の役割がますます強く求められます」
こうした「教師力」は、これまで日本の教育の強みであった。
しかし教員免許のあり方は、令和を迎えたいま限界にきている。多様な外部人材を公教育の場に呼び込み、子どもたちの学びを活性化するために、改革に躊躇している時間は無い。