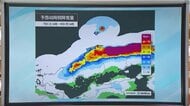味噌や醤油、日本酒など日本の伝統的な発酵食品に欠かせない「糀(こうじ)」。
その「糀」が島根・松江市にある明治時代から続く老舗「森脇糀店」で作られ続けている。
夫の病気で存続の危機に直面するも、妻である6代目の森脇千保美さんとその娘である片寄由美さんが継承している。
発酵食品ブームで需要も高まる中、日本の食文化を支える糀づくりに日々励む姿を追った。
湯気が立ち上る糀づくりの現場
寒さが厳しくなってきた12月初旬、松江市美保関町の一軒の建物から湯気が立ち上っていた。
明治時代から続く森脇糀店、6代目の森脇千保美さんと娘の片寄由美さんが迎えてくれた。
この日、取材にあたったJALふるさとアンバサダーの藤田エミさんも糀づくりを体験。
蒸し上げたばかりの米は「熱くて重い」という。

「あんた、冷めた?冷めちょう冷めちょう。こっちはいいわ」と千保美さんが声をかける。
「お米を冷ますことって大事なんですか?」と藤田さんが尋ねると、
「あまり冷めすぎると発酵が遅くなるし、熱かったら変になる」と一つ一つの作業の意味を説明してくれた。

糀づくりの工程はシンプルだ。
約50キロの米と麦を蒸し上げ、あら熱を取り、京都から取り寄せた糀菌をふりかけて揉み込む。
その後、温度や湿度を調整した室で寝かせ、夕方に発酵の様子を見ながら再び揉み込む。2日ほどで「糀」が出来上がるという。

「今は菌を入れたからまんべんなく菌が行き渡るように混ぜているところ」と千保美さんが説明。
蒸し上げた米を素手で揉み込む作業を体験した藤田さんは「結構力がいりますね」と驚いた様子だった。
突然の試練…存続の危機も 親子の絆で継承へ

森脇糀店では米糀のほか、麦糀、そして自家製の糀を使った味噌も製造している。
現在は、親戚の森脇真子さんも加わり、3人で週に2日のペースで糀づくりを行っている。
しかし、糀づくりを続けてきた道のりは決して平坦ではなかった。
「去年は大変でした。10月に倒れて、10月と11月は休業していた」と千保美さんが振り返る。

40年ほど前に両親から家業を継ぎ、二人三脚で歩んできた夫の正則さんが2024年、脳梗塞で倒れたのだ。
一命はとりとめたものの後遺症が残り、仕事場に立つことができなくなってしまった。
突然降りかかった出来事に、千保美さんは途方に暮れた。
その時、支えとなったのが娘の由美さんだった。
結婚して家を離れ、松江市内で美容師をしている彼女は、その合間を縫って店に戻り、糀づくりを手伝うようになった。

「跡を継ごうという気持ちはあった、まだ父が元気な時に。それが急にしないといけなくなったというのはあります」と由美さんは語る。
受け継がれる伝統と新たな展望
由美さんは美容師の仕事をしながら、母から糀づくりを学んでいる。
しかし長年の経験が必要な繊細な作業だ。

「糀から熱がでるんですけど、その(揉みこむ)加減というか、私には経験が浅いので、これから勉強しないと」、先祖から受け継いだ糀づくりに携わるようになって、由美さんは新たな気づきを得た。

「お客様が『ここの糀じゃないと』と言って下さると、なかなかそれを(辞めてしまうのはいけない)と思うようになりました」と語り、地域に食文化として深く根差していることを実感していた。
「試練だけど…二人三脚で」 地域の食文化を次世代へ
「発酵食品」ブームを受け、需要が高まる「糀」。
由美さんは地道に受け継いできた食の文化を次の時代にも残したいと考えている。

「続けていきたいとは思いますけど」と言う由美さんに、母の千保美さんは「絶対できるとは言えないけん、そのつもりで前進だわね」と応える。
母のあとを継ぐつもりの由美さんは、今の自宅近くに「室(むろ)」を移設することも検討している。
美容師と糀づくり、2つの道を両立させるための模索は続いている。

「試練と思っている、主人が病気になって。ずっと今まで二人三脚でやってきてたんだけど、これも私の人生と受け入れないとね。次に明るい意見もあるし先もちょっと見えたようだから、出来る範囲で頑張ってやろうかなと思っているところ」と千保美さん。
すると由美さんが「教えてもらわないといけないので、もうちょっと頑張ってもらわないと私一人ではまだできないので…ボケ防止に」と笑顔で返す。
山陰の港町で日本の伝統食を育んできた「森脇糀店」。
一歩一歩だが着実に親子のバトンが受け継がれようとしている。
(TSKさんいん中央テレビ)