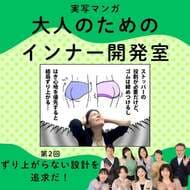石井食品は「地域と旬」を掲げ、日本各地で見つけた旬の食材の魅力をより多くの人に届けたいと考えています。その活動の一環として、「有機の里づくり」千葉県団体連絡会(ちばだん)と良品計画と共同で、有機野菜の商品開発を行っています。
その商品に使われている野菜を生産しているのが市原市にあるONE DROP FARMです。今回は、ONE DROP FARMの代表豊増さんと、石井食品の中で地域との連携を行う素材価値開発部の三谷が、現在農家に起きている現実などを語ります。

現場で何が起きているのか?猛暑と干ばつが及ぼす影響
--- ONE DROP FARMについて教えてください。
ONE DROP FARM 豊増さん(以下、豊増):ワンドロップファームは千葉県市原市に拠点を置く、里山再生型の農場です。有機JAS認証の野菜と養蜂を手がけています。耕作放棄地や里山を整備し、ミツバチの蜜源植物を育てることで生態系を回復させ、非加熱の百花蜜とみずみずしい野菜を生産。7.3haの圃場で人参・大根・ナスなどを育て、「おいしい」「気持ちいい」「楽しい」を大切に、里山の風景と農の文化を次世代へつなぐことを目指しています。
--- 今年の夏は、猛暑と干ばつが続いています。畑にはどのような影響が生じていますか?
豊増:今年は特に厳しいですね。にんじんの種を8月10日に蒔いたのですが、例年なら3〜7日で芽が出たあとは多少の高温でも大丈夫なのですが、に、今年は発芽後すぐに枯れてしまいました。にんじんの芽は非常に繊細で、気温が35度を超えると発芽しても葉が焼けつくようにしおれてしまうんです。
— 苗が"溶ける"というのは、どういう状態なのでしょうか?
豊増:乾燥と高温のせいで、植物が水分を吸う前に蒸発してしまうんです。まるでドライヤーを当て続けているような状態です。葉物も同じで、冷蔵庫に入れた葉物が溶けたようになる、あの感じに近いです。気温と湿度、そして土壌の状態が複雑に絡み合って、ほんの数日の気候変化で畑の命運が変わります。

— 他にも影響が出ている野菜はありますか?
豊増:例えばキャベツやブロッコリーなどの結球野菜と呼ばれる種類の野菜は、初期の外葉の成長が気温に左右されます。秋冬の植え付けが難しくなり、1〜2週間のズレで豊作か不作かがわかれます。現在、そのリスクヘッジの幅が極端に狭まっており、以前なら、5週間のうち4週間は良い結果が出ていたのが、今は1〜2週間しか成功しない感覚です。
--- この気候の影響は価格にも出てきそうですね?
豊増:個人的な印象ですが、11月頃に出始めの野菜が極端に少なくなって高騰し、年末に暴落するというサイクルになる可能性があります。特にキャベツ、白菜、ブロッコリー、ほうれん草、小松菜などの葉物系は打撃を受けやすいと見ています。
--- こうした気候変動に対して、農業の現場ではどのような対策がされているのでしょうか?
豊増:最近では、「設備勝負だね」という会話が農家の間で増えました。井戸を掘る、ハウスを建てる、遮光ネットを張るなどの投資が不可欠になってきています。例えば、3ヘクタールの畑があったら、1ヘクタールはリスク回避のためにハウスにするなど、単に自然任せの露地栽培では太刀打ちできない時代になりました。今、農業はまさに“設備産業”です。
石井食品とは「この人と一緒にやってみたい」と思えた
--- 石井食品とのつながりは、どのような経緯で生まれたのでしょうか?
石井食品・三谷(以下、三谷):私たちは日々、原材料の調達や商品づくりにおいて「誰が、どんな風に作っているのか」を大事にしています。その中で豊増さんの取り組みを知り、現場を訪れたのが最初のきっかけでした。実際に畑を見て、土の匂いを感じて、これを多くの人に届けたいと感じたんです。
豊増:石井食品は「人を見る会社」だと思いました。農家の作るものに興味を持つというより、「この人と一緒にやってみたい」と思える相手を探している印象です。だから僕もやりやすかったです。
三谷:豊増さんの野菜って、ただ有機栽培だからすごいとか、珍しいから扱いたいという話ではなく、食べてみて驚きがあるんです。香りも、甘みも、歯ごたえも、「あ、これは語りたくなる味だ」と思える。商品にしたときのストーリーが自然と湧いてくるんですよ。
--- 石井食品とのやり取りで、印象的なエピソードはありますか?
豊増:あります。実は、以前すごく天候が悪くて、どうしても納品が遅れてしまったことがあったんです。普通なら取引先から怒られてもおかしくない状況だったんですが、石井食品さんは「大丈夫です、畑のことはわかってますから」って言ってくれて。その一言が本当にありがたかった。
三谷:私たちとしては、自然の中で生き物を育てている農家さんの事情を無視してスケジュールを押し通すことは、本末転倒だと思っています。むしろ、“自然のリズム”を商品に反映させたいと考えています。

「BLOF理論」との出会いが自身のやり方を変えた
--- 豊増さんが有機栽培に取り組むようになったきっかけは何だったのでしょうか?
豊増:2010年、千葉県木更津で「耕す木更津農場(現:KURKKU FIELDS(クルックフィールズ))というプロジェクトに関わったのがきっかけでした。有機栽培の技術や理論をいくつかの先生方から学び、「これは面白い」と思えたんです。特に影響を受けたのが小祝政明さんの「BLOF理論」です。
--- 「BLOF理論」について詳しく教えてください。
豊増:簡単に言えば、有機栽培を「科学的に捉えるための基本理論」です。これまでは、有機栽培の中にも流派のようなものがあり、考え方がバラバラでしたが、「BLOF理論」は有機栽培に関わる多くの生産者に共通言語を与えました。微生物が作り出す水溶性炭水化物の量をいかに土壌中に増やすか、という視点で考えると、土の中にもう一つ“太陽”を作るような営みが必要になるんです。
--- 有機栽培のどういった点に魅力を感じていますか?
豊増:一番は「理にかなっている」ことですね。地域資源を活かす発想や、自然の仕組みを理解して組み立てていく感覚。たとえば海苔の粉末を肥料に使ったり、落ち葉やもみ殻などを活かして炭素を循環させたり。畑の周辺にあるものが、すべて資源に見えてくる。まるで“パズル”のように農業を組み立てていける面白さがあります。
--- 有機栽培を「普及したい」とは思っていない、ともおっしゃっていましたね。
豊増:そうなんです。誤解を恐れずにいうと、僕は「楽しいからやっている」だけです。矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、仲間が増えたら嬉しいんだけども、普及活動をしたいわけじゃない。そんな感覚です。有機栽培を追求しているけれど、それを他人に押しつけようとは思っていません。みんながそれぞれのテーマで、自分なりの“実験”をしているのだと思います。
だから、有機栽培は「サステナブル」と言われることもありますが、私自身はあまりしっくりきていないんです。持続可能というよりは、“自分が試してみたいことを実験している”という感覚に近い。僕の農業は、社会のためでも環境のためでもなく、自分自身の問いに答えを出すための手段です。だから「サステナブルな農業をやっている」とは思っていません。
--- 有機栽培で育てた野菜は、具体的にどのような違いがありますか?
豊増:たとえば人参は「香りが強い」とよく言われます。ピーマンも苦味がしっかりあるけど嫌な苦味じゃない。それぞれの野菜が本来持っている“個性”がドストレートに出ている感じです。香りも、歯ごたえも、色の発色も全然違う、一口食べたら驚くほどの味です。
--- 味の違いには理屈があるのでしょうか?
豊増:あります。炭水化物やアミノ酸の量が違うはずです。有機栽培は土の中に炭水化物が豊富に蓄えられるような環境をつくるので、野菜の味も濃くなる。光合成で生まれたエネルギーがしっかり野菜の中に蓄積されるから、うまみや香り、歯ごたえに差が出ます。逆に、乾燥が続きすぎるとそのバランスが崩れてしまい、苦味成分が増えるリスクもある。だからこそ、天候の変化にも敏感になりますね。

消費者と「一緒に旅をする」感覚で届けたい
--- 消費者の皆様に対し、有機栽培の価値をどう伝えていきたいとお考えですか?
豊増:有機栽培の価値を理解してもらいたいと強く思っているわけではありません。ただ、美味しかったら「美味しかった」と言ってもらえれば、それが一番嬉しいんです。例えば、スーパーで一番高い198円の人参を買って、「高かったけど美味しかった」と感じてもらえたらそれでいいんです。
--- "応援してください"というメッセージではないのですね。
豊増:そうですね。僕は「応援してください」じゃなくて、「一緒に旅に出ましょうよ」っていうスタンスです。僕らが目指してるのは、遠くにある楽しい目的地。その旅に一緒に付き合ってくれたら嬉しいし、「なんか楽しそうだから一緒に行ってみようかな」って思ってもらえるような存在でいたいです。
--- 最後に、「ちばびお」等の商品を通じて消費者の皆様へメッセージをお願いします。
豊増:農家が作った野菜を食べる。それだけで農業の“プレイヤー”になってるんです。応援席にいるんじゃなくて、実は一緒にピッチに立っている存在です。だから「美味しかった」って一言、売り場でつぶやいてもらえるだけで、次の農業が変わるんですよ。応援しようとしなくても、もうあなたは仲間なんです!
--- 有機栽培を新しい視点で捉えるきっかけになりました。ありがとうございました!
編集後記
石井食品では、ONE DROP FARMのような生産者の皆様との密な繋がりを持った素材価値開発部のメンバーが全国で活躍しています。これまでに培った繋がりをもとに、生産者のためになるのであれば、石井食品との取引とは関係がなくても、新たな取引先の開拓をお手伝いしたこともありました。
生産者も含め、短期的な利益ではなく、持続可能な食品の生産を考えた活動を今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ