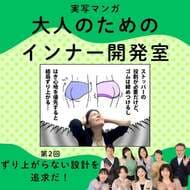石井食品は、今でこそミートボールでお馴染みですが、昭和45年に創業し、46年に「佃煮」の会社として始まっています。佃煮で培った煮物の技術を活かして生産した「栗ごはんの素」も好評いただいています。その年に採れた「新栗」だけを使ってつくるこだわりの商品です。
石井食品は、今でこそミートボールでお馴染みですが、昭和45年に創業し、46年に「佃煮」の会社として始まっています。佃煮で培った煮物の技術を活かして生産した「栗ごはんの素」も好評いただいています。その年に採れた「新栗」だけを使ってつくるこだわりの商品です。
今回は、今年の「栗ごはんの素」の生産にご協力いただいている栗農家の大槻さん、そして栗プロジェクトのリーダーであり、石井食品の原材料を担う「素材価値開発部」の夛田・行政、そして同部署の田久保に話を聞きました。「地域と旬」のスローガンのもと、生産者と直接向き合いながら、地域と一緒に新たな価値をつくる挑戦。その現状と未来を探ります。
まずは、現場で見えている課題から探ります。
農家の現場から見える“課題”
— 今年もご協力ありがとうございます。栗の栽培において大変なことは何でしょうか?
大槻さん:栗栽培で一番大変なのは、草刈り、栗拾い、そして枝の剪定です。特に剪定は1〜3月の3か月間、毎日ずっと続きます。虫の卵を見つけて防除するのも大切な作業です。最近はドローンを導入して消毒作業を効率化していますが、やはり手作業も欠かせません。
さらに、ここ3年は、空梅雨(からつゆ)で雨が十分に降らず、受粉もうまくいかない時期が続いています。栗は根が浅いため水を吸い上げにくく、干ばつに大変弱い植物なんです。水不足が続けば、収量も大きく落ちてしまいます。

— そんな中でも、品種の工夫をされていると聞きました。
大槻さん:うちでは約10種類の品種を育てています。早生、中生、晩生を組み合わせることでリスク分散をしつつ、収穫時期を長くしているんです。なかでも「倉片」という小粒の品種は黄色い果肉が特徴で、保存すると甘みが増し、消毒しなくても育ちます。石井食品さんにも「無着色でも色がきれい」と評価いただいています。

地域とのつながりから生まれる、栗の新たな可能性
— 今年の栗プロジェクトはどこが進化しましたか?
行政:最近では持続可能な生産ができるよう、農家さんと直接交渉をして、栗を調達する地域を増やす取り組みをしています。たとえば茨城県石岡市や熊本県和水町の農家さんから直接購入するなど、顔の見える関係をつくっています。
夛田:農家さんと直接つながると、農作物に関するフィードバックがしやすいんです。「今年の栗はこうだった」「来年はこうしてみたらどうだろう」といった、具体的な相談ができます。生産者にとっては品質改善のヒントになるとお声をいただいています。また、石井食品にとっても持続可能な調達につなげるための強固な関係性作りにつながります。
行政:ただ、国内の栗の生産者は年々減少しています。今後も栗の商品をお届けするためには、中長期的な視点で農家さんと信頼関係を築いていくことが欠かせません。

栗農家の皆さんと一緒に
商品にならなかった栗に、もう一度スポットライトを
夛田:そんな中長期的な施策の一つとして、今期からは栗をペースト状に加工し、別の商品として展開する試みを始めました。これまで、味は美味しくても見た目の基準を満たせず商品化できない栗がどうしても出てしまっていました。その栗を生かす方法を見出したいと考えました。
行政:残念な言葉ですが、従来は「シミ栗(染み栗)」と呼ばれていたんです。それを価値ある商品に変えていく。また、生栗からペーストをつくる仕組みを整えれば、栗ごはんや栗きんとんを生産する際には取り除いていた渋皮も有効活用できます。栗は皮の割合が大きく、通常は重量の60〜65%が食べない部分として廃棄されてしまう農作物です。しかし、ペーストにすることで渋皮まで活かすことができ、より栗本来の風味を感じられる栗ペーストが完成しました。その結果、廃棄率もこれまでより約10%改善する見込みです。
夛田:また、ペーストにすれば、モンブランのようなスイーツにも展開できます。小ロットでもお取引ができるような体制を整え、生産されている地域のお菓子店等とも繋がりをつくりながら、多様な商品展開を検討したいと考えています。
社内の“栗剥きプロジェクト”がもたらした変化
— 「栗ごはんの素」と言えば、手剥きの栗が特長です。今年はこの「栗剥き」の工程でも進化があったとか。
行政:石井食品では、栗の皮剥きに機械を用いながらも、最終的な仕上がりは人の手で、一つひとつ丁寧に確認しています。しかし、この作業は非常に力も技術も必要な作業でした。
夛田:そこで、これまで栗の時期だけ短期スタッフの方に頼っていた栗剥きの工程を改善するため、思い切って栗剥き作業の「固定メンバー制」を取り入れてみました。剥く手順や刃物の使い方といった一つひとつの工程も、皆で教え合ってどんどん上達しています。
1kgを何分で剥けるかタイマーで計測する等、専門チームの熟達度合いを測っています。開始から2週間で、かなりスピードも上がり、生産性向上につながっています。
行政:タイマー片手に「今のペースいいね」「あと何キロいけるかな」って、励ましあいながらやることで、工場の雰囲気もすごく良くなりましたね。今までは「栗=農家さんとの関係」ばかりに注目してたのが本音です。しかし、社内の生産体制もすごく重要だということに気づきました。社内にもちゃんと目を向け、改善していこうというのが、今の私たちのスタンスです。

石井食品が担う“架け橋”の役割
田久保:私は元々、石井食品の取引先として百貨店で働いていました。その際「無添加調理を取り入れ、生産者の思いが見える食品をつくる会社」であることに感銘を受け、とうとう転職してしまいました。今は生産者の声を集め、消費者へ届ける役割を担っています。
生産者から消費者へ、消費者から生産者へ。この両方の声をつなぐのが石井食品の強みです。大槻さんも「栗を市場に出したら終わり」ではなく、「お客様からのフィードバックが返ってくること」に、石井食品との取引の価値を感じてくださっています。
「日本全国の農家が手間ひまかけて育てた食材を“イシイに出したい”と思う──そんな会社にしたい。」
それが私のビジョンです。
栗ごはんのある暮らしを、次の世代にも残したい
— 改めて皆さんの栗プロジェクトに対する思いを教えてください。
夛田:栗ごはんって、ご家庭で作るとしたらすごく贅沢で手間のかかる料理ですよね。だからこそ、季節の訪れを感じられる特別な食べ物だと思うんです。
行政:最近では黄色い甘露煮で作った栗ごはんも多く売られています。しかし、砂糖の甘さで誤魔化さない本物の栗を使って作られる炊き込みごはんは、旬を感じる文化としてなんとか残していきたいです。栗のシーズンはお米の収穫シーズンとも重なっているので、季節感もより伝わる商品だと思います。
田久保:石井食品の栗は、石井食品の強みであるお正月の栗きんとんやおせちでも使われます。でも、それだけにはとどまらず、栗の新しい食べ方も探っていきたい。営業チームからも「栗プロジェクトをもっと盛り上げたい」という声が上がってきているので、ここからが栗プロジェクトの本当のスタートだと思っています。
大槻さん:消費者の声を直接聞けることが一番の励みです。遠方にも「また食べたい」と言ってくださるお客さまがいる。その期待に応えられる栗を、家族と一緒にこれからもつくり続けたいと思っています。

編集後記
石井食品が栗に向き合う姿勢は、まさに「地域と旬」のスローガンへの姿勢そのものです。生産者の皆様との関係、社内の改善、そして商品そのものの改善。すべてに真正面から取り組むその姿勢で、これからも持続可能な商品開発の体制を築いてまいります。
プロフィール
大槻敏之(大槻栗園)
行政翔平(石井食品)
2019年入社。顧客サービス部(営業)を経て、2024年より素材価値開発部の地域プロデュースグループ 地域コミュニケーションチームへ。”地域と旬”の食材と生産者を探しつつ、食材と商品を通して、地域に貢献する形を作り、地域と食卓をつなぐ調整役を担う。
夛田英梨奈(石井食品)
2019年入社。学生時代を北海道で送り、生産者と距離が近い仕事を求め、石井食品に入社。地域プロデュースグループ 素材加工研究チーム所属。現在は“地域と旬”の食材を活かした商品をお客様にお届けするべく、各地域の野菜や果物のペースト加工開発を行っている。
田久保圭(石井食品)
2022年入社。顧客サービス部(営業)、本社1階ヴィリジアン(直売店)を経て、2025年より素材価値開発部の地域プロデュースグループ地域コミュニケーションチームへ。前職は百貨店で小売業を行っており、そこで出会った石井の商品に魅力を感じ、地域と旬の取り組みを本気でやっていることが分かり、生産者と消費者をつなぐ活動を行っている。
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ