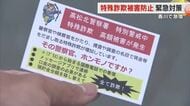聴覚障害者のスポーツの国際大会、「デフリンピック」の開幕まであと2カ月。日本で初めて東京で開催されるデフリンピックの意義を深掘りします。
日本選手団は過去最多の273人 100周年を迎える「デフリンピック」世界の頂点目指す岡山・香川ゆかりの選手
耳がきこえない・きこえにくい人のためのスポーツの国際大会「デフリンピック」。その歴史はパラリンピックより長く、1924年にフランスのパリで第1回大会が開催されたのが始まりです。
4年に1度開かれ2025年で100周年を迎える今大会には、70以上の国と地域から約3000人の選手が参加します。競技は陸上やバドミントン、ボウリングなど21競技が実施されます。日本選手団は過去最多の273人で挑みます。
岡山・香川からはデフ陸上男子400メートルハードルの石本龍一朗選手、デフバドミントンの片山結愛選手など4人の選手とデフボウリング女子、安田由紀子監督が世界の頂点を目指します。
参加資格は「通常の会話が聞こえないレベルの聴力」健常者にも分かりやすい競技上の工夫を紹介
デフリンピックのルールは、オリンピックとあまり変わりませんが、普段付けている補聴器や人工内耳は外さなければなりません。通常の会話が聞こえないレベルの聴力であることが参加資格となります。
そのため、会場では様々な工夫がされています。例えば、陸上。
(佐藤理子アナウンサー)
「デフ陸上の選手は音だけではなく、こちらのスタートランプの光を見て一斉に走り出します」
こちらがスタートランプ。「位置について、用意、スタート」と光で示されます。また、フライングは白いランプが点滅するなど観客にもわかりやすいよう工夫されています。
全国各地を巡る「デフリンピック」PRキャラバンカー 岡山県庁で活躍誓う地元ゆかりの選手
応援も手話を使って行われます。
(佐藤理子アナウンサー)
「デフリンピックをPRするために全国各地を巡るキャラバンカーが県庁に到着しました」
8月26日から30日にかけて岡山にやってきたキャラバン。デフリンピック日本代表の陸上男子走り高跳びの佐藤秀祐選手、サッカー女子の小森彩耶選手、ボウリング女子の安田監督も駆け付け大会での活躍を誓いました。
(デフサッカー女子 小森彩耶選手)
「デフリンピック100周年の大会が日本で開催される貴重な機会なので優勝したい」
各国の聞こえない人と「国際手話」 振動で伝える目覚まし時計…“聞こえない生活”の理解に向けろう者の日常を体験
この日は、浅口市でイベントです。デフリンピックにまつわるクイズで会場も盛り上がりました。
〇正解に喜ぶ参加者
またこちらでは・・・
〇国際手話を教える安田監督
訪れた人が体験したのはろう者が普段使用している手話と「国際手話」です。話し言葉と同じように国によって手話表現が異なるため、国際交流の場では国際手話という共通語が使われています。
(体験した人は…)
「おもしろい。いろんな国の聞こえない人と話す機会は(普段)ないので、この機会に話をしてみたい」
「いろいろ覚えた単語を使って交流ができればいいなと思う」
ほかにも、音の代わりに振動で伝える目覚まし時計など、ろう者の日常を体験できるコーナーなどもあり、会場は多くの人でにぎわいました。
(備南聴覚障がい者協会 川相真由美事務局長)
「音がないと命に関わることもある。コミュニケーションが難しいため孤立しやすいので、皆さんに聞こえない生活を理解してほしい。(特に)若い人にはろう者のことを理解してもらい一緒に社会をつくっていけたら」
このキャラバンカーは岡山県内6カ所を巡りました。キャラバンを通じて、応援の輪も少しずつ広がっています。
「デフリンピック」は聴覚障害者と健聴者が互いを深く知るきっかけになる可能性も
デフリンピックについて自身もろう者であり、ろう者や難聴者の生き方や考え方を調査、研究する筑波技術大学の大杉豊教授は、聴覚障害者と健聴者が互いのことを深く知る、大きなきっかけになると話しています。
(筑波技術大学 大杉豊教授)
「聞こえない、聞こえにくい人たちに対する理解や手話言語に対する理解がますます広がっていくとてもいい機会になったと思う。バレーボールの試合をする場所では非常時に点滅するランプがついて、聞こえない人への情報保障が盛り込まれていた。デフリンピックのために新しく設置したと説明を受けた。とてもいい例だと思う」
聞こえない、聞こえにくい人と聞こえる人が助け合い理解しあう。デフリンピックがそうしたきっかけになるかもしれません。
東京デフリンピックは11月15日に開幕します。一緒に応援しましょう。