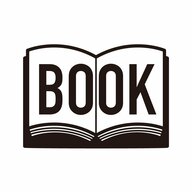だからこそ今問われているのは、制度の強化そのものではなく、その強化を誰がどこまで支えられるのかという、インフラ管理の持続性の問題なのです。
八潮は未来の予兆だったのか
事故発生は突然に見えて、実は時間をかけて進行していた──。八潮市で起きた下水道の陥没事故は、まさにそうした性質のものでした。管路そのものは、法定耐用年数である50年には達していませんでした。
定められた制度に沿って点検も行われており、評価は「Ⅱ(中度)」──すぐに補修が必要とされる状態ではなかったのです。それでも、地中では腐食が進行し、地盤との相互作用によって土砂が流れ込み、ある日突然、大きな穴として地表に現れました。
これは、下水道事故の新しい位相(いそう)を象徴しています。単に「老朽化していたから」ではなく、制度の対象から漏れがちな複合的なリスクが重なった結果として、事故は起きたのです。そしてこの構図は、決して八潮市だけの特殊事例ではありません。
都市の地下には、いまも数十万キロに及ぶ下水道管が張り巡らされ、その多くは高度経済成長期以降に整備されたものです。地上の風景は変わっても、地中のインフラは更新の機会を得られないまま、少しずつ劣化を進めています。
地盤が弱く、気候が変動し、地下が複雑化する中で、事故の条件は全国各地で静かに積み上がりつつあります。制度は整備されつつあります。点検の頻度も、判断基準も、以前よりは明確になってきました。
“足りない”状態が各地で
けれども、整備された制度がすべてをカバーできるわけではありません。人手が足りない、予算がつかない、情報が足りない──そうした理由で「わかっていてもできない」状態が、各地に広がっています。
八潮で起きたことは、むしろ制度がきちんと機能しているとされた地域で起きた事故でした。その意味で、この出来事は私たちに問いを突きつけています。
制度は、どこまで私たちの暮らしを守れるのか。制度に「頼る」だけでなく、自らの足元に潜むリスクを「見つめる」覚悟が、いま必要なのではないか──と。
八潮は未来の予兆だったのか。それとも、まだ選び直せる岐路なのか。この問いにどう向き合うかが、これからの下水道行政と都市インフラの在り方を左右していくはずです。
こうした地下のインフラが劣化し続ける一方で、その管理や整備の枠組みそのものにも、大きな盲点が存在しています。とくに、1つの自治体では対応しきれない規模で構築されてきた「流域下水道」は、その典型例と言えるかもしれません。
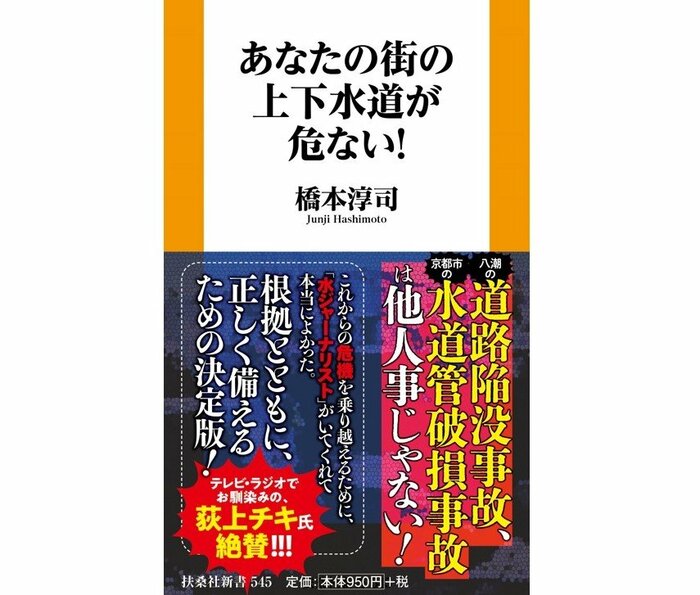
橋本淳司
1967年群馬県生まれ。アクアスフィア・水教育研究所代表、武蔵野大学工学部サステナビリティ学科客員教授。著書に『水辺のワンダー~世界を歩いて未来を考えた』(文研出版)、『水道民営化で水はどうなる』(岩波書店)、『67億人の水』(日本経済新聞出版社)、『日本の地下水が危ない』(幻冬舎新書)、『100年後の水を守る~水ジャーナリストの20年』(文研出版)、『2040 水の未来予測』(産業編集センター)など多数