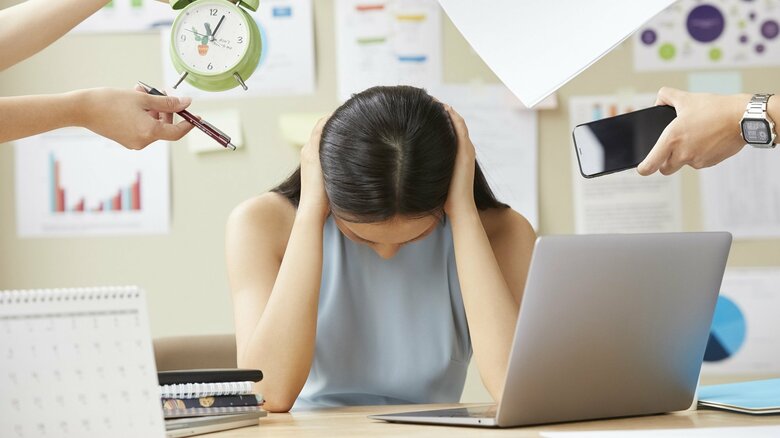一番手っ取り早いのはフィジカル面のリラクゼーションです。ジョギングをしたり、泳いだり。ウォーキングの場合は、早足でしっかりかかとから踏み出すように歩くのがコツです。ヨガや岩盤浴などもよいでしょう。
最も大事なのは睡眠です。ただ、ストレスが蓄積している人は持続的な緊張のために入眠しづらく、熟睡しにくいことがあるので、寝床に入る2時間前から、眠りのスイッチを入れるための入眠儀式を取り入れましょう。アロマテラピーを試したり、リラックス効果のある音楽を聞いたりするのもおすすめです。
また、睡眠はリズムが大切なので日々の寝起きの時間を一定にすることも求められます。仕事が溜まっていても、時間が来たらスパッと切り上げて入眠儀式に入る。しっかり体内時計を整えることが大事です。それでもだめならば、睡眠薬を使うのも一案ですが、その前に入眠儀式から試してみてください。

他にも、思いっきり遊んだり、興奮するほど楽しいことをすることも効果を期待できるでしょう。ストレスによる持続的な緊張を中断して、楽しい、嬉しい、感動する、心が安らぐといったエモーショナルな体験を織り込むのです。
毎日、パソコンの前で一生懸命仕事をしている人も、時々、美術館に行って絵画を眺める、プールに入って水にプカプカ浮いて「気持ちいいな」と感じてみる。そういう時間が織り込まれることが必要なのです。
まじめでがんばり屋の人ほど、知らずのうちに無理をしやすく、休むことを悪だと捉えてしまいがちです。こうした人たちはそもそもストレスが蓄積していると自覚すること自体、苦手な傾向にあります。だからこそ、肩こりや頭痛など、ちょっとした不調は体からのサインだと認識してください。病気に至る前に踏み止まるためにも、ぜひストレスマネジメントを習慣にしてほしいと思います。
森下克也(もりした・かつや)
心療内科医、医学博士、もりしたクリニック院長。著書に『もし、部下が適応障害になったら』『うちの子が「朝、起きられない」にはワケがある 親子で治す起立性調節障害』(CCCメディアハウス)など多数。
構成=高木さおり