国際卓越研究大学の第2回公募に、東京大学や京都大学など8大学が応募した。認定されれば多額の助成が受けられる一方で、準備や報告業務の負担が重いとの声もある。
専門家は、大学教員の研究時間が削られる構造に、制度的な問題があると警鐘を鳴らす。
国際卓越研究大学に8大学が申請
国が10兆円規模の基金で支援する国際卓越研究大学の2回目の公募に、東京大学など8つの大学が申請した。
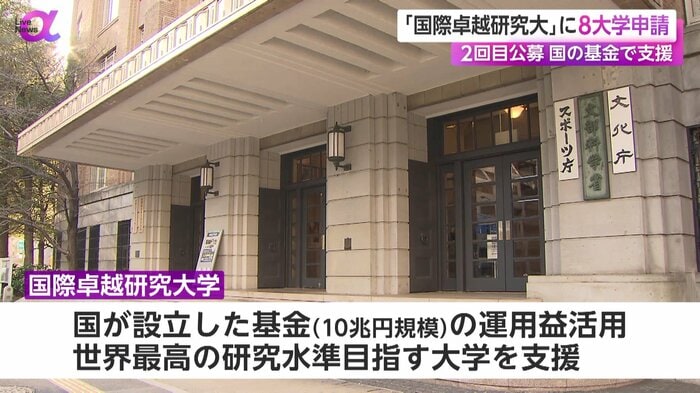
国際卓越研究大学は、日本の研究力低下を受けて導入されたもので、国が設立した10兆円規模の基金の運用益を活用して、世界最高の研究水準を目指す大学を支援する。
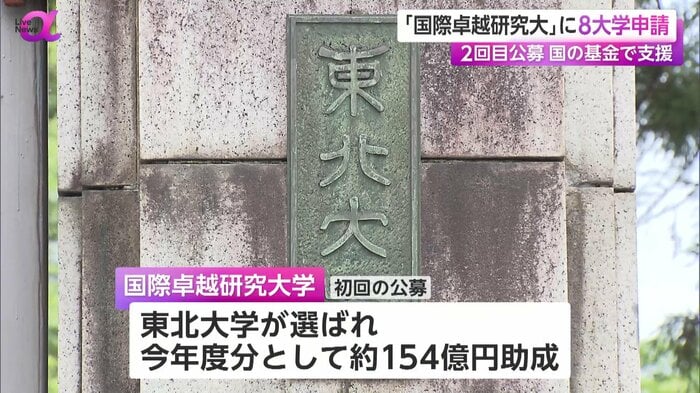
初回の公募では東北大学が選ばれ、今年度分として約154億円が助成されている。

16日までに行われた2回目の公募には、受付順に、大阪大学、京都大学、早稲田大学、東京大学、九州大学、東京科学大学、筑波大学、名古屋大学の8大学が申請した。
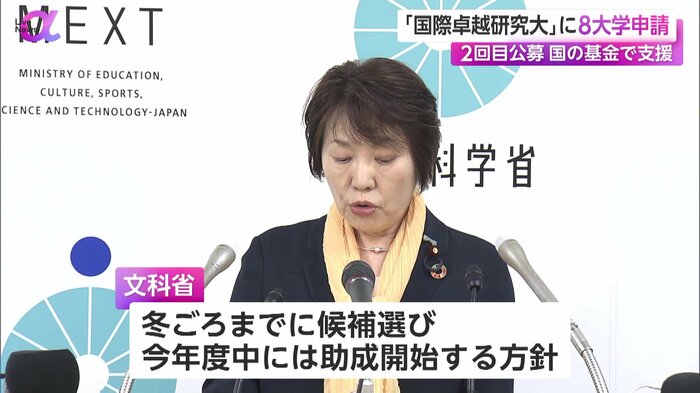
文部科学省は専門家らによる有識者会議を設置して、6月から審査を始め冬頃までに候補を選び、今年度中には助成を開始する方針だ。
研究資金と引き換えに大学教員の負担が拡大
「Live News α」では、津田塾大学教授の萱野稔人さんに話を聞いた。
堤礼実キャスター:
大学で研究教育に携わる萱野さんは、どうご覧になりますか?

津田塾大学教授・萱野稔人さん:
この助成金は、公募要領などの資料を読むと分かるんですが、多くの要件を大学に求めているため、申請するだけでもとても大変なんです。
今回申請した各大学は、申請するためにどれくらいの会議を開き、どれくらいの教職員を動員したのか、おそらく、申請準備のために研究時間を削らなければならなかった教員や、仕事量が増えた職員が相当いるんじゃないでしょうか。
堤キャスター:
その分、研究や教育などにしわ寄せが行ってしまうというようなことはあるんでしょうか?
津田塾大学教授・萱野稔人さん:
もちろんあります。もし国際卓越研究大学に認定されたとしても、それで大学の業務は終わりではないです。その後も進捗状況を報告し、評価を受けるために、教職員は多くの業務をこなさなければなりません。
つまり、大学は助成金を配分してもらうために、ますます忙しくなり、大学教員の研究時間も減少する。そんな構図がここにはあります。
申請しなければ評価に影響…大学は選択の余地なし
堤キャスター:
ただ、国際卓越研究大学に選ばれると、潤沢な研究資金が得られるようですね?

津田塾大学教授・萱野稔人さん:
確かに、大学が使えるお金は増えるでしょう。しかし、そのお金を使うために求められる業務が増えることで、腰を落ち着けて研究する時間はその分だけ減ってしまいます。
これで本当に、大学の研究力を高めることになるのかどうか。だからといって、大学は大変なら公募に申請しなければいいんじゃないか、とはなりません。
堤キャスター:
それは、どうしてなんでしょうか?

津田塾大学教授・萱野稔人さん:
今回申請したのは、日本を代表する大学ばかりです。もし申請しなければ、文科省がせっかく作った「国際卓越研究大学に認定されるつもりのない大学」という評価を受けてしまいかねません。
実は同じような構図は、他の大学政策にもよく見られます。私の知っている限り、10~20年前と比べて研究時間が増えたとか、腰を落ち着けて研究できるようになったという研究者は皆無です。
文科省は新しい事業を次々と大学に求めることで、文科省自身が、日本の大学の研究力を削いでしまっているという可能性があるという現実を、もっと直視してほしいと思います。
(「Live News α」5月20日放送分より)





