負荷が上がりすぎた管理職ポジションは、女性にとって「罰ゲーム」を超えた「無理ゲー」になり、逆に男性にとっては「覚悟を決めて挑む」そう簡単には「降りられないもの」となっていきます。
こうして、管理職への男女の意欲の差は入社後に徐々に大きくなっていきます。「女性に意欲が無い」問題の背景には、このような意欲差を生んでしまう構造が厳然と存在しているのです。
ロールモデルの少なさに苦戦
女性は管理職になったあとも、女性ならではの苦労に苛まれることが多くあります。管理職と、家庭の家事育児の両立に苦労する声は圧倒的に女性から多く聞かれますし、社内でも女性のロールモデルがいないことでやりにくさを感じています。
実際の声を紹介しましょう。
「女性の管理職者がほとんどいなくて、周囲の目が気になっていた。特に男性社員から蔑視(比較)されることが多々あるため、仕事のやりにくさを感じる」(48歳、女性、卸・小売業)
「女性として、家庭と仕事のバランスを保って維持するのが大変である」(41歳、女性、金融・保険業)
逆説的に言えば、「罰ゲーム化」してもまだ管理職のなり手が現れてきているのは、日本社会に残っているこうした大きなジェンダー・ギャップのおかげだ、という言い方もできます。
つまり、性別役割分業意識を背景に、仕事を通じて女性にモテたり、妻子を経済的に支えようとする、マッチョで男性的な規範があることによって、たとえ管理職が「罰ゲーム化」しても、「大変だが、やってみよう」と覚悟を決めていく男性が現れてくれるからです。
男性にもいつまでも期待はできない
しかし、ここまで述べてきたように管理職が「徐々に大変になっているのに、報われない」ポストになっていることを考えれば、男性にいつまでも期待はできません。
いまや「趣味のサーフィンのために海沿いに家を買うので、マネジャーにはなりません」「副業で稼いでいるので、会社で管理職なんて絶対にやらない」と言い切る男性が、続々と現れてきています。
「男性なら会社での昇進を目指すのが当たり前」という意識も薄れていっています。
これからより一層ジェンダー・ギャップが埋まり、「罰ゲーム」に「覚悟」を決める男性が少なくなっていくとき、管理職の次のなり手は現れるでしょうか。
そのとき、会社は女性側に「覚悟」を求めるのでしょうか。
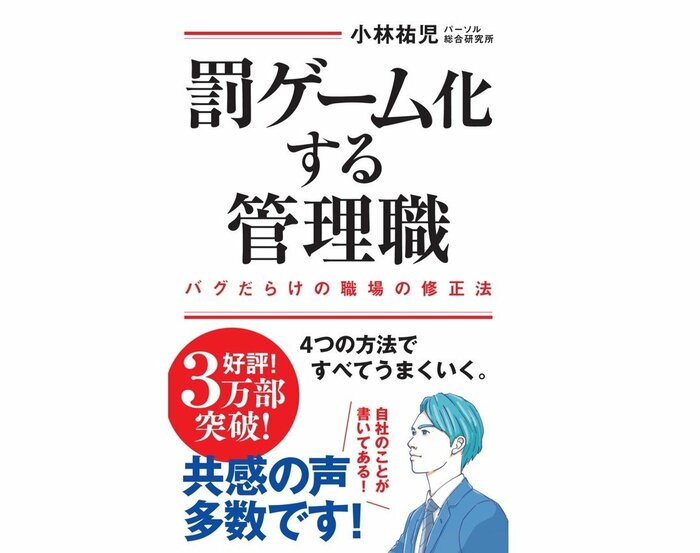
小林祐児
パーソル総合研究所主席研究員/執行役員 シンクタンク本部長。労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行っている。専門分野は人的資源管理論・理論社会学。
(※1)山田昌弘、2016、『モテる構造-男と女の社会学』、筑摩書房






