プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績、伝説を德光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る!
軟式野球からドラフト外でプロ入りした異色の経歴ながら、通算148勝138セーブをあげた大野豊氏。“7色の変化球”と呼ばれた多彩な球種でバッターを翻弄し、最優秀防御率2回、沢村賞1回、最優秀救援投手1回。広島カープ一筋22年で3度の日本一と5度のリーグ優勝に貢献した“広島カープのレジェンド”に徳光和夫が切り込んだ。
【前編からの続き】
「憧れの人」江夏豊氏と運命の出会い
大野氏がプロ2年目だった1978年シーズン、球界を代表する大投手・江夏豊氏が南海(現・ソフトバンク)から金銭トレードで広島に移籍してくる。
徳光:
この番組では人との出会いについて、皆さん、よく言われるんですけど、まさに大野さんが師匠と呼ぶ江夏さんが来られたのが、その翌年ですよね。
大野:
江夏さんとの出会いのタイミングが良かったですね。やっぱり出会いとタイミングは非常に重要ですよね。
徳光:
ですよね。
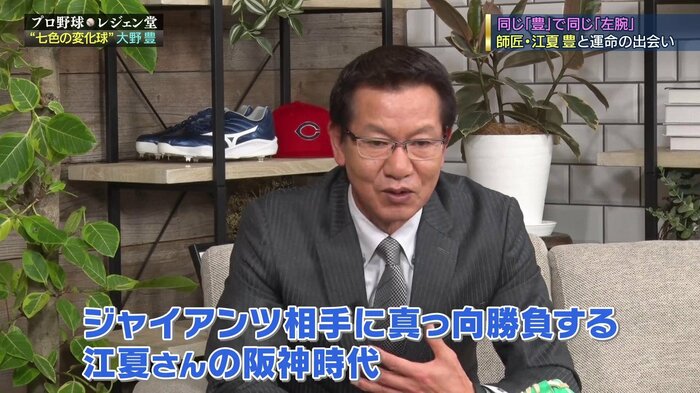
大野:
僕はジャイアンツを相手に真っ向勝負する阪神時代の江夏さんにすごく憧れてたんです。その証拠に、僕は社会人時代に背番号28(江夏氏の阪神時代の背番号)を付けていて、キャッチャーが22(田淵幸一氏の背番号)で「江夏・田淵のバッテリーだ」ってやったくらいですから。
徳光:
そうなんだ。へぇ(笑)。

大野:
そういう方がまさか広島に来られると思わないし、広島に来られても雲の上の人で、全く繋がりがないじゃないですか。でも当時の監督、古葉(竹識)さんが、「同じ『豊』で同じ左でこういうピッチャーがいるから、江夏、ちょっと見てくれ」ということを言ってくださって、2年目のキャンプからずっと、江夏さんとキャッチボールをして、ブルペンでも見ていただいたんです。これはすごく刺激になりましたよね。
徳光:
具体的に学んだことって何ですか。

大野:
まずはフォームを変えられましたね。僕は投げるときにボールを持つ左手がいったんお尻、腰の後ろに入るじゃないですか。そのときに右手は天井を向いている感じだったんです。「まず、そこを変えなさい」と。「もうちょっと右手を下げて、目標を脇の下から見るんじゃなくて、肩のラインから目標を見る感じで」。
徳光:
相手打者を?
大野:
はい。相手打者を。僕は個性のある独特なフォームでしたからね。左手がまずお尻の後ろに入る。こうしないと投げられないんです。
徳光:
そうなんだ。それは軟球時代もそうだったんですか。

大野:
ずっとそうです。そうやってお尻の後ろに手を入れる分、どこでタイミングを取るか、どこで上半身と下半身を合わせるかと言ったら、軸足(左足)しかないんです。となると、軸足が浅かったらトップは取れない。手が上がってこないじゃないですか。軸足の重心を下げてタイミングを合わせて投げる。そういうフォームになったんですよね。
右足を上げますよね。それで、軸足を低くして、左手をお尻の後ろでためる。そこから一気に投げる。僕は常にこういう投げ方です。下半身に体の強さがあったからこそ、このフォームで投げられたし、長くできたと僕は思いますよね。
徳光:
そういう意味ではお母さんにも感謝ですね。
大野:
そうですね。
江夏豊氏の鉄拳制裁
徳光:
江夏さんは本当にキャッチボールを大切にしましたよね。
大野:
キャッチボールは非常にうるさく言われましたね。キャッチボールができなくて鉄拳を食らってますからね。
徳光:
そうなんですか。
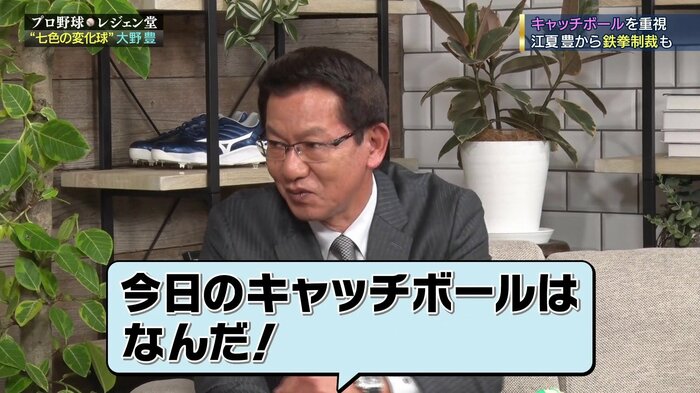
大野:
僕はちょっと肘の状態が悪かったんです。それでキャッチボールをしてたんですけど、江夏さんはお腹が出ているじゃないですか。だから、ジャンプもなかなかできないし低いボールも捕れない。なのに、僕がそんなボールばっかり投げたんです。そしたら、どんどん機嫌が悪くなっちゃって。キャッチボールが終わった後に「神宮のベンチ裏に来い」って言われて。「今日のキャッチボールは何なんだ!」って殴られました。「すみません!」ですよ。
でも、僕は嬉しかったです。「それだけ、自分のことを見てくれて、思ってくれて、やってくれたんだな」と思いました。だから、江夏さんにそんなことをさせるようなことをしちゃいけない、キャッチボールもしっかりしなきゃいけないということを、改めてつくづく教わりましたね。
徳光:
鉄拳制裁が生きたってことですね。
足が震えた“世界の王”の目力
徳光:
左投手として対峙する打者の中では、当時はやっぱり王さんが最高だったと思うんですけども…。
大野:
そうですね。
徳光:
王さんとの対決はどうでした。
大野:
僕はそれまでテレビで見る王さんしか知らなかったんですけど、先輩方に「王さんの目を見るなよ」と何度も言われたんです。「目を見るな」って言われても、マウンドに立って、セットに入って顔を見たときに、絶対目と目が合うじゃないですか。
後楽園球場で満塁のときに、初めて王さんと対戦したんですよ。セットに入って、パッと見たときに目と目があったんです。
徳光:
ええ。

大野:
そしたら、足がガタガタガタッて震えたんですよ。それはなんて言うか、王さんの眼力、目力ですね。「この人はやっぱり“世界の王”だな」と。勝負をする前から相手ピッチャーを目で威圧して、少しでも自分が有利なほうに持ってくる。それだけの力が目にある人でしたね。
徳光:
その初対戦のときは結局どうだったんですか。
大野:
そのときはセカンドゴロでした。ただ、僕はそういう王さんと対戦できて本当に良かったと思いますね。それを若いときに経験したから、目力の少々強い人でも動揺しなくなりました。
徳光:
なるほど。
大野:
かえってこちらのほうが睨み返してやろうと。
徳光:
(笑)。
2年目に防御率が「36分の1」に
大野氏は2年目から一軍に定着。主にリリーフとして41試合に登板し3勝1敗、防御率3.77の成績を残した。シーズン最後の試合ではヤクルト戦に先発登板、2安打に抑えて見事プロ初完封を飾った。
大野:
あの当時は130試合だったんですよね。129試合目に僕はリリーフで投げているんです。マニエルに満塁ホームランを打たれたんです。当然ガックリきますよね。それで落ち込んでいると、次の日、球場に行ったら古葉監督に「おい、大野。今日おまえが先発だ」って言われて、「えっ」。
徳光:
そんなことあるんですか。
大野:
結局そこで完封ですよ。当時、ヤクルトが開幕から129試合連続得点を続けていたんですよ。その記録も止めたんです。

徳光:
2年目の防御率は3.77、初年度の防御率は参考になるかどうか分かりませんけど135.00。36分の1になりましたね(笑)。
大野:
ただ、この時期も古葉さんによく怒られましたよ。結局点を取られるパターンというのは、フォアボールから自分で不利な状況を作って失点するケースが多かったんですよ。古葉さんには「お前は同じ失敗ばっかり繰り返して」ってガンッて蹴られたりとかね。
徳光:
古葉さん、そんなことをするんですか。
大野:
古葉さんは温厚そうで、すごく気が短かった。でも、「私はそんなことはやっておりません」。最後までそれを認められませんでした(笑)。
ベンチから見ていた「江夏の21球」
プロ3年目の大野氏は主に中継ぎとしてリーグ最多の58試合に登板。5勝5敗2セーブ、防御率3.86の成績で、広島の4年ぶり2度目のリーグ優勝、初の日本一に貢献した。
大野:
ここで何が一番嬉しかったかというと、やっぱりリーグ優勝して日本一になったことですね。
徳光:
まさに師匠の活躍があったわけですよね。
大野:
もう江夏さんなくしては語れないです。
徳光:
日本シリーズではあの“21球”を目の当たりにしたわけですもんね。

1979年、広島と近鉄の日本シリーズ第7戦でプロ野球史に残るドラマが起きた。広島は4対3でリードしていた7回裏から絶対的リリーフエース・江夏氏をマウンドにおくる。しかし、1点リードのまま迎えた9回裏に江夏氏は無死満塁のピンチを背負ってしまう。まずは三振でアウトを取り一死満塁となったところで1番打者・石渡茂氏がスクイズ。その瞬間、江夏氏、水沼四郎氏のバッテリーがボールを外して三塁走者をアウトにすると、最後は空振り三振でピンチをしのぎ切って広島が勝利。球団史上初めて日本一の栄冠を手にした。この9回裏の攻防は、江夏氏が投じた球数が21球だったことから、「江夏の21球」と呼ばれている。
大野:
あのときはベンチで見てましたけど、「これ、やばい。やられた」と思いましたね。江夏さんは信用してますけど、ノーアウト満塁ですからね。
徳光:
そうですよね。ああいう緊迫した場面は、同僚としてベンチで見ていて震えが来るでしょう。

大野:
もうたまらなかったですね。何とも言えない気持ちでしたよね。いろんな状況が入り乱れていましたから。

この試合、ノーアウト三塁一塁のピンチとなったところで、広島ベンチから池谷公二郎氏と北別府学氏がブルペンへ向かった。この動きに江夏氏は憤ったが、一塁手の衣笠祥雄氏が声をかけたことによって平静を取り戻したと言われている。
大野:
ただ投げるだけじゃなくて、動きの中で江夏さんの感情も出てましたし、それをなだめた衣笠さんもいらっしゃいます。そういう意味では、ただ21球だけじゃなくて、いろんな場面でいろんなドラマがあるわけですよね。僕らはそれをひたすらベンチでじっと見てたわけですから。
徳光:
なるほど。
大野:
ピンチのときに池谷さんと北別府がブルペン行く。それを見て江夏さんが結局どう思うかですよね。「自分が投げてる中でリリーフ陣を動かした。俺の信用はないのか」という雰囲気で、それを察知した衣笠さんがつかつかと行ってなだめて試合が再開するわけですけど、僕らはベンチで、「おいおい、大丈夫か、大丈夫か」と見てることしかできなかったです。でも、最後はああしてしっかり投げ切って、自分で作ったピンチを自分で乗り切った。
徳光:
あの1アウト満塁からスクイズを外した高めの1球はどう分析されてます。

大野:
あれはいろんな説がありますけど、ただ、あそこで瞬時にウエストできるのは、やっぱりキャッチャーの力なんです。三塁ランナーが走ったと同時に水沼さんが立ったんですよね。
それを察して江夏さんが外したんですけど、その外したボールは変化球なんです。変化球というのは低めに投げたいボールですから、高めに外す変化球ってのは、技術的になかなか難しいですよね。それをできる江夏さんもやっぱりすごいなと思いましたね。
徳光:
そういう話を聞くと、改めてすごいと思いますね。
最もきつかった3年間
翌1980年も広島はリーグ優勝、日本一に輝く。
この年のオフに江夏氏が日本ハムにトレードされ、81年からは大野氏が抑えになった。
徳光:
江夏さんとの師弟関係みたいなものは3年で終わり、今度は大野さんが抑えになる。
大野:
僕の一番辛い時代というのは初登板じゃないです。この江夏さんがいなくなった後の3年間、江夏さんの代わりにクローザーをやったときです。
徳光:
そうなんですね。

大野:
これは本当にきつかったですね。あの当時は今のように1イニング、勝ちゲーム限定の登板じゃなくて、セットアッパーとクローザーがセット。それを任せられたんですけど、うまくできない。一番ヤジられましたね。投げる前から「お前はもう投げるな、お前が投げたら負けるから投げるな!」と。
徳光:
お客さんからですか。
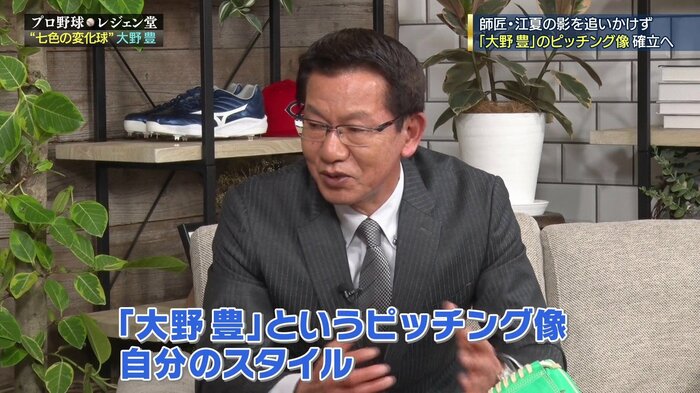
大野:
お客さんからです。そんなことを言われたら悔しいですよ。でも、そう言われるんであれば、そう言われないようなピッチャーになってやろうと。
僕はその一番苦しかった中で常に江夏さんを追いかけてたんです。でも、よくよく考えたら江夏さんを追い抜くことはできないし、近づくこともできない。だったら、大野豊という自分自身のピッチング像、自分のスタイル、これに色付けしてやっていこう。そう思うようになってから、ちょっと気持ちが楽になりましたね。
徳光:
いいところに気が付きましたね。
大野:
結構いろんなことに気付いているんですよね。これも社会人の経験のおかげです。
徳光:
なるほど。
【後編に続く】
(BSフジ「プロ野球レジェン堂」 25/3/25より)
「プロ野球レジェン堂」
BSフジ 毎週火曜日午後10時から放送
https://www.bsfuji.tv/legendo/





