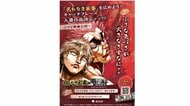日本3大オーケストラの一つ、東京都交響楽団は、東京オリンピックの記念文化事業として1965年に東京都が設立した。
定期演奏会を中心に、小中学生への音楽鑑賞教室、三宅島など多摩・島しょ地域での出張演奏、ハンディキャップを持つ方へのふれあいコンサート、2018年からは誰もが音楽の楽しさを体験・表現できる「サラダ音楽祭」を開催している。

都響のメンバーになるのは音楽家にとってはとても狭き門である。
たとえば、メンバーの1人が定年退職してポストが空いた場合、募集をすると、応募者が50人以上になるのは当たり前で、技術だけでなく都響との親和性など総合的に判断されるため、合格者がゼロの時もあるという。まさに音楽大学で首席クラスの演奏家が集まっているのだ。
音楽鑑賞教室で“音楽の魅力”伝える
1月30日に行われた中学生向けの音楽鑑賞教室を取材した。
演奏の前には、司会者が曲で描かれている情景や背景などを説明し、ポイントになる楽器に注目するよう呼び掛ける。
演奏が始まると、その迫力のある演奏に数百人の生徒たちがひきつけられ、身を乗り出して聴く生徒の姿も多く見られた。

クラシックの楽曲は演奏時間が長いものが多いが、音楽鑑賞教室では、生徒たちが飽きないようになじみのある小品や、特に有名な楽章を抜き出して演奏するなどしていた。
最後は、「ラデツキー行進曲」の演奏に合わせて手をたたくよう生徒たちに参加を促し、会場全体が一つになって幕が下りる。
「聞く人に感情や情景を伝えられる。演奏もやってみると楽しい。音楽を友達にすれば、最高の親友になる」。司会者は、音楽は人間の気持ちや感情を共有するツールであること、ライブのコンサートの楽しさについて生徒たちに語り掛けていた。
「若い世代の方々にも弾いている姿で伝えていきたい」
都響はこうした音楽鑑賞教室を年間で約50回、小規模な演奏会を100回ほど実施している。
都響の第2バイオリン副首席奏者の山本翔平さんは、演奏家の両親のもとに生まれ、子供のころからバイオリンを学んでいたが、都響との出会いは、小中学生対象の音楽鑑賞教室だったという。
そして学生の時、小澤征爾さんのコンサートキャラバンに参加、少人数であっても、演奏場所がどこであっても、音楽を通じて聞き手と感情を共有、シンクロすることこそ、音楽家にとって一番幸せな時間だということを学んだという。
「小澤さんから学んだ事、それは今も立ち返る場所のようなものなのですが、初めて都響で弾いた時から、音楽に対する積極性、お客様が誰であろうとベストを尽くす、そういう空気を感じました。それは今まで都響を築いてきて頂いた諸先輩方の伝統だと思います。それを僕らも絶やす事なく、これからの若い世代の方々にも弾いている姿で伝えていきたいと考えています」
「一生の間に“ずっと音楽が近くにある生活”を」
60周年を迎える2025年度の演奏会のスケジュールは、定期演奏会をはじめとする主催公演を47回。8回目となるサラダ音楽祭も実施する予定だ。

10月の都響スペシャルでは、すぎやまこういち作曲「交響曲イデオン」などアニメファンにもうれしい名曲が聴かれる60周年ならではの演奏会も予定されているそうだ。そのほかに都響の十八番といわれるマーラーの演奏は2026年2月の予定になっている。
都響のコンサートマスター、水谷晃さんに、2025年の演奏会への意気込みやヤングシート事業という取り組みについて聞いた。
「都響の大切な活動の一つである音楽鑑賞教室と並んで力を入れている活動として、子どもたちを無料でご招待する『ヤングシート』があります。抽選にはなりますが、親子のペア席で演奏会をお楽しみいただけます。理想的にはいずれ都響の定期会員になっていただきたいですが(笑)、心が何か刺激を求めた時、オーケストラ鑑賞も選択肢に加えていただけたなら、我々としては大成功です!この事業に協賛してくださっているたくさんのスポンサーさまが私たちと共にありますことも心強いです。
一生の間に“ずっと音楽が近くにある生活”を歩んでいただけるように、心に残る演奏を目指して取り組んでまいります」
ヤングシートで演奏を聴いた観客から都響に感謝のメッセージが届けられることは少なくない。
不登校の子供と一緒に演奏を聴いたという観客からは、「子供が『やっぱりオーケストラはいいね。僕の一生の趣味になっちゃうかも』と言っていました。息子に新たな世界を与えていただきありがとうございました」というメッセージが寄せられた。
音楽を知ってもらい、興味をもってもらうこと。都響の地道な活動で、今年も何人かの児童生徒の心に音楽の魅力が伝わることだろう。
(フジテレビ社会部 大塚隆広)