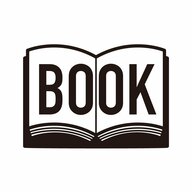見ている投手の誰もがすごいと言った。宇田川はそのフォークで信用を得て、チーム内に受け入れられた、という側面もあったのかもしれない。
データによって新鋭投手が評価され、仲間に受け入れられた、と言ってもよいだろう。
ダルビッシュ有の加入で、侍ジャパンは投手を中心に結束が強まり、チームコンディションも上向きになった。そして名古屋へ─。ここから当時エンゼルスの大谷翔平が合流したのだ。
ダルビッシュ・大谷に同じ問いをした星川
名古屋、バンテリンドームの初日、ブルペンに星川が待機していると、侍ジャパンと中日との試合の5回が終わったくらいに大谷翔平が入ってきた。

星川は大谷に「普段からポータブルの『トラックマン』を使っていると思うけど、どの項目を見ているんですか?」と聞いた。実は星川は宮崎でも同じ質問をダルビッシュ有にしていた。
驚くべきことに二人は「どの項目というよりも全般的に見て、自分の感覚と(『トラックマン』のデータが)合っているかどうかを確認している」と全く同じことを言った。
「あの二人が全く同じことを言っている。そこにはなにか深い意味があるんじゃないか?」
星川はホテルに帰ってじっくり考えてみて、二つのことに思い当たった。
一つは両投手ともに「仮説」を持っていること。データを計測した投手の多くは「僕の球どうでしたか?」「もっとよくするには、どうすればいいですか?」と聞くが、ダルビッシュと大谷は違った。
先に仮説があるのだ。
ダルビッシュ・大谷が1球1球確認する理由
「仮説」とはもともと“投げたい球”のことだ。
自分にとって投げないといけない球、“必要な球”がわかっていて、実際に投げた球が、自分が思っている通りの球になっているかどうかをデータで確認している。
だから1球1球、確認する必要が出てくる。
おそらく彼らであっても当然コンディションが日々違っていて、そんな中でも“投げるべき球”がある。それをデータで確認し、その差異をチェックしているのではないか?
そしてもう一つは、二人の投手は“自分の感覚だけを信用しているわけではない”ということだ。つまりファクトに基づいて自分のパフォーマンスを確認することを習慣にしている。
だからこそ二人とも、1球1球タブレットを見て確認していたのだ。
ファクトに基づいて確認する習慣は、文化の違いも含めてMLB的なのではないか。これこそが、まだまだ「感覚だけで投げる」ことが多い日本の投手とMLBの投手の決定的な差異かもしれない。
この二つは当たり前のことかもしれないが、「仮説」を立てることができなかったり、できても確認が十分にできない、ファクトチェックがしっかりできていない選手は多いのではないか。

広尾晃
コピーライターなどを経てスポーツライターに。立命館大学卒業。著書に『巨人軍の巨人 馬場正平』『野球崩壊――深刻化する「野球離れ」を食い止めろ!』(ともにイースト・プレス)など