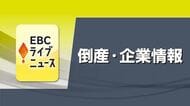「色としては上から2番目のだいだい色。ただ、今回は明確に感染が拡大しつつあると判定している」
国立国際医療研究センターの大曲貴夫センター長は、全体的な評価は先週と同じでも“中身”は全く違う、ということを冒頭で強調した。
11月12日の東京都の新型コロナウイルスモニタリング会議は、感染状況、医療体制とも先週と同様に深刻度を上から2番目の「オレンジ」に据え置いた。
しかし、コメントを先週までの「感染の再拡大に警戒が必要であると思われる」から「急速な感染拡大の始まりと捉え、今後の深刻な状況を厳重に警戒する必要がある」に変更した。
1カ月後には「1日に1160人」新規感染も
たしかに、感染状況の“中身”は先週と大きく異なっていた。
新型コロナウイルスに感染した人の7日間平均は前回の約165人から約241人と大幅に増加、100%を超えると増加傾向の指標となる増加比は147.7%になり、これが1カ月続くと1日あたりの感染者は約4.8倍の1160人程度になるという見通しも示された。

大曲センター長は「多すぎるのではないか、絵空事ではないかと言われるかもしれないが、私たちは夏に同じような状況があり、本当に週単位で患者さんが急速に増えていったことを経験している」と現場での経験を付け加えた。
感染経路は「夜の街→家庭→職場・学校→施設の繰り返し」
感染経路については、家庭内感染が15週連続で最も多くなっているほか、旅行、会食、自宅等でのパーティー、接待を伴う飲食店を通じての感染、部活動での感染など多岐にわたっている。
その中で、気になったのは接待を伴う飲食店、いわゆる夜の街での感染者の増加だ。
一時は新規感染者0人が続いていたのが11月に入ってじわじわ増えてきた。
このことをある都庁幹部に問うと「夜の街→家庭→職場・学校→施設を繰り返している」
つまり、感染経路が一周まわって再び夜の街での感染が増えてきた、というのだ。
さらに「“気の緩み”で感染して家庭内に持ち込んだもの、とも思っている」
コロナとの戦いが長くなればなるほど、気の緩みが出てくるのは仕方ないのかもしれないが、この感染症の“やっかいさ”を改めて実感させられる。
重症者も「一気に50を超えてきそうな数字」
医療提供体制についても東京都医師会の猪口正孝副会長が“中身の違い”について言及
「重症患者についても38人と先週から変わっていないように見えるが、約半数の患者さんが新たに人工呼吸器を装着されて、そしてそれが外されてと、ダイナミックに動いていて、重症患者がちょっとでも長引くと、一気に50を越えてきそうな数字である」
重症患者数が一見、先週の会議の時と同じ人数に見えても、今週は新たな重症患者が増えていて、これまでの重症患者の入院期間が少しでも長引けば、急増の恐れがある“中身”だというのだ。

さらに感染者の“中身”も重症化リスクの高い高齢者が増えている=ICU等に長く入る人が増える、ということで、重症者数が急増する恐れもあるという。
そうなると、医療機関は第一波の時と同じように、予定手術や救急の受け入れを大幅に制限しなくてはならなくなる、と猪口副会長は危惧する。
「一般の医療が必ず圧迫されてくるので、新規陽性患者が増えているというのは本当に心配な状況である」
小池知事「感染対策再徹底」「ネパール語の動画も」
「感染対策再徹底をお願いしたい」小池知事は手洗い、マスク着用、3密避けるなど、これまでの対策をしたうえで、テーブルやドアノブの消毒、こまめな換気をするよう呼びかけた。
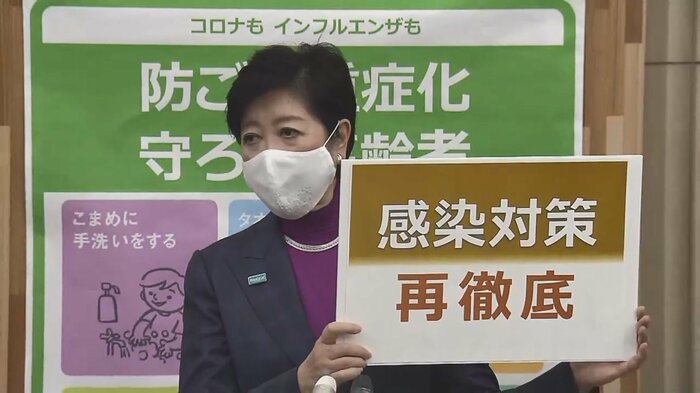
更に、きょうはもう一つ新たなことも
在留外国人の感染例が増えていることにふれ、「直近でお祭りが予定されているのはネパールのコミュニティです。ネパール語の動画も作成しています」
関係者によると、ネパール人の感染者が増えていて、その理由について「ネパール最大のお祭り「ダサイン」の関係で、集まっているとの話を聞いている」とのことだった。
小池知事は、今後はネパール語だけでなく「タガログ語などいろいろな言葉で直接コミュニティに伝わるようなきめ細かい対策をしていきたい」とも述べ、在留外国人への対策も強化する考えを示した。
感染拡大をここで食い止められるのか、今、私たちに出来ることは「感染対策の再徹底」に尽きるのだろう。
(執筆:フジテレビ都庁担当・小川美那記者)