2年をかけた“首都直下シナリオ”
中央防災会議の下に設置された「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」は12月19日、18人の専門家が2年という歳月をかけてまとめた首都直下地震の新たな被害想定を公表した。
ワーキンググループのメンバーは、増田寛也・野村総合研究所顧問を主査に、地震学、都市計画、経済、危機管理、エネルギー、自治体の現場、メディアまで、多様な顔ぶれで構成された。

報告書は「都心南部直下地震」と「大正関東地震タイプ」の2つを軸に、新しい被害想定と対策の方向性を示した。
プレート構造が複雑な東京圏で発生し得る多様な地震を整理し、M7クラスの直下地震とM8クラスの海溝型地震をどう位置づけるかを、最新の科学的知見と長期評価に基づいて再定義している。

委員たちは、首都直下地震を「国難級」の災害と位置づける一方、「対策を積み上げれば、被害は確実に減らせる」と繰り返し強調してきた。
報告書には、想定される被害をあえて具体的な数字で示しつつ、それを「不安をあおる材料」ではなく、「自助・共助・公助を動かすトリガー」として使う狙いが込められている。
40万棟被害と82兆円損失
ワーキンググループが最も重く見たシナリオの一つが、「冬の夕方(午後6時)、風速8メートル」の都心南部直下地震だ。
帰宅ラッシュと火気使用が重なる時間帯に、震度7の揺れが東京・神奈川を中心に直撃する想定で、建物被害や人的被害、経済損失が詳細に試算されている。
建物被害は、揺れ、液状化、急傾斜地崩壊、地震火災をすべて合わせて全壊・焼失が約40万2千棟。このうち地震火災による焼失が約26万8千棟を占め、東京23区と神奈川県の木造密集地での延焼が際立つ結果となった。
半壊は約58万棟で、もっとも被害を受けるのは東京23区だ。生活再建に時間と費用がかかる世帯が広範囲に生じる。

人的被害は、建物倒壊等による死者約5300人、火災による死者約1万2000人、その他の要因を合わせ、死者総数は約1万8000人に達するとされた。
負傷者は最大約9万8000人、自力で脱出できない「要救助者」が約4万4000人と推計され、大量救助・大量医療の体制がなければ命が救えない現実が示された。
経済面では、資産等の被害が45.1兆円、生産・サービス低下による全国的な影響が37.5兆円で、合計82.6兆円の損失が試算された。
これとは別に、道路や鉄道の寸断が半年続く場合、交通ネットワークの寸断による被害額は道路・鉄道で約10.9兆円。港湾の物流への影響は1年で約4.3兆円にのぼるとされる。

報告書は、こうした数字が「誇張ではなく、過去の大地震と最新データに基づくマクロな推計」であることを説明しつつ、対策を講じれば被害が大きく減ることもあわせて示す。
特に住宅耐震化と火災対策を組み合わせれば、全壊・焼失棟数や死者数を3割以上減らせるとの試算は、「逃げない・倒れない・燃えない」まちづくりの重要性を裏付けている。
『要対処人口』という新指標
首都直下地震の新しい被害想定は、「要対処人口」という概念を導入し、災害関連死リスクの見える化を進めた。
過去の大規模災害で、避難生活の長期化や医療の中断が、多くの人の命を奪ってきた事実を踏まえたものだ。
まず、東日本大震災や能登半島地震などのデータから、避難者1万人あたり40〜100人の災害関連死が発生していることが示された。
この比率を首都直下地震の想定避難者に当てはめると、災害関連死は約1万6000〜4万1000人に達する可能性がある。福島のように原子力災害を伴った厳しいケースを適用すると、最大約8万6000人という数字も出てくる。
報告書は、これを減らすために特に重点的な対応が必要な人たちを「要対処人口」と定義した。
1週間後の避難所には、要介護認定者が最大約13万2000人、難病患者が約3万人、妊産婦が約4万5000人いると想定される。こうした人たちに適切なケアが途切れれば、体調悪化から命に関わる事態に至る危険が高い。
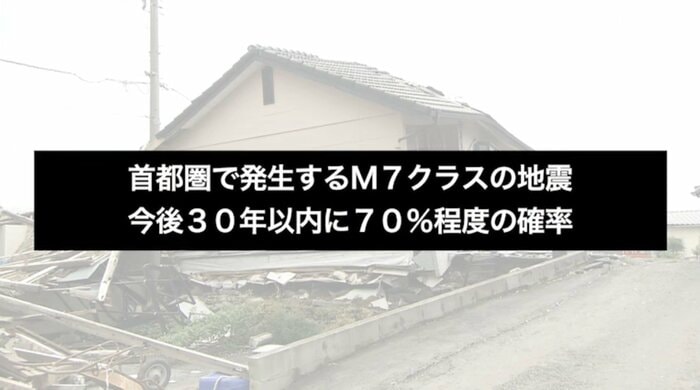
インフラ被害は在宅医療にも直撃する。
人工透析患者のうち、停電または断水に遭う人は最大約6万3000人、在宅人工呼吸器利用者で停電に遭う人は約3900人、そのうちバッテリーのない人が約1300人と推計されている。
医療機関側でも、病床の被災や職員不足で、入院を継続できない患者や新たに入院が必要な重症者を受け入れられないケースが出るとみられる。
報告書は、災害関連死を抑えるため、避難所運営を「健康を守る場」として設計し直すこと、在宅医療患者向けの非常用電源や水の確保、要介護者・難病患者・妊産婦に対応できる専門職の事前配置などを提案している。
自治体や医療機関、福祉分野が連携して「要対処人口」を把握し、平時から名簿や支援動線を整えておくことが不可欠だと強調する。
半分が停電・通信不通…“情報と電気”が消える首都圏
首都直下地震は、情報と電気に支えられた都市の基盤を一気に揺るがす。
新たな想定によると、被災直後、約1649万軒、全体の52%で停電が発生し、その状態が3日程度は続くと見込まれている。
発電所など供給側設備の被害を前提とするため、供給能力が夏季ピーク需要の48%にまで落ち込み、復旧には1カ月程度を要する。夏期ピーク需要自体は、12年前と比べ、約10パーセント増加している。
通信でも、固定電話とインターネットの不通回線数が最大約757万回線、全体の51%に達すると推計されている。
携帯電話は基地局の非常用電源が尽きる発災翌日に停波率が51%に跳ね上がり、数日〜1週間にわたり広い範囲で通話・データ通信が制限される見通しだ。
被災直後は電波が混み合い電話がつながらず、「安否も状況も分からない時間」が長く続く恐れがある。

上水道は最大約1400万人が断水し、1カ月後でも最大約120万人が断水下に置かれる。
下水道も処理場の機能停止や管路被害で支障人口が最大約200万人規模に達し、トイレや衛生面の悪化が健康被害を招く可能性が高い。
都市ガスは最大約141万戸で供給停止が起き、多い地域では完全復旧に5週間を要するとされる。
交通面での打撃も大きい。
道路では路面損傷や橋梁被害などが約1万900カ所、鉄道では線路が変形するなど施設被害が約6300カ所、橋梁・高架橋の中小被害が約880カ所発生すると想定されている。
新幹線と在来線、首都高と幹線道路の復旧が遅れれば、人と物の流れは長期にわたり制限され、経済活動全体に波及する。

報告書は、電力や通信の被害規模が前回想定より増えている一因として、需要や回線数の増加を挙げる一方、家屋耐震化や無電柱化、通信設備の耐震化などで一部の物理被害は減っていると分析する。
そのうえで、計画停電や通信制限を前提とした「アナログも含む多重の情報伝達手段」、分散型エネルギーや地域マイクログリッドの活用などを、今後の検討課題に位置づけている。





