2025年、明治時代から続いてきた刑法が118年ぶりに改正された。懲役刑と禁錮刑が一本化された「拘禁刑」の誕生である。“懲らしめ”から“立ち直り”を重視する刑罰へと大きく舵を切り、刑務所はいま変革の時を迎えている。
その塀の内側に迫った。
受刑者を“さん付け”で呼ぶ刑務官
広島刑務所の工場では、受刑者がミシンを動かしカープとのコラボグッズをつくっている。

その時、耳に飛び込んできたのは――
「〇〇さん、要件です」
受刑者を“さん付け”で呼ぶ刑務官の声である。
かつては呼び捨てが慣例だったが、2024年度から法務省が全国一律で“さん付け”を指示。刑務官と受刑者の関係構築が立ち直りを支えるという考えが根底にある。

広島刑務所の首席矯正処遇官・古谷大志さんは「これまで受刑者に対して見せていた顔とは“別の顔”を見せる場面が増えています。1人の人間として受刑者と向き合っていくことになります」と語る。
作業は義務ではなく“更生手段”
118年ぶりに改正された刑法に基づき、2025年6月に導入されたのが拘禁刑である。
これまで懲役刑の受刑者に義務付けられていた刑務作業はあくまで更生手段のひとつとなり、年齢や障がいの有無、依存症など個々の特性に合わせた“更生プログラム”が組まれるようになった。

拘禁刑の導入に伴って、広島刑務所が新たに整備した農場。ビニールハウスの中で広島菜が栽培されている。次の収穫に向け、受刑者がくわを手に土をほぐしていた。
ここで農作業を行うのは、心身に障がいがあり、出所後に福祉的支援が必要とされる受刑者たちだ。工場での刑務作業が困難で、これまでは個室で簡単な作業をしていたという。
「ゆっくりね。自分のペースでいいから」
農業の指導にあたるスタッフが受刑者に寄り添うように声をかける。
この農場は社会復帰に必要なスキルを身につけてもらおうと2024年に開設。農業指導者だけでなく福祉の専門家や多くの刑務官が立ち合い、作業を見守っている。
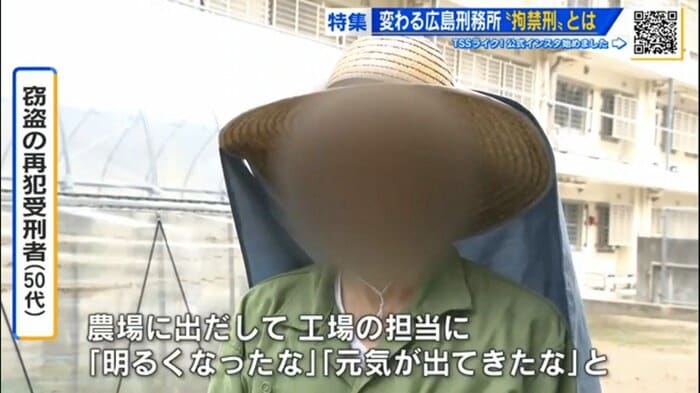
窃盗の再犯で服役する50代の男性は、「農場に出るようになってから工場担当の人に『明るくなったな』と言われるようになりました。物価高で野菜が高いので、出所したら自分で農作業をして生活を少しでも楽にしたい」と話した。
刑務所とは思えない部屋で…
広島刑務所の受刑者692人のうち、実に約85%が再犯者である。
再び罪を犯させないための“立ち直り支援”が課題となる中、広島刑務所が特に重視するのは「対話」。それを象徴する部屋がある。

テレビ新広島の竹内記者が案内されたのは「リフレクティングルーム」。元は受刑者の居室だったが、重厚なドアを開けると刑務所とは思えないほど明るい空間が広がっていた。
緑色を基調とし、間接照明と観葉植物が室内の緊張を和らげている。中央に置かれた3脚の椅子。小さなテーブルを囲んで刑務官と受刑者が対話する場所だ。
この部屋で、竹内記者は“受刑者役”を体験した。
対応するのは濱部刑務官と井上刑務官の2人。
「楽に腰かけて。クッションを前に置いても、足を上げてもいいですよ」

竹内記者が椅子を倒し、リラックスした体勢に座り直す。
「こんな感じで話を聞いてもいいですか?」
「全然、大丈夫です」
濱部刑務官は穏やかな口調で返した。
受刑者が「自分を見つめ直す」時間
「リフレクティングルーム」では、受刑者に威圧感を与えないよう刑務官は制服を脱ぎ、ラフな服装で臨む。
話題を決めるのは受刑者。趣味でも悩みでも、罪についてでも、語る内容は自由だ。
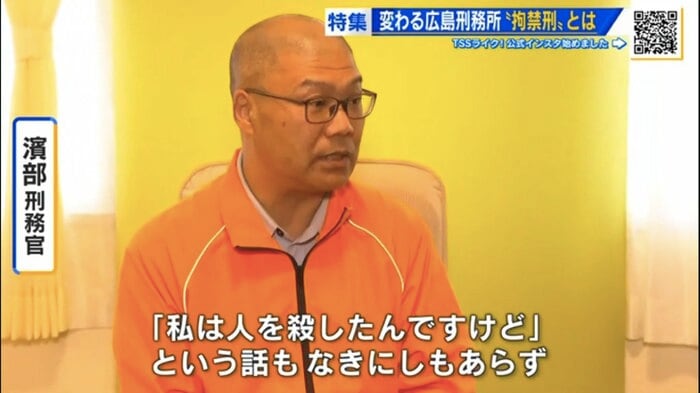
「話したいことを話してもらうだけです。『私は人を殺したんですけど』という話もなきにしもあらず、『社会に出て親孝行したい』と相談されたこともあります」
そして、もう一人の刑務官は“観察者”として耳を澄ます。
観察者の井上刑務官は、対話の後で「受刑者がどんな人に見えたか」を濱部刑務官と共有。受刑者本人はその話を第三者として聞きながら、自分が他者にどう映っているのか客観視できる。

体験した竹内記者はこう話す。
「自分の話をほかの人が振り返るのを見るのは少し恥ずかしいですが、嫌な気持ちはしませんでした」
刑務官との対話と自分自身の見つめ直し。この2点で、更生のきっかけをつかんでもらおうというのがねらいだ。
“御法度”だった受刑者との対話
ただ、対話の導入は、刑務官にとって価値観の“180度転換”を求められる。

井上刑務官は「昔は受刑者と会話するなんて御法度でした。最初は戸惑いましたが、対話後に受刑者の顔を見たら和やかな表情になっている。こういう一面が見られると、この取り組みによる変化を感じます」と語った。
服役中にコミュニケーション能力が育たず、出所後、社会になじめないケースも多いという。再犯防止のため、広島刑務所では拘禁刑の施行を機に対話の時間を増やした。
刑務官の負担も大きい。それでも「再犯者を減らす」ため、試行錯誤が続いている。

新たな取り組みは始まったばかり。拘禁刑によって、今後どのような変化が生まれるのだろうか。
(テレビ新広島)





