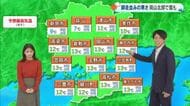瀬戸内市のハンセン病療養所、長島愛生園に11月、体験型展示施設がオープンします。懸命に生き抜いた入所者たちの生きた証を残したいー多くの願いが込められています。
◆瀬戸内海を望む「ハンセン病療養所」の病棟が“入所者の生きた証”に生まれ変わる
中に入ると、療養所から見える瀬戸内海が迎えてくれます。「きれいだな」と思えるまでに10年かかったと入所者が話す海です。
瀬戸内市の国立ハンセン病療養所、長島愛生園に11月にオープンするのは「でんしょう愛生館」です。使われなくなった病棟を改築しました。
◆「ここでは皆さんに偽名を名乗っていただきます」入所者が最初に入った部屋で本名を隠さねばならない理由
【はじまりの部屋】
(学芸員)
「本日はでんしょう愛生館にご来館いただきありがとうございます。ここでは皆さんに偽名を名乗っていただきます」
入所者が最初に連れて来られた部屋が再現されました。
「愛生園に入所した患者さんは、家族に差別が及ばないように園内名を名乗りますか、と尋ねられました」
本名を隠さなければならなかった入所者の気持ちに触れます。
(竹下美保記者)
「考えるととてもつらい気持ちになりますね。この名前を呼ばれたら呼ばれたで複雑な気持ち」
ハンセン病は治療法も見つかり感染力の弱い病気にもかかわらず、国の誤った隔離政策により患者は皆、強制収容されました。
◆もし「ハンセン病で療養所に隔離されたら」…自分ごととして感じてもらう9つの展示
ハンセン病問題を学ぶ展示は、企画展などを含め9つに分けられていて、「ハンセン病」を自分ごととして捉えてもらうための工夫が施されています。
(長島愛生園歴史館 田村朋久学芸課長)
「知識として持って帰ってもらうだけでなく、本人の体験として、どういう思いをそこに乗せているのか感じていくために追体験に重きを置いた」
(竹下美保記者)
「園の歴史を伝えるパネル展示です。写真が大きく引き伸ばされていて、自分自身もその場にいたような感覚を味わってほしいということ」
これまであまり見られなかった、療養所で生き抜いた入所者の顔をしっかり見てもらおうと、写真も紹介されています。
【VRシアター】
「お子さんはらい病(ハンセン病)ですね」
・本人家族社会の視点で物語を体験できる
「岡山県の長島によい療養所があって、そこに隔離されることになる」
【企画展には岡山・奈義町在住の漫画家、あさののいさんのイラスト】
・入所者の思いを伝える
【はやり病の物語】
【感染症の歴史を伝える】
誹謗中傷が問題となった新型コロナウイルスの流行は、ハンセン病の歴史が生かされていないと、入所者の多くが心を痛めました。
◆“追憶の森”の木の葉には入所者の「名前」が…「解剖記録」公開など偏見・差別のない社会の実現に向けた挑戦も
園は、これまで遺族の希望で、入所者の解剖記録を一般公開するなど、新しい企画を打ち出してきました。今回も・・・。
偏見・差別のない社会を実現するという決意を込めた挑戦をしたのです。
(竹下美保記者)
「こちらは追憶の森という展示、木の葉には開園当初の85人の入所者の名前が書かれています」
“開拓者”として希望してやって来たとされる人たち。今後も入所者の名前を公開し、名前が書かれた木の葉を増やしていきたいというのです。
【3年前…】
(長島愛生園 山本典良園長)
「7000人が愛生園に入所したことを、数だけではなく入所番号・名前・生年月日があると非常に身近に感じられる。その上写真があったら、それこそ、ここに生きていた、療養していたきのうのように感じられる」
入所者はもちろん、家族などの理解も必要で、簡単なことではありません。しかし、入所者の息吹を感じてほしいとの思いを込めました。
◆ハンセン病は「痛めつけられた病」だった…入所者の“息吹”を感じてほしいという願いを込め「でんしょう愛生館」21日オープン
長島愛生園の入所者の平均年齢は89歳を超え、語り部ができるのも91歳となった中尾伸治さん1人だけとなりました。新しい施設「でんしょう愛生館」には、多くの時間が残されていない入所者の願いが詰め込まれているのです。
(長島愛生園入所者自治会 中尾伸治会長)
「ハンセン病は、痛めつけられた病だった。本人だけでなく家族も、みんなばらばらになってしまった。堂々と名前が出せるような時代にしてほしい」
「でんしょう愛生館」は11月21日にオープンします。