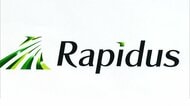離島などの海岸に漂着する海ごみが海洋生物の生態系へ影響を及ぼす等が大きな問題になっている中、東京都が漂着ごみを回収・運搬する自律型ロボットの研究・開発を支援することになった。
小笠原諸島や伊豆諸島の海岸には、毎年台風の季節になると流木やペットボトルなどプラスチック・ビニール類などのごみが大量に打ち寄せられている。
東京都は小笠原諸島や伊豆諸島の海岸漂着物対策を進めており、小笠原諸島では2024年度に6海岸の調査を実施、うち4つの海岸が漂着物がやや多いから、非常に多い海岸と評価されました。
漂着ごみの内訳では、流木や海藻などといった自然系のごみとプラスチックなど人工的なごみが半々で、人工的なごみの割合ではペットボトルや洗剤容器といったプラスチック・ビニール類が最も多く、次いで発砲スチロールとなった。
海外からと思われるごみも1割ほど含まれていて、国籍別では、6割以上が中国で、台湾、韓国の3つの地域を合わせると全体の9割を占めた。
ごみの回収作業は、海岸管理者である東京都や林野庁が行うほか、海水浴や観光のシーズンに合わせて地元の自治体や住民などのボランティア、漁業関係者が行っている。
漂着ごみの回収で現在の課題となっている点はまさに、人手不足にある。
住民やボランティアによる回収は、観光シーズンに合わせた時期に限られる。打ち上げられたプラスチックが放置される期間が長くなるほど岩などとぶつかり、マイクロプラスチックに変化していく。
そこで東京都が注目しているのが、株式会社ピリカが開発中の自律型ロボットだ。
東京都は、ピリカの自律型ロボットの研究開発について、東京ベイeSGプロジェクトの先行プロジェクトとして採用を決定した。
ピリカの開発する自律型ロボットはロボット本体が周囲を探索してごみを発見、アームハンドでごみを拾い上げ、ごみを運搬するロボットまで運び、集めるというものだ。
ピリカは、10年以上にわたり水上ごみの回収ロボットの開発や道路に落ちているゴミの種類を認識するシステムの開発などを道路に落ちているゴミの種類を認識するシステムの開発などを手がけてきた。
ピリカのこうしたごみ判別能力を活用し、漂着ゴミを回収するロボットの開発を進めていくことになる。
2026年にも試作機が完成し、都内の海岸で実証実験をスタートさせる予定だ。
(画像はイメージ)