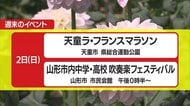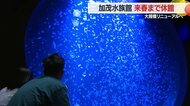天童市の小学生が、昔ながらの冬のおやつ「干し柿づくり」に挑戦。柿の収穫から干し柿の作り方まで、地域のみなさんが先生となって大活躍した。
(リポート)
「オレンジ色に実ったたくさんの柿。これから約1000個の柿を収穫し、午後には小学生が干し柿作りに挑戦します」
天童市の寺津地域づくり委員会は、地域の伝統や風習を知ってもらおうと、寺津小学校の児童に「干し柿づくり」を教える活動を18年前(2007年)から続けている。
この柿は、平核無柿(ひらたねなしがき)という品種で、種がなく四角い形が特徴。
いわゆる“渋柿”で、乾燥・熟成させる過程で渋が抜け、濃厚な甘みを持つ干し柿に仕上がるとされている。
31日朝、町内会の役員など8人が、約30分で1000個の柿を慣れた手つきで収穫した。
(寺津地域づくり委員会・太田藤昭さん)
「いつもの3分の2くらいの大きさ。子どもたちが大人になって思い出してくれれば良い」
(寺津地域づくり委員会 委員長・大石章夫さん)
「地域の人と子どもたちが交流できる場所。秋はこういう風にいっぱい柿があるので、ある材料を使って子どもたちと交流したい」
収穫した柿は寺津小学校に運ばれ、いよいよ干し柿づくりが始まる。
まずは皮むきから。
全校児童約60人のうち、低学年の子どもたちはピーラーで、高学年はナイフで皮むきに挑戦。
(児童)
「去年はあまりにも四角く切っちゃったが、去年よりは少し良くなった。六角形くらいになった」
ナイフを使い慣れていない子どもたちも、ベテランの地域の人たちに教えてもらい、皮むきを無事終了。
次は、柿のへたにひもをくくりつけて完成。
毎年行われるイベントということで、2024年よりも上手にできただろうか?
(5年生)
「95点です。まだ100点はあげられない。去年は急ぎで作って小さくなったので今回は丁寧にできたかなと」
(4年生)
「98点。実をちょっと多く削っちゃったから。来年はそんなに削らないでもう少し皮だけむけるようにしたい」
干し柿は校舎の軒先につるされ、12月初旬に出来上がる予定。
完成後は、日ごろお世話になっている地域の人たちに、感謝の手紙を添えて渡ることにしている。