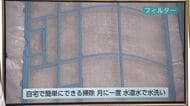東日本大震災の教訓を学び、南海トラフ巨大地震などに備えてもらおうと、宮崎市でシンポジウムが開かれました。
キーワードは「事前復興」です。
このシンポジウムは宮崎大学が開いたもので、大学関係者のほか行政職員や市民など、およそ170人が参加しました。
シンポジウムでは、津波防災の第一人者である、東北大学災害科学国際研究所の越村俊一教授が、「過去から学ぶ大規模自然災害への備えと事前復興」と題して講演しました。
越村教授は、東日本大震災での教訓について、津波の威力や速さのほか、津波によって出たがれきが東北3県だけでおよそ2300万トンとなり、国が処理できる能力を超えたため、復旧に時間がかかったと説明しました。
(東北大学 災害科学国際研究所 越村俊一教授)
「堆積物を含んだがれきをどう取り除いて、迅速に取り除いて、すばやく立ち直っていくかということも、考えるひとつ」
また、震災後に作られた仙台市の復興計画を紹介。
防波堤の高さには限界があるとし、海岸防災林やかさ上げした県道の構築、災害危険区域からの集団移転の促進など、多重の防御策が必要だと訴えました。
ただ計画を実行するには事前の合意形成が重要だと話しました。
(東北大学 災害科学国際研究所 越村俊一教授)
「津波の想定が行われて、そのエリアは恐らく被害を受けるといった時に、そこの復興をどうしようかということを今から決めておくというのが事前復興」
「ものすごく時間がかかった。なぜなら、事前に何の合意もないから」
(東北大学 災害科学国際研究所 越村俊一教授)
「津波の被害がどういうものであるか、津波から身を守るためにはどうしたら良いのか、そして立ち直っていくためにはどうしたら良いのか、我々の経験を通じて、ぜひ知ってもらいたい」
宮崎県では現時点で南海トラフ巨大地震が発生した際の復興計画は策定していないということです。