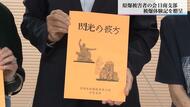終戦の混乱で日本の植民地だった旧満州では、子供たちの多くが現地に取り残され残留日本人となりました。
日中のはざまで翻弄され続けた女性が、過酷な人生を語りました。
カラフルな扇子を手にお年寄りたちが踊るのは、中国の東北地方に伝わる大衆舞踊です。
ここは愛知・名古屋市にある介護施設「ひかりの里」。
介護を受けているのは、主に中国から帰国した残留日本人たちです。
庄山陽宇子さん(84)。
熊本で生まれ、3歳のころ両親ときょうだいの家族5人で中国東北部にあった日本の植民地、旧満州に移り住みました。
しかし、終戦の混乱で家族と離れ離れになり、当時4歳だった庄山さんは中国に取り残されました。
庄山陽宇子さん:
どの家も引き取ってくれなかった。女の子で豚の世話も畑仕事もできないから。結局、3軒の家をたらい回しにされた。(Q.ギョーザの包み方は誰に教わった?)教わったことはなく、義母らが包むのを見て自然に覚えた。
中国人の家庭に引き取られ、中国名「ウ・シュクキン」として育った庄山さん。
当時は自身が日本人であることを知りませんでしたが、事情を知る周りの人から差別的な言葉でののしられることもあったといいます。
庄山陽宇子さん:
“日本の鬼子”と呼ばれた。(Q.直接ですか?)そうです。やっぱり嫌な気持ちになりました。
16歳のころに中国の公安の調査で初めて自身が日本人であることを知った庄山さん。
その後、中国人の夫と結婚し4人の子宝に恵まれましたが、実の両親に会いたいという強い思いから日本への帰国を決断。
終戦から54年が経った1999年、家族とともに永住帰国を果たしました。
しかし…。
庄山陽宇子さん:
両親に会いたくて日本に来たけれど、すでに亡くなっていたんです。
同じく残留日本人となり、先に帰国していた兄とは再会できたものの、両親と弟は戦後まもなく感染症で亡くなっていたことを知りました。
庄山陽宇子さん:
(両親の写真を)毎日見ます。会いたくてたまらない。
これまでに永住帰国を果たした中国残留日本人は6730人。
その中には、言葉の壁に阻まれ日本社会になじむのに苦労している人も少なくありません。
庄山さんも、その1人です。
庄山陽宇子さん:
日本国籍を持っていても、日本人は私を日本人とは思わず“中国人”と言う。中国に行けば今度は“日本人だ”と言われる。
そして今、そうした残留日本人の高齢化が進み、介護を必要とする人が急激に増えています。
同様に介護が必要となった庄山さんが選んだのが、中国残留日本人向けの介護施設です。
施設での食事は中華料理がメインで、口になじんだものが中心。
スタッフは日本の介護資格を取得した中国人で、言葉の心配もありません。
お昼に流れるのも中国のニュース番組です。
介護スタッフの男性は、「日本のニュースは見ても分からない。日本の出来事は職員から伝える」と話します。
施設の代表、王洋さんは、妻が残留日本人の3世で、日本で介護士の資格を取り介護事業を始めました。
残留日本人の女性を受け入れたことをきっかけに、多くの残留日本人が言葉の壁などにより介護の面でも孤立していることに気付いたといいます。
ひかりの里・王洋代表:
(残留日本人は)要介護になっても日本の介護制度を知らなくて、1人暮らしでも踏ん張って、うちの営業活動で国の保険サービス制度も使えることを知って、徐々に使えるようになった。
当初は一般の高齢者向けの施設でしたが、「残留日本人を再び置き去りにしてはいけない」と考え、残留日本人に特化した介護施設に切り替えました。
10年前に1人だった残留日本人は、今では70人にまで増加。
しかし、全国的に見ればこうした施設はまだ不足していると指摘します。
ひかりの里・王洋代表:
特に(残留日本人の)人口が多い、東京、長野、大阪はまだ足りてない。名古屋でももう少し増やしても全然可能性はある。
庄山陽宇子さん:
戦争、私たち一家にとっては、親も子もバラバラに引き裂かれ、泣くものもいれば叫ぶものもいて、本当にとてもつらいものでした。
中国と日本、その狭間で翻弄され続けた多くの残留日本人。
その多くを再び孤立させないための十分な取り組みが今、求められています。