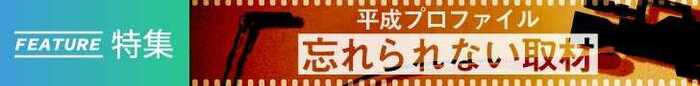受け入れられなかった突然の死
平成6年(1994年)12月6日。
米国ワシントンDCに赴任して5年が過ぎ、僕はまもなく帰国することになっていた。
その日は、短い欧州出張を終えてワシントンに戻り、タクシーの中からフジテレビの支局に電話した。
助手のポールが出て、「平井さん、カイロの入江さんがおかしなことになって…」と言った後、黙っている。
おかしなことって何だろう。
普段は日本語が上手なのだが、動転してるのか要領を得ない。
支局長に代わってと頼むと、カイロに行きましたと言う。
変だと思って東京に電話した。
外信部長から、入江君がルアンダ難民の取材で乗った飛行機が行方不明になった、絶望的だ、と聞いた。
入江が死んだ?
言葉が出ず、電話を切った。
一人ではアパートに帰る気がせず、カメラマンを誘って日本料理屋に行き深夜まで飲んだ。
その日は眠れなかった。
「前へ、前へ」が口癖だった入江特派員

入江君は僕より2年後の入社だが、新人の頃から行動力が抜群で「前へ、前へ」が口癖だった。
記者に最も必要な能力は「現場での強さ」だと思う。
取材対象に対して、他社に対して、自然に対して、強くなければならない。
彼にはそれがあった。
どちらかと言うと「後方分析型」の僕は、とてもかなわなかった。
僕がワシントンに赴任したのは90年8月。
イラクがクウエートに侵攻した直後だった。
関心はいつ米国が攻撃するか、さらに地上戦、つまり本当の戦争にいつ入るかということだった。
高校生くらいの頃から、海外特派員には憧れていた。
きっかけはヒッチコック監督の映画「海外特派員」。
米国NYで働くハンサムな記者ジョンは、ある日ロンドン特派員を命ぜられ、慌ててトランクに着替えを詰めて飛行機に乗る。
これがかっこよかった。
大学生になってマスコミを目指すことを決めた時に、サツ回りでなく海外特派員だと心に決めていた。
湾岸戦争を開始

29歳で入社以来2度目の外信部勤務となり、中国の天安門事件、東欧革命などを取材した後、ワシントン駐在になった。
どの仕事も面白く、夢中になって働いた。
91年1月米軍と多国籍軍は空爆を開始、さらに2月には地上戦に突入し、100時間後にはあっさりクウエートを解放した。
初めて戦争というものを取材して、2つ忘れられないことがある。
1つはワシントンポスト紙の「ニンテンドーの戦争」というタイトルの社説。
当時、任天堂のゲームは世界を席巻し、ニンテンドーはコンピューターゲームの代名詞だった。
社説は、「政府もメディアも、戦争を任天堂のゲームのように面白く伝えるが、戦争というのはあなたの息子の手がちぎれ、足がなくなり、そして命を失うものだ」という淡々としているが、ドキッとする内容だった。
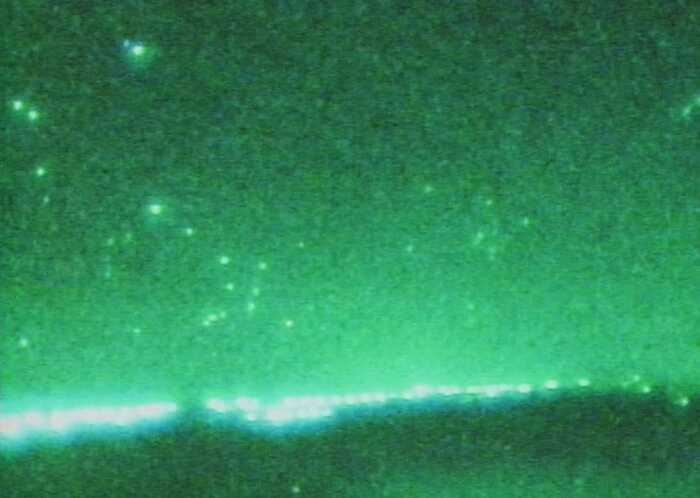
もう一つは軍のトップだった、パウエル統合参謀本部議長。
地上戦突入の会見で、軍人だからさぞかし威勢のいいことを言うだろうと思っていたら、冒頭にいきなり「私はイラクに派遣する兵士を全員生きて返したい」と言ったことだった。
世界の警察として思うがままにふるまっている米国だが、みんな死ぬのは怖いんだなとその時つくづく思った。

人の命は簡単に終わる。
あっという間に死ぬのだ。
それは特派員として世界各地を取材してわかったことだった。

さらに今回米国に来て新たに知ったのは、革命の現場に行かなくても、軍というのはしょっちゅう事故が起きて、兵士が死んでいるという事実だった。
僕はどんどん臆病になっていった。
ただ、湾岸戦争では米国政府の対応と外交交渉が担当だったので、戦争の現場に行くことはあまりなかった。
何度かは行ったが、米軍と一緒に行動し、これは怖くなかった。
軍や警察が構える銃の前に出るのはとてつもなく怖いが、銃の後ろにいる分には安全、という当たり前のことを学んだのだ。
世界の警察官を目指したアメリカ
湾岸戦争が一応終わり、大統領もブッシュからクリントンに代わって2年が過ぎた1994年の10月、クリントンはなぜか中東に行くと言い出した。関係者に聞くと、中間選挙の戦況が思わしくなく、外交で得点を挙げたいということらしかった。当時中東は、米国にとって、湾岸戦争勝利の場所でありゲンが良かったのだ。

クリントンはイスラエル、ヨルダン、シリアを回り、中東への米国の関与を確認した。
同行取材した僕は、カイロ支局長の入江君と一緒に動いた。
彼と最後に会った日のことはよく覚えている。
10月27日、クリントンはエルサレムを訪問。
僕は夜のニュース用にリポートを撮って東京に送った。
その後、入江君と市内のレストランで、シシカバブと羊の脳みそを食べた。
この羊の脳みそがおいしかった。
なんでも日本のフグの肝と味が似ているらしい。
フグの肝は子供のころ食べたことがあるが、確かに似ている。
そんな話をしながら食べた。
食べながら二人で今後の話をした。
入江君も帰国が迫っていた。
当時、欧米のテレビ局は中継機材を飛行機で世界中に運び、そこでアンカーパーソンに中継させる、「ロケーションアンカー」というやり方を始めつつあった。
フジテレビでも当時の報道局長が、それをやろうと言い出し、僕や入江君ら何人かがそのチームに入ることが内定していた。アンカーパーソンは安藤優子さんだ。
2人でワインを飲みながら、遅くまでしゃべった。
そしてレストランの前で握手をして別れ、それぞれのホテルに帰った。
それが入江君を見た最後だった。

「こんな仕事やめたくなる」
訃報を聞いたのはその1か月後だった。
チャーターした小型飛行機が墜落したのだった。
僕も当時はよく小型飛行機で移動することがあった。
席に座った後に、バランスが大事だと、操縦士が人や荷物の位置を直すことがよくあった。
それがいつも不安だった。
入江君の乗った飛行機はバランスを崩して墜落したのだった。
その日の日記にこう書いている。
若かったので自信過剰な部分がある。
「入江死去。信じられない思い。ライバルとして脅威を感じていたので、その分、親近感があった。二人でフジテレビの外信部を支えているという自負があったし、これからも背負っていこうと思っていた。その片割れが簡単に死んでしまい、力の抜ける思いだ。人が死ぬのは嫌だし、そのために周りの人が悲しむのはもっと嫌だ。こんな仕事やめたくなる。」
翌1995年(平成6年)、僕は米国勤務を終え帰国した。帰ってみると、入江君の死とともに、ロケーションアンカーの計画はなくなっていた。
人の命が終わることの意味
僕はしばらく外信部のデスクをやった後、次の海外赴任までのつなぎに、政治部の外務省クラブへの異動を希望した。ただ配属先は野党クラブで、国会で36歳での番記者生活はきつかった。だがその後、外信部には戻らなかった。後に外信部長から、「お前を次はパリ支局長にしようと思ってたのに、外信に戻って来なかったな」と言われた。
僕は海外特派員をやめてしまった。
入江君とのコンビの仕事がなくなったから、つまらないと思ったのか。
革命や戦争の取材がもう嫌だったのか。
あるいは、自分を含め人の死というものが怖かったのかもしれない。
憧れて入社したのに、海外特派員生活は、結局6年弱だけだった。

湾岸戦争は米軍及び多国籍軍の圧倒的勝利だったが、パウエルの心配は現実となり、米兵は300人近くが死亡した。
ボディバッグ(遺体袋)に入れられた米兵の遺体は、輸送機で中東から米国の基地に運ばれ、そこで白い棺に納められる。
基地の格納庫にずらっと並べられた棺は、戦争の現実を見せつけた。
米国はこの後も長い間、中東で戦い続けたが、オバマ政権で方針を転換。
撤退を開始するとともに、新たな関与にも慎重になった。
世界の警察官をやめたのだ。
理由として、軍事費の高騰による財政負担に耐えられない、あるいは、シェールオイルの開発で中東の石油の重要度が下がった、などと説明されている。
しかし本当の理由は、米国の若者を戦争で殺し続けることに、米国自身が耐えられなくなったからではないだろうか。
関連記事:「平成プロファイル ~忘れられない取材~」すべての記事を読む