1月20日に第47代アメリカ合衆国大統領としてドナルド・トランプ氏が再び就任してから3カ月が経過した。
この間、トランプ政権の経済政策の柱である関税戦略が具体化し、その特徴が明確に浮かび上がってきた。
様々な捉え方があろうが、1つにトランプ関税は大きく「特定品目関税」と「特定国関税」の2つの側面に分類される。
これらは目的や対象、政策的意図において異なり、それぞれ経済性と政治性の比重が異なる特徴を持つ。
本稿では、トランプ政権の関税政策を振り返りつつ、「特定品目関税」が財政赤字削減を主眼とした経済合理性を重視するものであるのに対し、「特定国関税」が移民対策や安全保障におけるディールとしての性格を強く持つ政治的ツールであることを論じる。
トランプ関税の背景と発足初期の展開
トランプ大統領は選挙キャンペーン中から「アメリカ・ファースト」を掲げ、貿易不均衡の是正や国内産業の保護を訴えてきた。

2025年1月の就任直後、この公約を実行に移す形で関税政策が矢継ぎ早に打ち出された。
最初の3カ月で、鉄鋼やアルミニウム、半導体といった特定品目への関税が発表され、同時に中国やメキシコなど特定国に対する包括的な関税措置が発表された。
これらの政策は、2017~2021年の第1期トランプ政権で実施された関税戦略の延長線上にあるが、新政権ではその対象範囲と適用条件がより精緻化されている。
トランプ政権の関税政策は、単なる経済・貿易上の保護主義の枠を超え、経済的・政治的目標を同時に追求する二重構造を持つ。
特に注目すべきは、関税が単に輸入品の流入を抑える手段ではなく、国内経済の再構築と対外的な交渉力を強化するツールとして設計されている点である。
この二重性が、「特定品目関税」と「特定国関税」という2つの側面に結実している。
「特定品目関税」経済合理性を軸とした財政戦略
「特定品目関税」は、鉄鋼、アルミニウム、半導体、農産物など、特定の産業や品目を対象とした関税である。
この関税の主目的は、財政赤字の削減と国内産業の競争力強化である。
現時点で、アメリカの連邦債務はGDP比で130%を超えており、インフレ抑制と財政健全化が急務とされている。

トランプ政権は、税収を増加させ、同時に国内生産を刺激し、雇用創出を図る戦略を採用している。
例えば、鉄鋼・アルミニウム関税は、第1期政権時の2018年措置を踏襲しつつ、対象品目の範囲を拡大した形で再導入された。
これにより、カナダやEUからの輸入品に25%の関税が課され、国内鉄鋼産業の保護が図られている。
この政策の経済合理性は、関税収入が年間数百億ドル規模で財政に寄与する点にある。
財務省の試算によれば、2025年度の関税収入は前年比で約15%増加する見込みであり、これがインフラ投資や減税政策の財源として活用される予定である。
また、半導体への関税は、先端技術の国内回帰を促す意図を持つ。
中国や台湾からの輸入依存度が高い半導体産業において、関税は国内生産能力の拡大を後押しする。
2022年のCHIPS法による補助金政策と連動しつつ、関税は輸入コストを高めることで、アメリカ企業に国内投資を促すインセンティブを提供している。
このように、「特定品目関税」は経済的合理性を基盤とし、財政再建と産業振興を同時に目指す政策であると言える。
しかし、この関税には限界もある。
輸入価格の上昇は消費者物価に転嫁され、インフレ圧力を高めるリスクを孕む。
また、報復関税による輸出産業への打撃も無視できない。
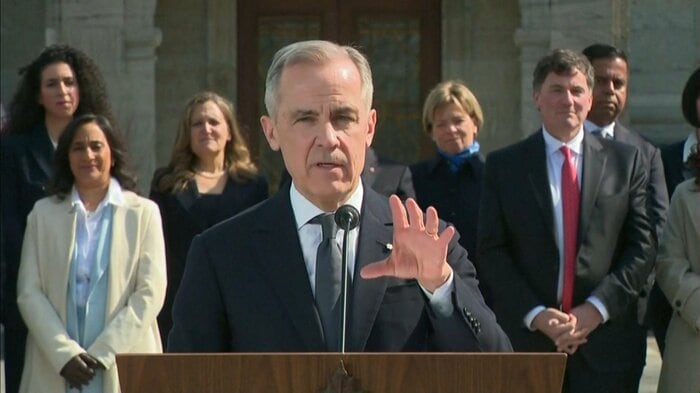
カナダは米国の鉄鋼・アルミニウム関税に対し、報復措置として米国産の鉄鋼・アルミニウムやその他製品(ウィスキー、ヨーグルトなど)に25%の追加関税を課す方針を表明した。
それでも、トランプ政権は短期的な経済的コストを上回る長期的な利益を見込んでおり、「特定品目関税」を経済政策の中核に据えている。
「特定国関税」政治的ディールの道具としての関税
一方、「特定国関税」は、中国、メキシコなど特定の国を対象とした包括的関税である。 この関税の特徴は、経済的効果とともに政治的交渉を重視したディールとしての性格が強い点にある。特定品目関税より政治性が濃い。
トランプ政権は、関税を「交渉のレバレッジ」として活用し、相手国から譲歩や負担を引き出すことを目指している。
その対象は、貿易収支の是正に留まらず、移民対策や安全保障における防衛費負担の拡大にまで及ぶ。
例えば、第二次トランプ政権の発足当初、中国に対する関税は、第1期政権時の25%関税を基盤に、さらに上乗せすることが検討されていた。

この背景には、米中間の技術覇権争いと安全保障上の緊張がある。
トランプ大統領は、中国が知的財産権の侵害や不公正な貿易慣行を改めない限り、関税を解除しない姿勢を明確にしている。
さらに、中国企業への輸出規制と連動させることで、アメリカの技術優位性を確保する戦略が進められている。
この関税は、経済的損失を中国に強いることで、交渉テーブルへの復帰を促す政治的ツールとしての役割を果たしている。
メキシコに対する関税も同様に政治性が強い。
2025年2月、トランプ大統領はメキシコからの不法移民流入を理由に、全輸入品に対する25%の関税を提案した。
これは、2019年に同様の脅しでメキシコから移民対策の強化を引き出した手法の再現である。
メキシコ経済がアメリカへの輸出に依存している点を突き、関税をちらつかせて国境管理の強化を迫るディールである。
結果として、メキシコ政府は3月に対策強化を約束し、関税発動は棚上げされた。この事例は、「特定国関税」が経済的効果以上に政治的成果を優先する性質を如実に示している。
経済性と政治性の対比と今後の展望
「特定品目関税」と「特定国関税」の最大の違いは、その目的と影響範囲にある。
「特定品目関税」は経済合理性を重視し、財政再建と産業保護を直接的な目標とする。
一方、「特定国関税」は政治的ディールとしての性格が強く、相手国との力関係を変化させる手段として機能する。
この二重構造は、トランプ政権の関税政策が単なる保護主義を超えた戦略性を有していることを示す。
しかし、この二重性がもたらす課題も見逃せない。
経済性を追求する「特定品目関税」は、グローバルサプライチェーンの分断やコスト増を招き、アメリカ経済の成長を阻害する可能性がある。
一方、政治性を帯びた「特定国関税」は、国際関係の緊張を高め、長期的な同盟関係に亀裂を生じさせるリスクを孕む。

今後、トランプ政権がこの2つの関税をどのように使い分けるかが注目される。
経済的合理性を優先するならば、「特定品目関税」の適用範囲を拡大しつつ、報復関税への対策を講じるだろう。
逆に、政治的ディールを重視するならば、「特定国関税」を柔軟に運用し、交渉の成果を最大化する戦略を追求するだろう。
いずれにせよ、トランプ関税の2つの側面は、アメリカの内政と外交を同時に映し出す鏡であり、その展開は国際社会全体に影響を及ぼすであろう。
トランプ政権発足から3カ月を経て、トランプ関税は「特定品目関税」と「特定国関税」という2つの側面を持つことが明らかになった。
前者は財政赤字削減と産業保護を目的とした経済合理性を基盤とし、後者は移民対策や安全保障におけるディールとして政治性を強く帯びている。
この二重性は、トランプ大統領の統治スタイルを象徴するものであり、経済と政治の境界を越えた戦略的アプローチを示している。
【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】





